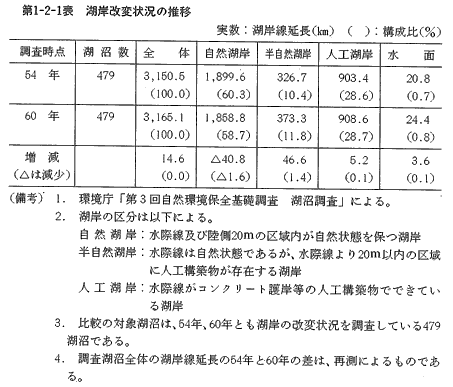
1 自然環境の保全の現状
「自然環境保全法」は自然環境保全の基本理念を明らかにするとともに、国の責務として、基本的かつ総合的な施策を策定し実施することを定めている。
(1) 自然環境保全地域
同法に基づいて、ほとんど人の手が加わっていない原生の状態が保たれている地域や、貴重な動植物、地形、地質等を含む自然が優れた状態を維持している地域等が、原生自然環境保全地域、自然環境保全地域、都道府県自然環境保全地域として指定され、我が国に残されている原生的な自然や優れた自然が総合的に保全されることとなった。62年度には、新たに、都道府県自然環境保全地域が3地域指定され、63年3月末現在、原生自然環境保全地域は5地域5,631ha、自然環境保全地域は9地域7,550ha、都道府県自然環境保全地域は496地域7万1,887haとなっている。合計面積では8万5,068haであり、全国土面積の0.2%である。
これらのうち、自然環境保全地域は、優れた天然林が相当部分を占める森林、野生動物の生息地等でその自然環境が優れた状態を維持しているもの等について指定を図るものであり、我が国の自然環境の保全を図るうえで極めて重要な地域である。このため、55年度から59年度にかけて原生自然環境保全地域において行った学術調査に続いて、60年度から自然環境保全地域の現況を詳細に把握し当該地域の保全に資するための調査を実施している。62年度においては栃木県の大佐飛山(おおさびやま)自然環境保全地域と熊本の白髪岳(しらがだけ)自然環境保全地域について調査が行われた。大佐飛山自然環境保全地域(面積545ha)は、下方ブナ、上部はオオシラビソの天然林が、また、稜線にはハイマツ郡落が残された優れた天然林の地域である。今回の調査においても、オオシラビソ、コメツガ、ダケカンバ等を主とする針広混交林やブナ林が維持されているほか、ツキノワグマやニホンカモシカ等が生息していることが確認されるなど、貴重な自然環境が残されていることが改めて明らかになった。
白髪岳自然環境保全地域(150ha)は、我が国の南限に近いブナ林やツガ林、モミ林が残された優れた天然林の地域である。今回の調査においても、ブナ林、ツガ林、モミ林等が維持されているほか、貴重な昆虫類等が生息していることが確認されるなど、貴重な自然環境が残されていることが改めて明らかとなった。
(2) 自然公園
「自然公園法」は、優れた自然の風景地を保護するとともに利用の増進を図ることにより、国民の保健、休養及びに自然に対する愛情とモラルの育成に資することを目的としている。
62年7月31日我が国最大の湿原でありタンチョウ等の貴重な野生生物が生息する釧路湿原が国立公園に指定され、63年3月末現在、国立公園28ヶ所205万ha、国定公園54ヶ所129万ha、また、都道府県立自然公園299ヶ所199万ha(合計533万haで全国土面積の14.1%)が指定されている。また、海中の景観を維持するため、国立公園及び国定公園の海面内の57地区2,398haが海中公園地区として指定されている。
自然公園の年間利用者数は、50年代は8億2,000万人前後で推移していたが、59年から徐々に増えはじめ、61年は9億717万人と初めて9億人を突破した(対前年比2.3%増)。
(3) 自然環境調査
環境庁においては、自然保護施策の推進のための基礎資料を得るため「自然環境保全基礎調査」を第1回(48年)、第2回(53〜54年)と実施し、第3回調査を58年度から62年度にかけて実施してきたところである。このうち調査結果の明らかになった「湖沼調査」(60年)及び「河川調査」(60年)によって、陸域の水辺環境の現況をみてみることとする。
ア 湖沼・河川の改変状況
湖沼調査は全国の面積1ha以上の天然湖沼(483)を対象に実施されたものであり、調査対象湖沼の総面積は約2,400km
2
、湖岸線の総延長は約3,000kmである。
これらの天然湖沼は、土砂の流入等の自然的要因あるいは干拓・埋立て等の人為的要因により、その数・面積が減少しつつあり、20年以降でみると、湖沼面積の13%が干拓・埋立てにより減少している。また、前回調査(54年)と比較すると調査対象湖沼のうち5湖沼が消滅あるいはほとんど湖の形状をとどめない状態となった。
湖沼の自然性という観点から、湖岸の改変現況についてみてみると、自然湖岸の比率は59%、半自然湖岸は12%、人口湖岸は29%である。これを、前回調査と比較すると自然湖岸立がやや減少し、半自然湖岸率がやや増加している(第1-2-1表)。
河川調査は全国の一級河川の幹川(109)、主要な支川(3)及び沖縄県の浦内川の計113河川を対象として実施された。
まず、魚類等生物の繁殖、生息の場として重要である水際線の状況についてみると、平水時の水際線が護岸等によって人工化されている割合は調査区間の総延長1万1,412kmのうち21%(2,442km)となっている。一般に北海道の河川や四国の太平洋に注ぐ河川の人工化の割合は低く、本州、四国の瀬戸内海へ注ぐ河川や九州の日本海、東シナ海に注ぐ河川の人工化の割合は高いといえる。また、前回調査(54年)と比較すると、人工化された水際線は全体で249km(2%)増加している(第1-2-2表)。
また、我が国の河川のすべてを対象としてその流域全体が原生的である「原生流域」(面積1,000ha以上にわたり、人工構造物の存在や森林伐採等の人為的な影響のみられない流域)を抽出したところ、全国で100流域(21万1,879ha)がこれに該当した。前回調査と比較して原生流域に該当しなくなったのは、11流域(1万7,386ha)である。また、100の原生流域の分布をみると、北海道(37流域)、東北地方(31流域)に集中して存在し、西南日本では離島(屋久島・西表島)に存在するのみである。
イ 魚類の生息状況
湖沼・河川の魚類の生息状況をみると、前回調査と比較して、ブラックバスをはじめとする外国産の移入魚が各地で分布域を拡大する傾向が認められ、交雑と生態的圧迫による在来種の減少が懸念される。また、清水性の魚類であるギギ類・トゲウオ類の生息する河川が減少しており、清水性魚類の生息環境の悪化が懸念される。
河川における魚類の遡上は、河川横断工作物をはじめ、河川の形状、水理特性、水質、魚類の生態的特性等の諸々の要因により規定されている。本調査では、それらの要因のうち河川横断工作物の設置状況について、魚類の遡上の可能性という観点から調査を行った。その結果、横断工作物がない、あるいは、あっても魚道がよく機能することなどにより、サケ、サクラマス、アユ等の遡河性魚類が調査区間の上流端まで遡上可能な河川は釧路川、後志利別川(しりべしとしべつがわ)(北海道)、名取川(宮城県)等13河川である。逆に、遡上可能区間が河川延長の一割に満たない河川は6河川あり、そのうち、瀬戸内海へ注ぐ河川が4河川を占めている。なお、調査河川延長に対する遡上可能区間の割合は、調査河川全体で平均すると約六割である。主要河川における横断交作物の設置状況と遡河性魚類の生息状況の関係(第1-2-3図)をみると、放流の盛んなアユは別として、サケ、サクラマスは横断工作物により、遡上が制限されていることが認められる。