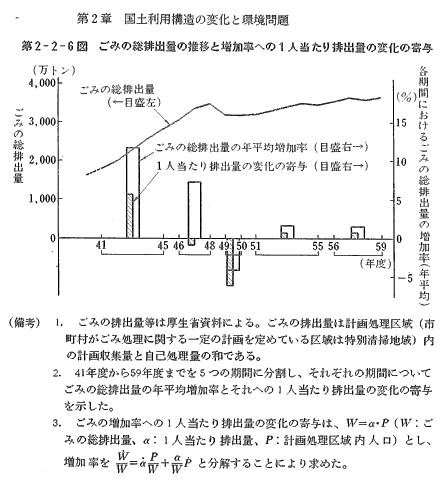
3 廃棄物
我が国では、高度な産業活動と消費生活を背景に膨大な量の廃棄物が発生し、しかも国土の限られた地域において集中的に発生しているため、その処理・処分が重要な課題となっている。
(1) 廃棄物問題の背景
我が国における廃棄物(し尿を除く。)の発生量をみると、ごみは4,300万トン(59年度)、産業廃棄物は2億9,200万トン(55年度)となっている。
廃棄物発生量の長期的変化をみると、ごみの排出量は、生活水準の急激な上昇に伴う1人当たり排出量の増加と計画処理区域内人口の増加により、40年代中頃まで急速に増加の一途をたどってきた。第一次石油危機以降は1人当たり排出量の低下もあって、一時減少したが、その後は緩やかに増加しつつある(第2-2-6図)。産業廃棄物については、全国的な統計が整備されている50年度と55年度を比較してみると、産業活動の高度化等により5年間で2割強増加している。
大都市圏についてみると、ごみの排出量は全国の総排出量の48%を占めており、面積当たりの排出量では全国平均の約5倍となっている。また、産業廃棄物についても、関東、中部、近畿地方で全国の産業廃棄物の6割が発生している(55年)。
そこで、特に発生が集中している東京都の状況を具体的にみることにする。まず、ごみについてみると、東京都では全国のごみの15%が発生しており、面積当たりでは全国平均の26倍にもなっている。また、1人当たり排出量も全国最高である。産業廃棄物については、全国の5.2%が発生しており、面積当たりでは全国平均の9倍となっている(55年)。東京都の調査によって発生量(上下水道業を除く。)を業種別にみると、57年においては建設業が60.6%を占めるが我が国全体をみると建設業の占める割合は1割程度にすぎず、建設業からの排出割合が高いことが特徴となっている(第2-2-7図)。
以上のような廃棄物の量の問題のほか、廃棄物の質も生活様式及び産業活動の高度化、技術革新の進展等に伴って多様化するとともに、現行の処理技術、システムでは適正な処理が困難な廃棄物が発生するおそれがある。
(2) 廃棄物の減量化
多様で膨大な量の廃棄物は、資源化や焼却などによる減量化等がなされた後、国土上に最終的に処分されていくこととなる。
ごみについては、収集されたごみは焼却による減量化や、リサイクル、堆肥化など資源化による減量化が行われている。減量化への寄与をみると、焼却による減量化によるものがほとんどであり、資源化によるものはごくわずかである(第2-2-8図)。
産業廃棄物については、再生利用と中間処理による減量化が行われており、最終的に処分が必要な量は発生量の4分の1程度である。発生量は50年から55年にかけて2割強の増加をみたが、こうした減量化の努力を反映して最終的に処分が必要な量は低下している。種類別に減量化の状況をみると、金属くず、廃油などは減量化が進んでいる。しかしながら、減量化が進んでいないものもあり、特に建設廃材については発生量の1割弱のみが再生利用・中間処理されているにすぎないほか、適正な処分が行われず、水田、畑、山林などに不法に投棄されている例も多い。
(3) 廃棄物の最終処分
近年、廃棄物の最終処分に必要な処分場の容量が、ひっ迫している。ごみの最終処分のための処分場の面積及び全体容量は経年変化の面では特に顕著な特徴はみられないが、残余容量は53年度以降減少傾向をたどっている。また、産業廃棄物についても最終処分場はひっ迫している。特に、大都市圏とその周辺地域においては最終処分場の確保が極めて困難となっている。東京圏、大阪圏については陸上に最終処分場の確保を求めることが難しくなっており、海面埋立ての割合が高まっている。特に、東京都区部においては、ごみの処分に関しては、20年代までは陸上処分が中心であったが、30年代はじめを境として内陸部での受け入れが困難となり、次第に海面埋立処分が増加し、50年代はじめからは全量を海面埋立てにより処分している。
全国でみるとごみの埋立処分地は、58年度において山間や平地などにあるものが面積でみて8割、海面にあるものが2割となっているが、今後、全国の毎年のごみ及び産業廃棄物の埋立処分量が59年度の実績の3,600万トン(ただし、産業廃棄物については法律に基づく届出のなされている施設に係る分のみ。)のまま推移するとし、仮にこれを深さ6.6m(59年度平均値)の埋立てで処分するとすれば10年間で約5,400haの面積になる(ただし、埋立処分の際にはしゅんせつ汚泥、陸上残土も使われているが、これらは直接計上はしていない。)。これはほぼ三宅島の面積に相当する膨大な量にのぼることになる。他方、大量の廃棄物が発生すると予想される大都市を後背地とする東京湾、大阪湾等の閉鎖性水域においては、貴重な自然や水面の確保に留意していく必要がある。
このため、廃棄物の発生量の抑制及び資源化、有効利用や中間処理による減量化を一層推進するとともに、計画的に最終処分場を確保していくことが必要である。なお、建設工事などに伴って発生する陸上残土についても発生量の削減、有効利用の促進等のための施策の確立を図る必要がある。
また、最終処分がなされた後の跡地は国土の一部を形成していくこととなるが、この最終処分場の跡地管理も重要な課題である。今後、埋立跡地の開発・利用が広がっていくとみられるが、この場合、ガス、悪臭、浸出液による環境影響や地盤耐力等についての配慮が必要となる。こうした跡地管理の技術については、必ずしも十分に確立されていないのが現状であり、今後環境汚染の未然防止を図るため取組を強化していく必要がある。