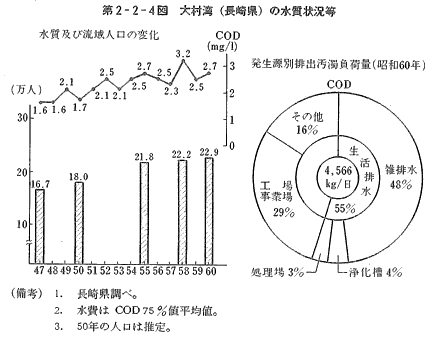
2 水環境
流域における経済社会活動の進展やそれに伴う土地利用の変化は、水質を始めとして水域の環境に大きな影響を与え、人と水のかかわりも変化させている。このような傾向は特に都市部で顕著であり、水環境の問題は重要な都市型環境問題となっている。さらに近年では、国土利用の変化に伴い、農村地域や上流域においても水環境の保全が課題となってきている。
(1) 水環境の状況
近年における水質の状況をみると、第1章でみたように、内湾や湖沼、都市内の中小河川を中心に改善が遅れている。また、開発の進行等により水質の悪化している水域もみられる。例えば長崎県の大村湾についみると、40年代末から開発が進み人口の増加が続いており、これに伴って水質も徐々に悪化してきている(第2-2-4図)。さらに、都市の周辺や農村地域においても身近な水域の水質汚濁の進行がみられる。
水質汚濁の要因をみると、近年、産業系の排水については、排水規制等により一定の効果がみられる一方、生活用水の使用量の増大等を背景に生活系排水が増大してきたため、生活系負荷の比重が高まってきている。特に、下水道等の生活排水処理施設の整備が十分進んでいないことから、生活雑排水の6割程度が未処理のまま放流されており、これが大きな汚濁原因となっている。例えば、東京湾、伊勢湾、瀬戸内海の3海域について流入する汚濁負荷の内訳をみると、59年度で産業系が35%、生活系が55%であり、生活系の負荷の占める比重が高い。
また、高度成長期においては、水道の普及等により身近な水域を利用する機会が少なくなったことや都市内の中小河川において防災上の理由などからコンクリート護岸や暗きょ化が進んだことにより、水辺の自然性が喪失し、人々の水辺とのふれあいの機会の減少がみられた。これに対して近年は、身近な水域を見直し、潤いややすらぎの得られる貴重なオープンスペースとして水辺を再評価しようとする気運が高まってきており、良好な水辺環境の形成のため、護岸の親水性の向上、環境改善のための用水の確保をはじめ、水辺と周辺の自然環境や歴史的環境の一体的保全など各地で多様な取組が行われている。
(2) 地域特性を踏まえた水質保全
次に、地域を自然的、社会的条件から、都市地域、都市近郊及び農村地域、上流地域の三つに分け、水質の状況や対応の在り方等についてみることとする。水質の保全を進めるにあたっては、流域全体も視野に入れつつ、以下のような地域の特性を踏まえながら対応を進めていく必要がある。
ア 都市地域
都市地域では、人口や産業活動が高度に集積しているため、水質に対する負荷も大きい。大都市圏を後背地にひかえた東京湾、伊勢湾及び瀬戸内海の水質総量規制地域についてみると、人口は6,300万人と総人口の約半数(59年度)、産業についても工業出荷額で全国の6割(58年度)を占めており、このような諸活動の集積のため水質の改善が進んでいない。下水道の普及率を東京湾地域についてみると、重点的な整備が進められているため、全国平均より高い普及率となっているが、埼玉県及び千葉県では未だ普及率が低い状況にある(第2-2-5図)。次に、河川の状況を大都市圏内の392の環境基準点でみると、BODの52〜54年の平均水質と58〜60年の平均水質を比較すると5mg/l(コイ、フナしか生息できない程度)を超える地点は43%から41%へ、うち10mg/l(日常生活に不快感を生じない限度)を超える地点は21%から17%へと減少しており、改善はみられるものの、依然汚濁の水準が高い地点が多い。
都市地域において水質の改善を図るためには、産業系の負荷の削減を引き続き行うとともに、生活系の負荷の削減について下水道等の整備の一層の推進に努める必要がある。また、既に下水道の普及した地域においても、都市再開発や業務活動の一層の集中等により汚水量の相当の増加が見込まれる場合には、処理能力の増強を図る必要がある。さらに、流域における開発の進行は、保水能力や雨水の浸透能力の低下を通じ、治水上の問題のみならず、河川や地下水の水量の減少や降雨時の面源負荷の増加等をもたらしている。このため、緑地など地下水のかん養域の保全や流域の保水・浸透能力の向上を図り、地域の水循環を回復させていくことが重要となっている。
イ 都市近郊及び農村地域
都市近郊においては、拡散的な市街化や農地との混住化の進行がみられ、生活排水処理施設の整備が不十分であることなどから生活雑排水による水質汚濁を生じ、生活環境の悪化や農業被害を招いている。また、農村地域においても、近年、都市的生活様式の普及により生活雑排水による水質汚濁が生じている。農業用水の汚濁による農業被害の状況をみると、60年における被害面積のうち都市汚水(農村における生活排水を含む)によるものは全体の79.3%を占めている(第2部196頁、第3-2-1表)。
このような地域では、下水道をはじめ、拡散的な市街地や集落単位のまとまりといった地域の特性に応じ、各種生活排水処理施設の整備を的確に組み合わせ、個々の家庭における負荷削減のための取組も含め、生活排水対策を総合的に推進していくことが重要である。さらに、今後市街地開発が見込まれる地域については、処理施設の先行的整備に努める必要がある。なお、今後とも混住化が進むなかで、畜産業についても適切なふん尿の処理・処分の一層の推進が求められる。
ウ 上流域
上流部の河川や湖沼については、周辺に森林や自然地域が多く人口や産業の集中も低いため、一般に水質が良好である。しかし、近年、開発の進行、レクリエーション利用の増大により、水源となっている湖沼の富栄養化による水道水の異臭味問題等が生じているほか、水質汚濁の進行により良好な自然環境が損われるとともに、観光面での価値も低下するおそれのある例がみられる。このような地域では、観光開発や産業立地を行う場合には、水域の持つ環境容量に十分配慮し、水質汚濁を生じないよう対策を講ずる必要がある。例えば、十和田八幡平国立公園の十和田地域についてみると、観光客数が45年の約270万人から60年の約390万人へと大きく増加しており、観光施設の集中している十和田湖湖畔で水質汚濁がみられるため、現在、下水道の整備が進められている。