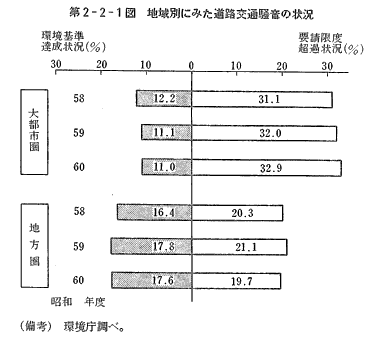
1 道路交通公害問題
交通量の多い幹線道路沿岸等では、自動車の走行に伴い発生する騒音、排出ガス等により、道路交通公害問題が発生している。
(1) 道路交通公害問題の現状
道路周辺における大気汚染を把握するため、沿道に設置されている自動車排出ガス測定局の測定結果をみると、一酸化炭素については、自動車に対する規制が逐次強化されてきた結果、すべての測定局で環境基準を達成している。しかしながら、二酸化窒素については、大都市圏を中心に未だ改善が遅れており、達成期限である昭和60年度内に環境基準を達成できなかった測定局が多く残されている。特に、総量規制が実施されている東京、大阪、神奈川の三地域の達成率は45%にとどまっている。
次に、自動車走行に伴う騒音についてみると、依然として環境基準の達成率は低く、市町村長が自動車騒音について対策を要請する目安となる要請限度を超過している地点も多い。地域別にみると、騒音が著しい地域は、大都市圏及び幹線道路沿線の都市地域に集中しており、特に、大都市圏では改善が遅れている(第2-2-1図)。
(2) 輸送構造の変化と国土利用構造からみた道路交通公害問題
道路交通公害問題は、大都市圏を中心に改善が遅れているが、その背景には近年における輸送構造の変化とともに、大都市圏と地方圏の国土利用構造の相違があると考えられる。
我が国の貨物輸送量は、高度成長期には年率10%程度の高い伸びを示していたが、第一次石油危機以降急激な落ち込みをみせた。その後、50年代半ばにかけて増加したものの、50年代後半はおおむね減少している。しかしながら、輸送機鑑別にみると、トラック輸送の比率が年々高まってきており、59年度には、国内貨物輸送量のうち、輸送トン数では90%、輸送トンキロでは46%をトラック輸送が占めており、貨物輸送の主力となっている。また、近年の貨物輸送は、経済のサービス化の進展、消費者ニーズの多様化等を背景に小口・高頻度化しており、こうした傾向はトラック輸送の優位性を高めるとともに、延べ輸送回数の増加をもたらしている。
一方、旅客輸送については、輸送人員、輸送人キロとも着実に増加してきている。なかでも乗用車輸送の伸びは大きく、59年度における国内旅客輸送量のうち、輸送人員では47%、輸送人キロでは44%を占めている。第2-2-2図は、東京、名古屋、大阪の三大都市を中心とする交通圏について旅客輸送分担率の推移をみたものであるが、公共輸送機関の分担率が低下しているなかで、自家用乗用車の分担率が増加してきているのがわかる。
次に、可住地面積当たりの自動車保有台数をみると、59年度末で5.8台/haとなっており、50年度末(3.7台/ha)に比べ約1.5倍に増加している。地域別にみると、大都市圏は地方圏の約3.5倍となっている。また、一般道路面積(道路面積全体から農道及び林道の面積を除いたもの。)当たりのトラック輸送トン数及び乗用車輸送人員については、大都市圏は地方圏の約2倍となっている(第2-2-3図)。
以上のように、貨物輸送、旅客輸送ともに自動車の占める比率が高まっている状況の下、大都市圏における交通構造は地方圏に比べ高密度なものとなっている。こうしたことに加え、我が国においては、幹線道路沿道に住宅地が隣接しているなど土地利用が適正でないことも道路交通公害問題の背景になっていると考えられる。例えば、建設省の58年度の調査によってDID地域における幹線道路沿道の土地利用状況をみると、高速道路では39%、一般国道では34%が住宅系の土地利用になっている。
したがって、道路交通公害問題を解決するためには、自動車から発生する排出ガス、騒音そのものを一層低減していくとともに、都市における交通構造、物流構造に着目した交通対策を総合的に推進していくことが重要である。併せて、幹線道路沿道の土地利用の適正化が図られるよう各種施策の推進に努めていく必要がある。