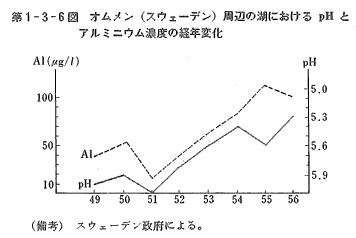
2 国境を越える環境問題
国境を越える環境問題として、酸性雨及び国際河川の汚染についてみてみよう。
(1) 酸性雨
酸性雨は、化石燃料の使用によって発生する硫黄酸化物、窒素酸化物が原因となって生ずると考えられているが、発生源から数千キロも離れた所に降下することがあり、欧州や北米において国境を越えた問題となっている。
酸性雨は、河川や湖沼を酸性化させ、魚類の減少等生態系に影響を与えたり、樹木や農作物に直接的に、あるいは土壌の変化を通じて間接的に影響を与えたりすることなどが知られている。欧州や北米では、酸性雨によるとみられる湖沼の酸性化や森林の被害のみならず、建物や文化財への被害などの現象が生じており、大きな社会問題となっている。
以下、スウェーデン政府の報告により酸性雨による湖沼への影響をみることにする。スウェーデンではここ数10年の間、近隣欧州諸国で発生した硫黄酸化物等によって生じたとみられる酸性投下物が増大しており、最近の南スウェーデンにおける年間硫黄降下量は、約2.0g/m
2
と自然降下量の10倍程度となっている。同時に雨のpH値は本来5.0以上であったとみられるのに対し、4.2ないし4.3へと酸性化が進んでいる。このため、多くの湖沼において魚類等への酸性投下物の影響がみられている。酸性湖沼での魚類の死滅はアルミニウム中毒によるものとみられるが、アルミニウム濃度は水域の酸性化が進むにつれて急激に増加する。例えば、スウェーデン南端部、バルト海を東に望む小さな町オムメン周辺の湖におけるpHとアルミニウム濃度の経験変化をみると、酸性化が進むとともに、アルミニウム濃度が上昇している(第1-3-6図)。
こうした湖沼の酸性化に伴う漁獲量の損失はスウェーデン全体で年間約850万ドル、また、これまでの累計の損失は約1億2,000万ドルに上るとされている。
(2) 国際河川の汚染
ライン川やドナウ川のような国際河川では上流の諸国が汚濁原因物質を排出しており、他方、下流の国々では、河川水を飲料水その他に利用していることなどから関係諸国間で調整が図られている。
ライン川についてみれば、西欧の経済発展と人口増加に伴って、その水質は悪化してきた。45年半ば以降には溶存酸素量の低下が深刻になり、大量の魚が水面に浮かび上がることが日常的にみられた。また、重金属や有機化合物のような微量汚染物質の排出量も増大し、とりわけ飲料水への影響が懸念されるようになった。
このため、51年に「ライン化学条約」及び「ライン川の塩化物による汚染防止条約」が成立するなど、ライン川の水質汚濁防止のための国際協力が進められてきた。こうしたことから、ライン川の水質は過去10年程の間に著しく改善され、溶存酸素量は正常値の80%にまで改善された。重金属の排出量は半滅し、特に水銀の排出量は90%の減少をみた。この結果、河川水中の重金属濃度はほとんど全ての金属について減少し、また、多くの有機微量汚染物質や油についても改善された。しかしながら、窒素、燐、塩素については十分な成果はあげられていない。
こうした中で、61年11月1日スイスのバーゼル郊外の薬品倉庫で火災が発生し、その消化作業中に水銀等の有害物質が大量にライン川に流出したため、漁業被害等が生じている。ライン川の下流に位置する国々は、事故により様々な影響を受けている。河口に位置するオランダでは事故から9日後に汚染水が到達している。オランダ国内の状況をオランダ政府が中間的に行った報告によってみると、西独との国境付近において水銀の測定値が汚染のピーク時で通常の3倍になったこと、運河や河川においては、魚類の大規模な死滅は発生しなかったがイトミミズや数種の昆虫の幼虫への影響が生じていること、などが明らかになっている。また、水道会社3社が9日間にわたりライン川からの取水を停止したり、漁業が一時停止されるなど社会的影響も生じている。また、オランダより上流の国々ではウナギ類が大量に死滅するなどの影響が生じている。