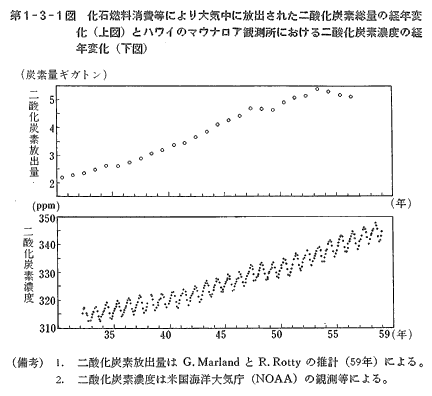
1 地球的規模の環境問題
(1) 大気
ア 温室効果を有する気体の気候への影響
対流圏(地球を取り巻く大気の最下層)中の二酸化炭素、亜酸化窒素、メタン、オゾン、フロンガスの量が増加している。例えば、化石燃料の使用の増大に伴い、二酸化炭素の排出量は20世紀半ば以降急速に増加しており、それにつれて、大気中の二酸化炭素濃度もハワイのマウナロア山の観測結果では、30年代以降年平均1ppm強の割合で上昇してきている(第1-3-1図)。また、同地点におけるフロンガスの濃度も上昇している(第1-3-2図)。
これらの気体は、太陽から地表にふりそそぐ日射エネルギーをほぼ完全に透過させるが、逆に、地表から放射される赤外線を吸収して宇宙空間に熱が逃げるのを妨げることから、地上気温を上昇させる「温室効果」を有するとされる。
全米科学アカデミーが58年に発表した報告によれば、大気中の二酸化炭素濃度は、21世紀半ば以降には現在の約2倍に達し、このため温室効果により地球全体で地上気温が1.5〜4.5℃上昇するとされている。この結果、気候の変化、極地地方の氷の融解による海面上昇がもたらされ、人類の生活に多大な影響を及ぼすと同報告は推定している。
また、二酸化炭素以外の温室効果を有する気体についても、気象等に及ぼす影響は重大であるとの指摘もある。
イ オゾン層の変化
成層圏(対流圏の更に上部)内のオゾン層は、紫外線の地上への到達量を制限する機能を有している。オゾン層が破壊されると、地表に達する紫外線の量の増大による皮膚ガンの増加、気候の変化等をもたらす可能性があると指摘されている。
エアゾール製品、冷媒等に利用されているフロンガスが環境中に放出された場合、分解されずに成層圏に達してオゾン層を破壊する可能性があることが指摘されている。OECDの推計によれば、昭和8年から50年間の累計で、全世界において、1,447万tのフロンガス(フロン11とフロン12の合計)が生産され、そのうち1,307万tが環境中に放出されている。
また、米国連邦航空宇宙局(NASA)が衛星を用いて54年10月から59年10月にかけて南極大陸で観測したオゾン量調査によれば、春期におけるオゾン量の減少が認められている(第1-3-3図)。
しかしながら、オゾン層の変化については、その状況、原因、影響等について未だ科学的な解明が十分には行われていない部分がある。
(2) 海洋汚染
海洋の汚染は、河川経由、沿岸排出、廃棄物・その他の物の海洋投棄、船舶の運搬及びこれに伴う事故、海底油田開発等が主要な原因である。
石油による海洋汚染は、多くの海域において引き起こされている。汚染のほとんどは、メキシコ湾内、欧州、日本のタンカー航路及び米国と欧州間のタンカー航路に沿って見受けられる(第1-3-4図)。
石油による汚染の発生は地域によって大きく異なっている。最も頻度の高いのは、フランスからポルトガルにかけての海域及び地中海であり、北海、バルト海ではそれほど頻繁ではない。欧州以外で油汚染が多いのは、カリブ海、メキシコ湾及びアフリカとインドネシアの沿岸である。
(3) 熱帯林の減少
熱帯林は、熱帯地方の開発途上国の人々の生活基盤となっているのみならず、生物種の宝庫であり、近年は遺伝子資源保存の観点からも注目されているほか、大気の浄化、土壌の保護、気象の緩和等人類を含む全生物の生存のために極めて大きな役割を果たしている。「熱帯林資源評価調査」(FAO/UNEP)によると、55年末の熱帯地域の森林面積は19.4億haで、その分布は、熱帯アメリカ役9.0億ha、熱帯アフリカ約7.0億ha、熱帯アジア約3.4億haとなっている。
一方、森林の減少は、56年から60年の間において年々約1,130万haに及ぶと推測されており、その主たる原因は焼畑移動耕作によるものとされている。
(4) 砂漠化の進行
熱帯林の減少と並んで砂漠化が進行している。乾燥・半乾燥の熱帯地方の開発途上国において、人口の増大から過度の放牧が行われたり、希少な樹木が燃料として過剰に利用されることなどから、毎年600万haの土地が不毛の砂漠に化しているとされている。
国際環境計画(UNEP)は砂漠化の危険性が高い地域として、サハラ砂漠以南の地域、「アフリカの角」と呼ばれる地域などをあげている(第1-3-5図)。
砂漠化の進行は、熱帯地方の開発途上国を中心に、人々の生存基盤を大きく揺るがす原因となっている。