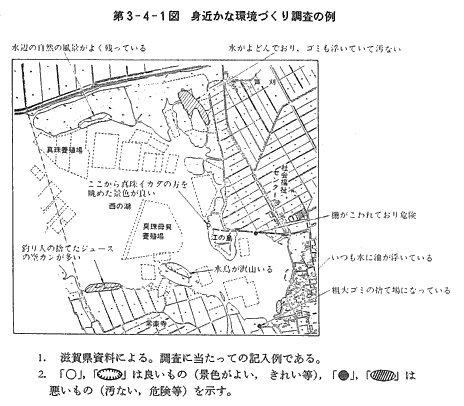
2 自主的な環境保全の推進
(1) 日常生活における環境への配慮
国民生活の変化や向上に伴い、国民と環境とのかかわりも従来とは異なるものとなっており、国民生活に起因する環境問題の比重が大きくなっている。
すなわち、国民生活の向上とニーズの多様化を背景としたマイカー利用の増大は、道路周辺の大気汚染や、沿道地域の騒音、振動などの自動車公害問題を引き起こすひとつの要因となっている。また、都市化の進展と生活様式の多様化によって生活雑排水が増大しており、都市内河川、湖沼等の水質汚濁の重要な原因となっている。さらに、消費の多様化、大量化は各種商品の使用後の廃棄物の増大と多様化をもたらし、都市における廃棄物の処理・処分が問題となっている。
このため、国、地方公共団体における環境保全施策の推進に加え、国民一人ひとりが日常生活においてできるだけ環境に与える影響を減らすなど、環境保全に配慮した行動を心がけていくことが重要となってきている。
ここでは、各種世論調査などによって、国民の日常生活における環境への配慮の実情を具体的にみていく。
総理府が60年10月に行った「自動車公害に関する世論調査」によれば、「ある程度自動車による公害が出ても生活が便利になる方がよい」と考えている者がかなり多く、45.8%となっているが、一方、自動車公害を防止するために、自動車利用の自粛や交通制限などが必要とされる場合、協力するとした者の割合は78.1%となっており、自動車公害問題解決への協力意識は高い。
また、河川、湖沼などの公共用水域の水質汚濁に関しては、台所やし尿浄化槽からの排水など生活系による発生負荷が高くなっている。例えば東京湾では、59年において約7割が生活系による負荷と推計されている。
台所からの排水による負荷を軽減させるためには、廃食用油をごみとして処理したりすることが必要である。例えば、環境庁が57年度に行ったアンケートによれば、廃食用油の処理について、新聞紙などに吸わせてごみとして処理している家庭が36.9%と最も多く、次いで土に埋めている家庭が19.0%、新聞紙などに吸わせて焼却している家庭が18.9%となっている。一方、流しに捨てている家庭は11.6%となっている。
近年深刻化してきた近隣騒音問題も、家庭用機器の低騒音化や住居の遮音性能の向上などの施策が求められる一方で、自動車エンジンの空吹かし音、室内等の足音、話し声、扉の開閉音など、日常のちょっとした気配りで近隣に与える迷惑を軽減することができるものも多い。総理府が58年8月に行った「近隣騒音公害・自動車公害に関する世論調査」によれば、自分の家で発生する騒音が近所の迷惑にならないように日頃から気をつけている者は、非常に気をつけている者(23%)とどちらかと言えば気をつけている者(55%)を合わせて、8割近くになっている。
以上みたように、日常生活において環境に配慮している、又は環境に配慮しようという意識を持っている国民は総じて多いといえよう。
(2) 自主的な環境保全活動の推進
こうした環境保全のための国民意識を背景として、国民の自主的な環境保全活動が各地で盛んになってきている。この動きは自らの手で住みよい愛着の持てる地域社会を保全・創造していきたいとする現われでもある。
このような環境改善に向けた国民の意識や努力を具体的な行動へと高めていくことにより、環境保全の一層効果的な推進を図ることが求められている。
例えば、滋賀県長浜市と安土町では、地域住民が参加して「身近かな環境づくり調査」を行っている。これは住民が身の回りの環境を診断し、目標を設定した上で、その達成に向けて実践活動を展開することを目的としている。予備調査においては、住民による現地調査などの結果が地図などにわかりやすく記述される(第3-4-1図)。これをもとに将来の身近な環境をつくっていく際の問題点とその解決策が「環境カルテ」としてまとめられ、地域の環境改善に役立てられている。
また、国民が環境保全のために行動するための機会を設けることが必要である。
環境庁では、厚生省とともに、58年度以来関係省庁、地方公共団体、事業者団体、各種民間公益団体等の協力を得て、「環境美化行動の日」を設定し、国民がこぞって環境美化に取り組むことを呼びかけている。この呼びかけに応え、60年度には都道府県・政令市で統一実施日が設けられ、全国の市町村数の80%に当たる2,614市町村で環境美化運動が行われた。参加人員は約890万人、収集ごみの重量は約6万3,000t、植栽された苗木の数は約110万本にのぼっている。
さらに、国民の環境保全活動を盛り上げるための支援が必要である。
環境庁では、59年度から生活雑排水対策実践活動を推進しており、例えば、手賀沼流域の柏市松ヶ丘地区(千葉県)等のモデル地区において、地域住民の参加を得て流し台に細かい目の網などを備え調理くずや食べ残しを流さないようにするなどのきめ細かい対策を行っている。