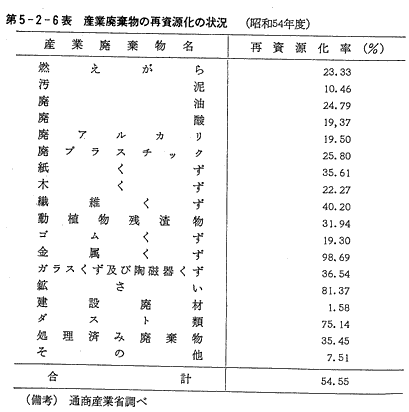
2 廃棄物処理対策
(1) 一般廃棄物
一般廃棄物処理施設の整備については、廃棄物処理施設整備緊急措置法に基づき、第5次廃棄物処理施設整備計画(昭和56年度〜昭和60年度)が策定されているところであるが、昭和59年度においてはし尿処理施設整備費補助金181億円、ごみ処理施設整備補助金411億円、埋立処分地施設整備費補助金54億円をもって施設の整備拡充を図るとともに新たに台所、風呂場等からの排水を処理対象とする生活排水処理施設に対する国庫補助制度(国庫補助金3億円)を創設し、その整備を図った。
また、モデル事業として行われている廃棄物運搬用パイプライン施設整備事業及び都市廃棄物処理管路事業に対して、それぞれ2億4,468万円及び2億5,300万円の補助を行った。
厚生省においては、廃棄物の減量化・資源化に関する調査、「家庭系特殊廃棄物の処理対策に関する調査」等を実施した。
また、環境庁・厚生省においては、ごみ処理に係る水銀、ダイオキシン等についての実態把握を行ったほか、環境庁は埋立処分後の水銀の挙動に関する調査を行った。
(2) 産業廃棄物
近年発生量が増大してきた建設木くず(建設業者が工作物を除去する際に排出される木くず)は一般廃棄物として市町村による処理が行われてきたが、処理の広域化等の処理体制の整備を図るため、59年4月から、産業廃棄物として処理が行われることとなった。
厚生省においては産業廃棄物の不法投棄等の不適正処理の防止を図るための「産業廃棄物不法投棄等防止対策調査」、政令で指定されていない産業廃棄物の処理施設の実態調査としての「未指定産業廃棄物処理施設精密実態調査」等を実施した。
なお、58年度における行政処分の状況は、立入検査51,361件、報告徴収20,066件、許可の取消し又は一時停止19件、措置命令又は改善命令15件となっている。
通商産業省では今後の廃棄物処理及び再資源化対策に必要な調査を行っており、都道府県又は大規模なコンビナート単位ごとに国、地方公共団体、事業者等が共同で、廃棄物の収集、中間処理、再資源化、埋立処分等を有機的に結合して行う総合システムの調査、設計を行った。
なお、製造業(電気・ガス業を含む)からの廃棄物の再資源化の状況は第5-2-6表のとおりである。
また通商産業省においては、廃棄物の再資源化を促進するため、(財)クリーン・ジャパン・センターのモデル都市における実証プラント・分別回収等の再資源化モデル事業、啓蒙普及・空缶等の散在性廃棄物の再資源化対策の推進、廃棄物交換のための情報提供、家庭から排出される粗大ごみ等の再資源化に関する調査研究等の各種の再資源化事業に対する補助を行った。
(3) 広域処理場整備の推進
廃棄物の最終処分場の確保が極めて困難になってきている大都市圏域において、圏域を一体とした広域的な最終処分場確保の要請に対処するため、厚生省及び運輸省においては、関係地方公共団体及び関係港湾管理者が共同で整備、利用する広域的な廃棄物の埋立処分場計画の推進を図ってきたが、大阪湾圏域においては、大阪湾広域臨海環境整備センターが広域臨海環境整備センター法に基づき広域処理場の位置、規模等を定める基本計画案の作成作業を行った。
また、首都圏については、関係地方公共団体により廃棄物の広域処理について検討が行われているところであり、厚生省及び運輸省においても前年度に引き続き広域処理場の整備に関する調査を実施した。厚生省においては中部圏及び北部九州圏についても基本調査及び予備調査を行った。
(4) その他
運輸省においては、港湾における廃棄物処理対策として48年度から廃棄物埋立護岸の整備に対する補助等を行っているが、59年度は、19港1湾において事業費約271億円(うち国費約73億円)をもって廃棄物埋立護岸の整備に対する補助及び広域処理場整備のための実施設計調査を実施したほか、廃油処理施設の整備及び清掃船の建造に対する補助さらに一般海域におけるごみ・油の回収事業を行った。
環境庁においては、廃棄物の埋立処分地跡地の管理手法等を検討するため、制度面、技術面の調査研究を行った。
さらに、建設省においては、環境保全に留意しつつ下水汚泥の緑農地利用、建設資材化等の資源化を図るとともに、広域処理処分に関する調査を進めている。