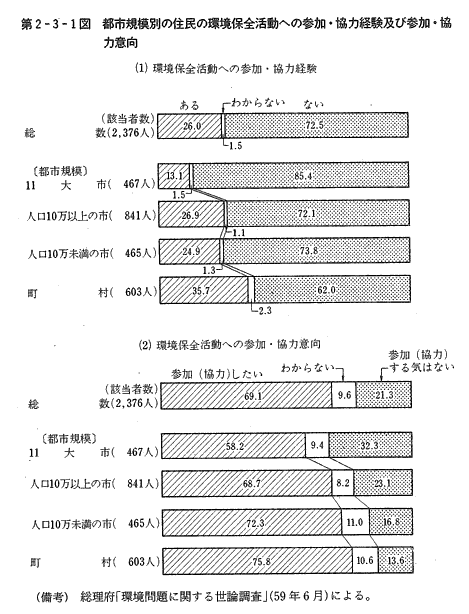
3 住民の参加と協力
都市においては、人口が集中し、豊かな生活が営まれていることから、生活雑排水や都市ごみの問題のように一人一人でみれば小さな環境負荷であっても、集積して環境に大きな影響を与えている場合がある。
また、住居が密集していること等から生ずる近隣騒音や積雪寒冷地域の都市部におけるスパイクタイヤ粉じんのように、住民が被害者となり、また加害者となる環境問題も生じやすい。
都市における環境問題の解決には、行政や事業者が取り組むべき課題も多いが、住民の協力も重要であり、ごみの分別収集に協力すること、騒音を出さないようにすること、あるいはスパイクタイヤの使用を自粛することなど身近なところから環境に対する負荷をなるべく小さくする生活・行動ルールづくりが大切である。
さらに、緑化や環境美化活動に市民が積極的に参加し、より快適な都市環境を創出していくことも重要となっている。
一方、都市の住民は、一般に定着率が低く、コミュニティ意識が稀薄なこと等から、総理府が59年6月に実施した「環境問題に関する世論調査」によると大都市の住民ほど環境保全活動への参加・協力の経験は少ないという結果が示されている(第2-3-1図)。しかしながら、同じ調査で、環境保全活動に参加・協力したいとする者の割合は11大市で約6割と、総じて都市市民の環境保全活動への参加・協力意向は高くなっており、このような意識を具体的活動に結びつけていくことが求められている。
このため、環境保全に関して、住民の意識啓発、地域組織の形成、指導者の育成等を図り、住民自身が、都市における環境のあり方を考え、その保全・創造を自主的に進めていくことができるような条件を整備することが必要である。