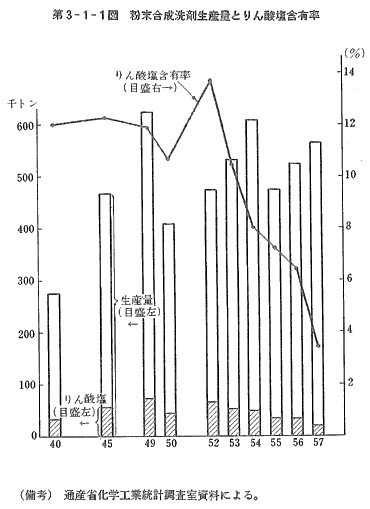
4 きめ細かな対策
近年、近隣騒音、生活排水、ごみ問題等日常生活に密着した問題が注目されており、きめ細かな対策が求められている。
近隣騒音のうち、カラオケに代表される深夜営業騒音については、対策の一層の推進を図るため、環境庁は、55年10月、都道府県知事に対し留意事項を示し、条例改正等必要な措置を講ずるよう要請した。これまでのところ、20府県が条例改正を行い、31都府県が音量規制などの具体的な措置を条例に定めるに至っている。
一方、ピアノ、クーラー、自動車の空ぶかしなどの生活騒音については、騒音の防止に関する意識の向上がまず必要である。このため、環境庁では、55年以来、近隣騒音防止ポスターを作成・掲示したり、「騒音を考えるシンポジウム」を開催するなどの啓蒙を行っているところである。このほか、住宅の設備・構造に起因する騒音についての遮音性の向上、クーラー、洗濯機、掃除機などの家庭用機器及びピアノなどの音響機器の低騒音化等の対策が必要である。
また、生活排水についても水質汚濁の原因物質の排出を極力抑制するため、有りん洗剤の使用の抑制や廃食油の適正処分等のきめ細かな対策が必要である。たとえば、滋賀県では、54年から条例によりりんを含む家庭用合成洗剤の販売・使用の禁止を行っているほか、多くの自治体でそのころから「合成洗剤対策推進要網」を定め、有りん洗剤の使用の抑制を図っている。この結果、洗剤メーカーにおいても低りん化を図っており、最近、生産される合成洗剤に含まれるりんの量は激減している(第3-1-1図)。
さらに、ごみ問題についても、ごみの発生量を抑制したり、ごみの再利用を図ったりするなどきめ細かい対策が必要である。たとえば、小学校の副読本として「ごみのはなし」という小冊子を作成し、清掃に関する知識を普及させ、また、廃品回収を行う住民団体に対し、回収量に応じて奨励金を出すことによってごみのリサイクルを図っている自治体も多くみられる。
また、散乱性のごみが地域の環境美化の観点から問題となっているが、一斉清掃の実施等環境美化運動の強化が図られており、また、分別収集の実施による再資源化も進められるなど、地域の実状に即して真剣な取組がなされている。