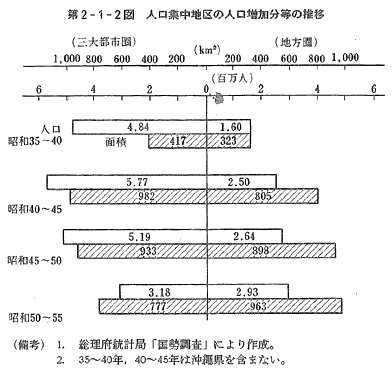
2 人口の都市集中と都市化の動向
我が国の人口分布の動向をみると、一時の急激な都市集中化傾向は鎮静化したものの、全体としての都市化は依然として進行している(第2-1-2図)。人口集中地区(DID)の居住人口でみると、35年から50年までの期間に4,100万人から6,400万人へと1.5倍強増加している。また、55年には約7,000万人、総人口の約6割が人口集中地区に居住している。
今後の20〜30年間は、全国的な都市化が大きく進展する最後の段階であると考えられる。巨大都市圏においては自然増を中心とした人口増による膨張と、周辺部への拡散的な市街化が進んでいる。また、地方中核都市ではその周辺市町村にまで市街地が拡大していくという都市圏の形成が進行しつつあり、地方中小都市では、一般に低密度、拡散的な市街地が形成されつつある。さらに、農村においては、都市との交流が一層強まり、都市と一体となった生活圏が形成されることが予想される。
こうした都市化の進展に伴って都市的な生活様式もさらに一層普及し、すでに顕在化している生活排水による水質汚濁、近隣騒音、自動車騒音等交通公害問題、廃棄物の不適正処理、身近な自然の喪失などの都市的な環境問題がさらに広がるおそれがある。
また、すでに成熟の段階に達した都市にあっても、都市は常に生成発展しており、今後ますます都市の再開発活動重要になってくることが予測される。このような都市再開発活動に際してはその環境への影響に配慮し、地域環境の改善に資するような再開発を進めることが望まれる。また、既存の建築物を取り壊して新たな建築物の建造(スクラップ・アンド・ビルド)が進んでいるが、その結果、大量の建築廃材や廃土砂などの不要物が排出されている。このような都市化や都市再開発に伴う廃棄物の管理も重要な課題である。
今後はこのような状況に対応して、計画的かつ先行的に生活環境施設を整備することなどにより、公害の発生と拡散を予防するとともに、さらに一歩進めて、地域の特徴を生かした快適な環境を整備することが重要である。
都市化の進展に伴う生活様式の変化の中で、人々が自然と直接ふれあう機会も少なくなってきている。このため、自然に対する直接的な体験を持たない世代が増加している。自然とのふれあいやその観察を通じて得られた正確な理解と愛着がなくては自然保護は図り得ない。多くの人々が自然とふれあう機会が少なくなっていく状態が続くならば、将来の我が国の自然環境の保全が憂慮される。人口の大多数が都市に住むことになった今日、自然とのふれあいの場を確保していくことは今後の重要な課題である。