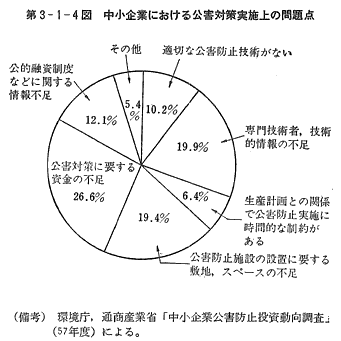
3 公害防止のための助成
公害防止は事業者の自発的な努力のみでは不十分なことがある。このため、「公害対策基本法」においては各種の規制措置を定めるとともに、その第24条において国は事業者に対し必要な金融上の措置などを講じるよう努めるべきこと、特に中小企業者に対しては特別な配慮を払うべきことを定めている。
近年、窒素酸化物、ばいじんなどの大気汚染物質、CODなどで示される水質汚濁等に関して規制の強化等が行われており、事業者の早急な対応が必要となっている。しかしながら、収益の改善に直接寄与しない公害対策を行うことには事業者にとって難しい面もある(第3-1-4図)。このような状況から事業者とりわけ中小企業者においては、公害対策の実施に際しての適切な公的助成に関し、強い要望がある。例えば、環境庁、通商産業省の「中小企業公害防止動向調査(55年度)」によると、公害対策資金の援助を要望する中小企業者が33%、公害対策技術指導を要望する中小企業者が21%などとなっている。
このような要請に答えるためにも、現在、公害対策を実施しようとする事業者に対しては、公害防止事業団、日本開発銀行、中小企業金融公庫等の政府系金融機関による資金の貸付が行われている(第3-1-5表)。また、税制面でも、公害防止施設等の設置を促進するため、特別償却、登録免許税の軽減、不動産取得税の特例、固定資産税の特例等の制度が設けられている。
このほか、公害防止事業団では、より直接的な助成事業を行っており、?複数の事業者が共同で使用する共同公害防止施設、?工場群と住宅地とを遮断する緩衝緑地、?公害の原因となっている工場の移転及び適地への集約化のために必要な工場移転用地や共同利用工場(工場アパート)を建設し、譲渡している。
さらに、中小企業者に対する公害対策技術指導等のため、全国の主要な商工会議所において産業公害相談室を設置し、事業者が適切な公害対策を行うための相談・指導を実施している。
このように、効果的な公害防止のためには、規制と相まって助成策が進められる必要がある。また、複雑、多様な交通公害問題、生活排水対策等の都市・生活型公害に対しても、産業公害対策とともに、各種の公害防止事業などの政策手段を総合的に活用し、公害防止計画等との有機的連携の下に、効果的な助成を図っていく必要がある。