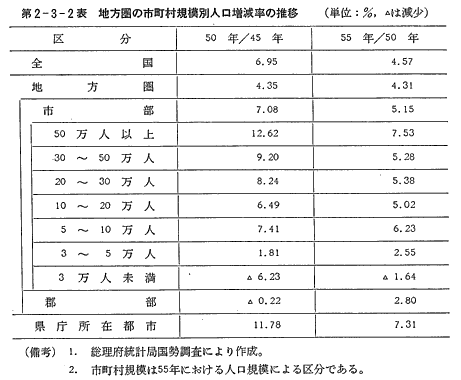
2 地方都市
地方都市は大都市圏に比べ自然性に富んだ空間に恵まれているが、近年の地方定住傾向の高まりなどによる人口の増加、都市化の進展などを背景として環境の変化が進んでいる。
50〜55年の地方圏の市部の人口増加率は5.2%と全国平均を0.6%ポイント上回る高い伸びとなっている。これを人口規模別にみると、人口5万人以上の市で増加率が大きくなっている(第2-3-2表)。中でも、人口50万人以上の市又は県庁所在都市における人口の増加が著しく、さらには、これらの地方中核都市を中心にその周辺市町村にまで市街地が拡大していくという都市圏の形成が進行しつつある。このため、今後、大都市的な環境問題が顕在化するおそれがある。しかしながら、地方都市では一般に低密度、拡散的な市街地が形成されつつあることは注目すべきであり、今後大都市のような過密状態の下で環境悪化がもたらされる前に、あらかじめ長期的観点からの環境を保全し、総合的な快適性を確保するための施策を講じる余地があるものと考えられる。
(1) 生活圏の広域化と交通公害
地方圏においても交通公害問題が生じてきているところもみられる。例えば地方圏においてもモータリゼーションが浸透し、自動車保有台数の伸びは三大都市圏を上回っている(第2-3-3図)。周辺市町村の居住者の地方中核都市への通勤が一般化し、都市機能の地方中核都市への集中が進むとともに、広域にわたって生活圏の一体化が進み、圏域内における日常的な人や物の流れが大都市圏と類似してきている。
地方圏では圏域内の交通をほとんど道路に頼っている所が多いことから、圏域内幹線道路においては、騒音、振動などの道路交通公害問題が生じている。 56年に地方圏の都道府県、市町村が当該地域の騒音を代表すると思われる地点又は騒音に係る問題を生じやすい地点において測定した自動車交通騒音の環境基準達成立率は17.9%と三大都市圏と同様に低くなっており、重要な問題となっている。
(2) 社会資本の整備
都市的生活様式は大都市圏に限らず地方圏においても急速に浸透した。しかし、地方都市においては、一般に下水道、道路等の根幹的な施設整備の面では立ち遅れがみられ、そのためこれらの整備に対する住民の要望が強い(第2-3-4表)。道路の適切な整備及び下水道の整備の促進は、より良い環境の形成にも資するものである。
このうち、道路については周辺土地利用を勘案し、沿道の交通公害を防止しつつ都市景観の創造等の機能も重視して、長期的視野から体系的な整備を図っていく必要がある。
また、生活排水等の処理については、都市的生活様式の浸透に対して施設整備の立ち遅れがみられ、水質保全のための条件は厳しい。このため、地方都市においても地域の特性に応じた処理施設の整備を図っていく必要がある。
以上のように、地方都市においては都市化の進展と拡大の下で、無秩序な開発が進行して環境が悪化する前に、公害の発生を防止し、自然環境を保全しつつ長期的観点から計画的な都市整備を進め、個性豊かで魅力ある都市環境を創出していくことが課題である。