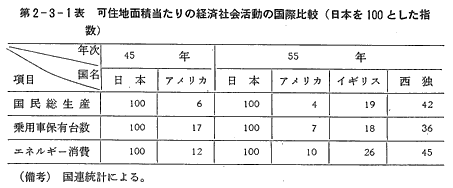
1 大都市圏
我が国では、既に欧米諸国と比べ第2-3-1表に示されるように過密な経済社会が形成され、このような状況の下で、多くの環境問題が生じている。特に大都市圏においては、人口と経済社会活動の集中により、地方圏に比べ環境保全上大きな問題が生じている。
三大都市圏は全国の約10%の面積を占めるにすぎないが、人口の集中傾向が一時に比べ鎮静化しつつあるものの、総人口の約45%が住んでおり、既に過密な状態が形成されている。加えて、特に東京圏については50年から55年の間に6.1%と、地方圏の4.1%を上回る率で人口が増加しており、依然過密化が進んでいる。また、商工業活動の面でも工業出荷額では全国の50〜60%、卸売販売額では全国の約70%を占めている。
このような状況を背景として、大気汚染、水質汚濁、騒音、振動等の公害の発生や自然改変が著しい地域等がみられる。
(1) 住環境
地方圏と比べ大都市圏において劣っている条件としては、まず住環境の問題があげられる。
大都市圏では、一部の地域においてはミニ開発におけるスプロール化が進み、市街地が密集して形成され、緑のオープンスペースはもとより、安全な歩行空間すら十分確保されていない状況もみうけられる。また、大都市圏では、地方圏に比べて集合住宅の割合が高く、これらの住宅には遮音性能の十分でないものも多く存在している。このため、近隣騒音や交通騒音の問題が一層深刻化していると考えられる。
住民は住宅及び住環境の質的向上を要望しており、今後は、このような要望にも沿って、地域の特性、美観、伝統、住民意識などにきめ細かく配慮した住環境の形成を図ることが必要である。
(2) 交通と環境
大都市圏における重要な環境問題としては、自動車、航空機、鉄道の運行に伴う交通公害があげられる。
自動車については、自動車走行量が増大しており、圏域内の交通が慢性的な渋滞を繰り返し、人口密集地帯を通過する一般国道43号沿道(兵庫県、大阪府)、都道環状7号線沿道(東京都)などにおいて、大気汚染や、騒音、振動などの公害問題が生じている。また、大阪国際空港周辺の航空機騒音、名古屋市内の新幹線鉄道沿線の騒音、振動などが問題となっている。
(3) 下水道整備の立ち遅れ
大都市圏に置いては、急激な人口集中地域の拡大に対して、一般に公共施設等の生活基盤の整備が後追いとなる傾向がみられ、環境が悪化している。中でも下水道整備が不十分な地域についての水質汚濁の問題が大きい。
都市的生活にとって下水道は欠かせないものであるが、下水道の整備には多額の投資を必要とすることから、その普及はどうしても人口増加の後追いとなりがちである。
40年代には工場排水や生活排水によって河川が著しく汚れ、悪臭さえ放つような状況であった。その後、下水道の普及率が向上するとともに、工場排水の規制等の効果と相まって、一時期の深刻な汚濁状況は脱しているが、なお都市内中小河川では高い汚濁状況にある(第1-1-6図参照)。
全国的にみれば、大都市圏の下水道は、全国水準よりは普及が進んでいるものの、いまだに多くの未普及人口を残しており、特に大都市周辺地域においては人口の増加に対し整備が立ち遅れている地域もみられ、これらの地域では、都市的生活様式の浸透に伴う生活排水の増加等によって水質汚濁の問題が生じている。
また、既に下水道の普及した地域においても、業務活動の活発化や昼間人口の増加によって汚水量が増加し、これに対処するため既設下水道の処理能力を向上させることが必要となっている場合もある。
(4) 廃棄物
大都市圏においては、活発な都市的活動によって大量の廃棄物が発生しており、これをいかに公害を出さず、かつ、効率的に処理していくかが重要な問題となっている。
すなわち、可燃ごみの全量焼却や不燃・焼却不適ごみの中間処理施設の整備がまだ必ずしもなされておらず、また最終処分場の確保についても将来的に不安があるなど多くの問題をかかえている。また、事業活動に伴って生じる産業廃棄物もかつてに比べ多種多様になっており、環境保全の見地からその適切な処分を図っていく必要がある。このように、大都市の廃棄物問題には解決すべき問題が多く、特に、新たな最終処分場の確保は、極めて困難な状況に直面している。このため、ごみの減量化と資源の有効利用を図ることが緊要の課題となっているとともに、廃棄物の広域処理場の整備を図ることが必要である。