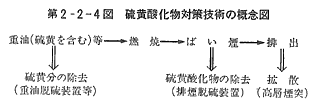
2 環境保全技術の動向
環境行政を進める上で、環境に関する科学技術の果たす役割は他の行政分野にも増して大きいものがある。例えば、
? 水俣病、イタイイタイ病等のさまざまな被害の原因究明
? 光化学スモッグ、赤潮等の発生機構の解明
? 大気、水、自然環境等の質に関する調査、測定、監視
? ばい煙、自動車排出ガス、排水、廃棄物等の処理技術を中心とする各種公害防止技術の開発
? 環境基準や排出基準の設定
? さまざまな開発が環境に及ぼす影響の調査、予測及び評価
等がある。
このうち規制に直接対応する技術として公害防止技術の開発状況を中心にみることとする。
(1) 固定発生源に係る大気汚染防止技術
二酸化硫黄などの硫黄酸化物対策の主な技術は、第2-2-4図のとおりである。明治以来の歴史を持つ高層煙突は、汚染物質を拡散し、稀釈させることにより、発生源周辺における濃度を低くしようとするものである。しかし、工業化が進むとともに、更に一層、硫黄酸化物の排出濃度を低下させ、排出総量を一定限度内に抑制することが求められることとなった。このため、重油脱硫装置、排煙脱硫装置の開発が進められ、40年代前半以降導入が図られている。
二酸化窒素などの窒素酸化物対策の主な技術は第2-2-5図のとおりである。排出規制に対応した技術としての燃焼改善法が広く普及しているほか、排煙脱硝装置の開発、導入が進みつつある。燃料中の窒素分の除去に資する技術は、現在、研究、開発中である。
ばいじん対策としては、電気集じん器が大正期以来実用化されており、現在では高性能なものが広く普及している。
(2) 自動車公害防止技術
自動車排出ガス低減技術については、窒素酸化物の低減を中心に研究、開発が進められてきている。ガソリン、LPG車では、触媒装置、排気ガス再循環装置等の技術の研究、開発が進められ、実用化されている(第2-2-6図)。ディーゼル車では、黒煙の増加をできる限り抑制しつつ窒素酸化物の低減を図るため、エンジン構造の改良、燃焼の改善等の技術の研究、開発が進められてきており、実用化されつつある。また、ディーゼル乗用車では、これらの技術に加えて排気ガス再循環装置の技術の研究、開発が進められている。
一方、自動車騒音低減技術については、エンジン、消音器等の改良、エンジンルームの遮へい等の技術の研究、開発が進められてきており、実用化されつつある。
(3) 水質汚濁防止技術
大都市圏にある水域あるいは流量が少ない河川などでは、生物化学的酸素要求量(BOD)、浮遊物質量(SS)等の環境基準を達成、維持していくことは困難なことがある。このため、下水処理の分野では高度な処理方法の開発が進められており、実験プラントの段階ではBOD5ppm以下の技術開発が実現している。
また、排水処理についての技術開発が進められているが、増大する費用の問題、大量に発生する汚泥の処理・処分の問題など解決すべき課題がまだ多く残されている。
なお、洗じょう水、製品処理水については、再生利用、循環利用するクローズド化が進んでおり、近年の汚濁負荷の公共用水域への流出削減に寄与している。