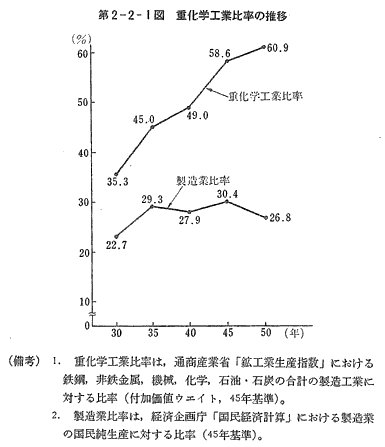
1 産業社会の発展と環境
戦後の経済は重化学工業を中心に拡大してきた。重化学工業の製造業に占める比率は30年には35%程度であったが、40年代には60%程度にまで達した(第2-2-1図)。この過程で多くの外国技術が導入され、それに刺激されて技術革新が進んだ。産業基盤の警備も進められ、道路、港湾等の交通施設の整備などが推進された。これらは経済成長に寄与し、人々の所得の向上、食生活や衣生活の大幅な改善をもたらし、便利な生活を確保することができることになった。しかし、同時に環境保全の観点からみればさまざまな問題を生じた例もある。
例えば、各地で進められた石油コンビナートの形成に伴う大気汚染、水質汚濁、悪臭等の問題がある。三重県四日市地区においては30年代前半から石油化学関連の工場が相次いで立地し、操業が開始されたが、36年頃からいわゆる四日市ぜんそくや異臭魚問題が生じた。
大都市地域においては、工業用水、ビル用水のための地下水の汲み上げ等による地盤沈下が著しくなり、建造物の亀裂などのほか、高潮による被害も生じた。
熊本県水俣地区では、アセトアルデヒド酢酸設備内で生成されたメチル水銀化合物により水俣病が引き起こされるに至った。
PCBは耐熱性や電気絶縁性にすぐれた化学物質で、かつては広範囲に利用されていたが、量によっては生命に危険があるほか、微量であっても長期間摂取すると人体に有害であることが明らかとなり、49年に製造、輸入、使用等が規制されている。しかし、PCBは残留性が強い化学物質であり、最近の調査においても、環境中に排出されたPCBが母乳、魚類等から検出されている。
また、各種の公共事業の実施に当たって、周囲の自然環境への影響に対する配慮がともすれば十分でなかったこともある。
公害の発生に対応するため、環境基準の設定や排出規制が各種汚染因子に対して本格的に整備され、40年代後半から50年代初めにかけては、公害防止投資は大企業、中小企業とも急速な伸びを示している。その後50年代に入ってからは、投資水準が下落してきたが、大企業においては54年度以降再び増加に転じている(第2-2-2図、第2-2-3図)。
近年、二次にわたる石油危機を契機に産業構造は大きく変化してきている。相対的には環境への負荷が大きい素材産業の生産は、エネルギー等原材料価格の上昇、需要の不振などによって全般的に低迷してきている。その反面、環境への負荷が相対的に小さい機械工業の生産が伸び、産業全般における比重を高めている。このような変化は、公害対策の進展とも相まって環境に対する負荷を相対的に軽くする効果をもたらしている。