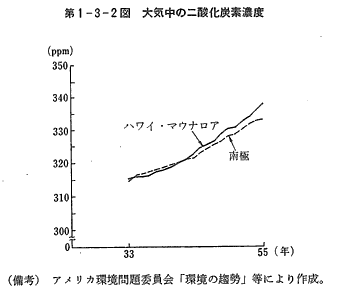
2 地球的規模での環境の状況
57年5月に、ケニアのナイロビで開催された国連環境計画(UNEP)管理理事会特別会合は、幾つかの無統制又は無計画な人間の行為はますます環境の悪化を引き起こしていることを確認した。同会合によると二酸化炭素濃度の上昇等の大気の変化、海洋の汚染等が一層深刻となっているほか、森林の減少や砂漠化も広がっており、地球的規模での環境問題についての関心が高まってきている。ここでは、地域的規模での環境の状況について、UNEPが作成した報告書「世界の環境1972−1982年」を中心にみることにする。
(1) 大気
大気中の二酸化炭素濃度が主に化石燃料の使用と森林伐採の結果次第に上昇してきている。ハワイのマウナロア山の観測所では、32年以降年平均約1ppmの割合で二酸化炭素濃度が上昇しており、45年には326ppmであったものが55年には338ppmとなっている。この上昇傾向は南極等でも観測されている(第1-3-2図)。二酸化炭素濃度の上昇は地表からの熱放射を妨げ、気候や氷雪地帯の分布を変化させる可能性を持つものである。
そのほか、フロンガスの成層圏オゾン層に対する影響等について調査研究が進められている。
(2) 海洋の汚染
多くの海域で油や下水、農薬などによる汚染が引き起こされている。油による海洋汚染については、高い頻度で油濁が発見されている海域がある(第1-3-3図)。
その発生源をみると、第1-3-4図に示されるように河川と都市排水によるものが最も多く、全体の約30%であり、次いでタンカーによるものが約25%となっている。なお、タンカーの事故は狭小な海域に大量の油を放出し、大きな損害を引き起こすことが多い。
このほか、我が国を始めとする工業国が販売禁止等の規制を実施しているDDTなどの殺虫剤がアジア太平洋地域等の開発途上国では依然使用され続けており、今後このような化学物質による海洋汚染の拡大が懸念される。
(3) 土壌悪化
開発途上国を中心に、人口増加のため、食糧の増産が強く要請されている。このため、国によっては、焼畑農業やかんがい地を広げることによって耕地を拡大している。熱帯雨林地域などでは、焼畑耕作の短期間における繰り返しや、森林の皆伐などによって土壌侵食が進み、乾燥地域などでは過度の放牧、樹木の燃料利用などによって砂漠化が進行し、不適切なかんがい排水などによる土壌の塩類集積、アルカリ化などによって土壌が悪化している地域がある。
砂漠化については、毎年、我が国の四国と九州の面積の合計にほぼ等しい600万ヘクタールの土地で進行しているとされている。
また、土壌浸食による土壌の喪失量は世界全体で年間約250億トンにのぼるといわれており、これは、日本全国の土壌が深さ5cm以上にわたってはぎとられたのとほぼ等しい量である。さらに、乾燥地域、半乾燥地域のかんがい地域では湿地化、アルカリ化が激しく、かんがい土壌のうちシリアのユーフラテス谷では約50%、エジプトでは約30%、イランでは15%以上がその影響を受けているとされている。
このような土壌の悪化によって土地の農業生産力が減退し、安定した経済社会活動の維持に大きな障害となっている。
(4) 熱帯林の減少
国連食糧農業機構(FAO)やUNEP等の国際機関は、最近の熱帯林の減少などに対し、熱帯林の減少が土壌悪化や地すべりなどの原因となり大気中の二酸化炭素濃度の上昇にも結び付くとして、さまざまな警告を発している。
FAOが調査した76ヶ国において、熱帯林の面積は約19億ヘクタールと推定されている。このうち約12億ヘクタールが、植生相が地表の全部又はその大部分をおおっている森林である(第1-3-5表)。
また、熱帯林は広葉樹林と針葉樹林から形成されているが、大部分は広葉樹林であり、地域的には、その56%が熱帯アメリカに分布しており、特にブラジルだけで全体の31%を占めている(第1-3-6図)。
このような熱帯林については、その急速な減少が世界各地でみられている。その原因としては、発展途上国における人口増加を背景とした焼畑農業の拡大と、燃料用木材の伐採の増加のほか、世界的な木材需要増による森林の伐採があると考えられている。
熱帯林の伐採は、年々進んでおり、熱帯76ヶ国だけみても、広葉樹林からは毎年約1億3,500万立方メートルが、針葉樹林からは約1,700万立方メートルが伐採されていると推定されている。
我が国は最近5年間の年平均で、約4,000万立方メートルの木材(丸太、製材)を海外から輸入しており、そのうちインドネシア、マレーシア、フィリピン等の熱帯林からの輸入が約2,000万立方メートルである。