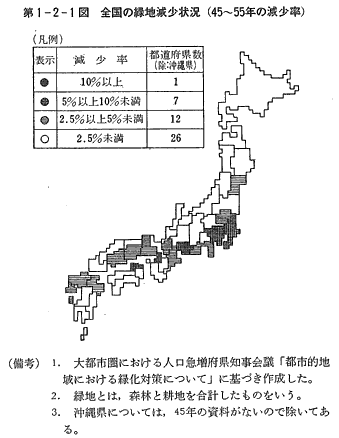
2 土地利用の変化と自然環境
自然環境の状況は土地利用と密接な関係にある。森林、原野は、林業生産等の場であるとともに、生態系の重要な一部を構成し、自然性の高い緑地としてさまざまな環境保全機能を果たしている。また、農用地は農業生産の場であるとともに、大都市地域などでは、緑地としての役割も大きい。さらに、河川、湖沼や海岸及びその周辺は古くからの生産や生活の場であり、その意味で人の活動と密接にかかわってきた。ここではこれらの土地利用に着目して、自然環境の状況の推移をみていくことにする。
(1) 森林・原野
我が国の森林面積は、55年には2,526万ヘクタールであり、50年の2,518万ヘクタールに比べ、全体としてはわずかながら増加している。
地域別にみると三大都市圏(埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、三重、京都、大阪、兵庫の各都府県)では、50年の207万ヘクタールが55年には205万ヘクタールと2万ヘクタールの減少となっている。一方、地方圏はそれぞれ2,311万ヘクタール、2,321万ヘクタールであり10万ヘクタールの増加となっており、森林面積の増加が主として地方圏におけるものであることを示している。なお、1人当たりの森林面積でも、三大都市圏は地方圏の9分の1にすぎない。
森林のうち人工林は45年に比べ55年には24.4%増加しているのに対し、天然林は10.2%の減少となっている。
次に、原野の状態をみることとする。原野には特異でしかも貴重な植生が多く、例えば湿原においては、北海道のツルコケモモ、ミズゴケ群落や沖縄県西表島の浦内川河口のミミモチシダ群落が知られている。
三大都市圏には原野がほとんど存在せず、地方圏においても次第に減少しており、原野の面積は50年の41万ヘクタールが55年には33万ヘクタールとなった。
(2) 農用地
農用地面積は50年は575万ヘクタールであったが、55年には561万ヘクタールと14万ヘクタールの減少となっている。これを地域別にみると三大都市圏では4万ヘクタール、地方圏では10万ヘクタールの減少となっており、減少率はそれぞれ5.7%、2.0%となっている。
また、森林と農用地のうち耕地とを合わせた緑地の面積を見ると、大都市圏内の都府県での減少率が大きく、大阪府では、10%を超える急激な緑地の減少がみられる(第1-2-1図)。
なお、緑地に対する人々の意識を56年度の「自然保護に関する世論調査」(内閣総理大臣官房広報室)によってみると、居住地の周辺が「緑の自然に恵まれていない」が17%となっており、特に東京都区部及び10政令指定都市では36%と非常に多くなっている。
(3) 水面、河川等
河川、湖沼等の陸水域の面積は50年には113万ヘクタールであったが、55年には115万ヘクタールと2万ヘクタールの増加となっている。
このような水辺は、人々の日常生活に深い係わり合いを持っている。環境モニター・アンケート「身近な水辺について」によれば、日頃接している水辺が「ある」は67.6%、その水辺までの時間は「10分以内」が71.5%となっている。しかし、都市の人口規模が大きくなるほど水辺までの距離が遠く、接する機会も少なくなっている(第1-2-2図)。
また、日頃接している水辺に対し、「満足」は26.1%となっており、その理由は広々として開放感がある、景色がよい、水がきれいだ、スポーツ・魚つり等の利用に都合がよい、自然が豊かであるなどである。しかし、「不満」も多く、全体の28.5%になっている。
さらに、今後の水辺環境のあり方に関し、66.4%の回答者(複数回答)が都市内を流れる中小河川についてはコンクリート等でふたをして安易に暗きょ化せず、まず川をきれいにして、できるだけ川を残すように努力すべきだと指摘しており、次いで、「跡地の環境整備がなされて、公園、緑道等に生まれ変わるのならよい」(31.9%)、「暗きょ化することによって道路、駐車場等有効な土地利用ができるのだからよい」(23.1%)などとなっている。