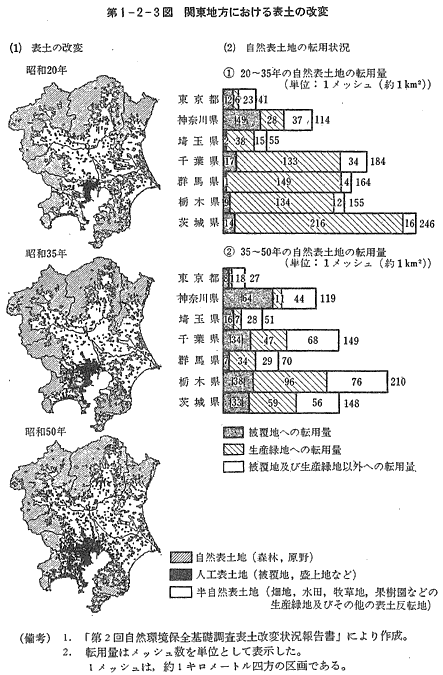
3 都市化の進展と自然改変
都市化の進展とともに自然の改変が進んでいる。宅地化の進行や交通機関の発達を伴う都市化の進展により、森林や原野の自然表土地が減少し、人工の構築物におおわれた被覆地が増大している。このため、土壌への水の浸透が少なくなり、流域への降雨水が短時間のうちに河川に集中して小河川のはん濫や傾斜地でのがけ崩れが起こりやすくなっている。
表土改変状況について「自然環境保全」に基づく「第2回自然環境保全基礎調査」(いわゆる「緑の国勢調査」)の表土改変状況調査により関東地方についてみると第1-2-3図に示されるとおりである。
戦勝直後から高度経済成長期までの間(20〜35年)においては、急速な市街地の拡大がみられた東京都及び神奈川県で自然表土地が高い比率で被覆地に転用されている。その後35年から50年にかけては、東京都では、被覆地への転用は減少しているものの、周辺の埼玉、千葉、茨城、栃木の各県での被覆地への転用が著しくなっている。また、群馬県でも被覆地への転用が次第に増加してきている。
この結果、関東地方では第1-2-3図に示されるように、20年頃には比較的広範囲に残されていた自然表土地が急速に減少し、50年頃には多くの地域が被覆地となってきている。
表土は自然の浄化能力を維持し、動植物の生息、生育の基盤となるなどの重要な機能を持っており、このような表土の自然性が減少していくことは、環境に対するさまざまな影響をもたらすことになる。