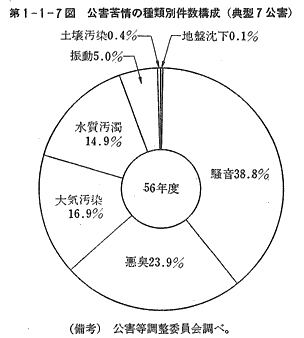
3 騒音、振動、その他
騒音、振動、悪臭、土壌汚染及び地盤沈下は、大気汚染や水質汚濁と並んで典型7公害と称されるものである。
また、廃棄物、化学物質は、その処理の仕方によっては環境の悪化をもたらすこととなる。
(1) 騒音
騒音は、振動、悪臭と並んでいわゆる感覚公害に属しており、日常生活に密着した公害であることから、例年、典型7公害のうち、地方公共団体に寄せられる苦情件数が最も多く、全体の40%近くを占めている(第1-1-7図)。
発生源は多種多様にわたっている。これを苦情件数でみると、工場・事業場騒音、建設作業騒音が全体の約半数を占めているが、減少傾向にある。飲食店等の深夜営業騒音を始めとする営業騒音に関する苦情件数は全体の約4分の1を占めている(第1-1-8図)。
また、一部の交通施設周辺に置いては自動車、航空機、新幹線鉄道等の運行に伴って発生する騒音が住民の生活に障害を及ぼしている。
(2) 振動
振動の発生源を苦情件数でみると、工場・事業場、建設作業振動に関するものがそれぞれ約40%を占めている(第1-1-9図)。
また、近年、人の耳には聞きとりにくい低い周波数の空気振動(低周波空気振動)による影響が注目されてきている。
(3) 悪臭
例年、地方公共団体に寄せられる悪臭に係る苦情件数は、騒音に次いで多い。悪臭の発生源は畜産農業、飼料・肥料製造工場、食品製造工場、科学工場等が主要なものである。これを苦情件数でみると畜産農業に関するものが最も多く、全体の30%近くを占めている(第1-1-10図)。
(4) 土壌汚染
土壌汚染は、大気、水等を媒介として排煙や排水中に含まれる重金属等の有害物質が土壌に蓄積し、それにより長期間にわたり、農作物等に悪影響を与えるいわゆる蓄積性汚染の典型である。
土壌汚染については、「農用地の土壌の汚染防止等に関する法律」(「土壌汚染防止法」)において、カドミウム、銅、砒(ひ)素が特定有害物質に指定されており、汚染地域及び汚染のおそれのある地域について調査等が実施されている。56年度までの調査によると、土壌汚染地域とその推定汚染面積はカドミウム88地域(約6,060ヘクタール)、銅37地域(約1,360ヘクタール)、砒(ひ)素13地域(約400ヘクタール)となっており、重複を除くと全体としての土壌汚染地域は124地域、推定汚染面積は6,610ヘクタールとなっている。これらの地域については、「土壌汚染防止法」に基づく所要の対策が講じられている。
「土壌汚染防止法」に基づく対策地域としては、58年1月末までにカドミウム42地域、銅11地域、砒(ひ)素5地域となっており、重複を除くと全体で49地域、約5,050ヘクタールが指定された。指定地域のうち45地域、約3,230ヘクタールについて対策計画が策定され、客土、排土、水源転換等対策事業が完了実施されている。このうちに地域、約560ヘクタールについては対策がして対策地域の指定解除が行われている。
また、県単独事業等により42地域(約330ヘクタール)について対策が講じられているほか、その他の地域についても調査や地域指定の検討が進められている。
(5) 地盤沈下
公害としての地盤沈下は地下水の過剰採取を原因として生じるものであり、これにより多くの地域で建造物、治水施設、港湾施設、農地及び農業用施設等に被害が生じている。地盤沈下は、地形、地質、土地利用等の状況の差異により沈下の程度や被害の状況が大きく異なるという極めて地域的特性の強い公害である。
現在まで地盤沈下の認められた主な地域は全国36都道府県、60地域である。全国の主要地域における最近の地盤沈下は、かつてのように全国的に著しい沈下を示すような状況はみられなくなったが、56年度においては前年度に比べ沈下量が増加した地域数が増えるなどの状況がみられた。
(6) 廃棄物
廃棄物は生産、流通、消費活動等に伴い発生するものである。日常生活に伴って生ずるごみについてみると、48年の第一次石油危機後、排出量は減少したものの、その後大きな変化はみられない(第1-1-11図)。
厚生省の調査によれば、一般廃棄物のうちごみの発生量は55年度でも4,400万トン(50年度は4,200万トン)、市町村の計画処理区域内におけるくみとりし尿(し尿浄化槽汚泥を含む)は、4,600万キロリットル(同3,900万キロリットル)である。産業廃棄物の発生量は50年度で同2億4,000万トンとなっている。
また、年間90億本程度生産されている缶飲料の空き缶等の一部が散乱し、地域の環境美化の観点等から問題となっている場所もある。
(7) 化学物質
現在使用されている化学物質は数万点にも及ぶが、化学物質の中にはPCB等のように難分解性、蓄積性、慢性毒性といった性質を持ち、環境を汚染し、人の健康を損なうおそれのある物質がある。
これら化学物質については、環境汚染の未然防止を図るため、49年度より分解性、蓄積性、毒性に関する点検及び環境中の濃度レベルを把握するための化学物質環境調査を実施してきており、現在までに7物質が「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」上の特定化学物質に指定されている。