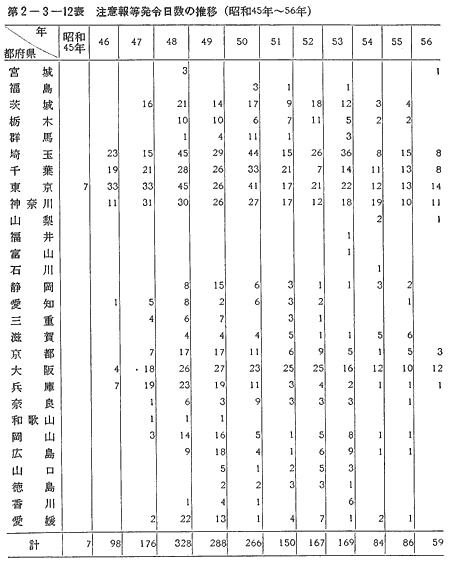
4 光化学大気汚染対策
45年夏以来、毎夏光化学大気汚染によると思われる目の刺激、のどの痛み、胸苦しさ等を典型的な症状とする健康被害が発生しているが、大気汚染防止法第23条にのっとり、地方公共団体では光化学オキシダント緊急時対策要綱等を定め、光化学オキシダント濃度と気象条件に応じて、予報、注意報、警報等を発令し、発生源対策と住民対策を実施してきた。
(1) 光化学大気汚染の発生状況
? 全国の注意報等発令状況
56年の光化学オキシダント注意報(光化学オキシダント濃度の1時間値が0.12ppm以上で、気象条件からみて、汚染の状態が継続すると認められるとき発令される。)の発令は9都府県に及び、注意報の発令日数は、54〜55年の約7割にあたる延べ59日であった(第2-3-12表)。
注意報等の発令日数の多い夏季について月別発令日数をみると、6月に11日、7月に26日、8月に11日となっており、7月を除き比較的光化学大気汚染の発生しにくかった気象条件の影響を反映し、注意報等発令日数は比較的少なかった(第2-3-13図)。
光化学オキシダント警報(地方公共団体により発令基準は異なるが、通例光化学オキシダント濃度の1時間値が0.24ppm以上で、気象条件からみて汚染の状態が継続すると認められるとき発令される。)は、本年、発令されなかった。
? ブロック別注意報等発令状況
光化学オキシダントの発生は、各地域の気象、地形、発生源状況等の条件の差異に大きく影響を受けると考えられることから、東京湾地域、伊勢湾地域、大阪湾地域及び瀬戸内海地域の4ブロックに区分し、最近5ヶ年の注意報等発令日数の整理を行った(第2-3-14図)。
本年においては、伊勢湾地域と瀬戸内海地域に発令がなかったため、東京湾地域の発令日数が全国の7割、大阪湾地域の発令日数が全国の約3割弱となっており、発令のほとんどが、これら主要2地域に限られたことが特徴的であった。
? 注意報等発令日における最高濃度
東京湾地域では、56年7月7日から22日まで、連続16日間、最高気温が30℃を超える日(東京管区気象台気象表による)が続き、特に16、17日の両日は、それぞれ34℃を超えた。この間の7月15日から20日まで南関東地域において6日間連続して注意報の発令があり、被害の届出が集中するとともに、56年の最高の光化学オキシダント濃度0.21ppm(7月17日、神奈川県相模原市)を記録した。
? 被害届出人数
56年の光化学大気汚染によると思われる被害者の届出人数(自覚症状による自主的な届出による)は、昨年の約1/2にあたる780人で、そのほとんどが7月に集中した(第2-3-15表)。なかでも、7月16日には、東京都町田市において6年振りに3名の入院患者が発生した。なお、同日、同市上空約350mの地点で0.26ppmのオゾンを含む高濃度の汚染気塊が航空機調査により観測されたことは、被害との関連において注目された。
? 光化学大気汚染監視体制及び緊急時対策
大気汚染防止法第23条の緊急時報(注意報等)発令の判断に必要な気象データを得るため、環境庁では、毎夏季に光化学大気汚染の発生しやすい全国4地域(10か所)で気象観測を行い、地方公共団体に気象情報の提供を行っている。また、気象庁では、全国8か所の大気汚染気象センター及び11か所の大気汚染気象予報業務担当官署で光化学大気汚染の発生しやすい気象条件の解析と予報を行い、地方公共団体に通報している。これら情報と測定局データを基に、地方公共団体では光化学オキシダント緊急時対策要綱等により注意報等を発令すると同時に、ばい煙排出者に対し、大気汚染物質排出量の削減を要請し、また、住民に対する広報活動を開始する等のシステムを採っている。
(2) 光化学大気汚染調査研究の推進
光化学大気汚染は、広域にわたる極めて複雑な現象であり、それに関する調査も、光化学反応機構、移流拡散等の気象の影響、原因物質の排出実態、それらを盛り込んだ光化学大気汚染予測モデル、更には、二次生成物質の健康影響や光化学オキシダントによる植物影響など広範な分野にわたって行われており、それぞれ貴重な知見が得られている。
まず、光化学反応論の分野では、移動用スモッグチャンバーを用いた環境大気の光酸化反応の研究と国立公害研究所の大型スモッグチャンバーを用いた各種炭化水素−NOx-加湿空気系等での光酸化反応の研究が並行して行われている。これら研究により初期一次汚染物質濃度と主要反応生成物質濃度との関係、諸々の中間生成物、最終生成物の生成機構等についての解明が進められ、全体として、光化学反応のより詳細で精密な理論化に向けて研究が着実に進展している。
一方、このような光化学反応理論の進展と同時に実際の環境大気中での光化学大気汚染の実態把握も極めて重要な分野であり、航空機を用いた光化学反応関連物質の水平・垂直分布に関する調査やパイロットバルーンやゾンデを用いた上層気象に関する観測を行い、これらの実態把握に努めるとともに、地上の汚染物質濃度や地上気象との関連、光化学大気汚染における気象条件の関与等についても解析を進めている。
さらに、上述の各種調査研究で得られた光化学反応モデル及び汚染質と気象に関する上層データに、一次汚染物質の排出に関するデータ及び常時監視による地上データを加え、光化学オキシダントの時間値を定量的に再現する物理化学モデルの研究も進められてきた。50年度よりはじまったこの研究では、東京湾地域等を対象に夏季の特定日の光化学大気汚染現象の再現計算を行い、モデルの精度向上に努めてきており、こうした成果を踏まえ、光化学スモッグ等の広域的大気汚染に適切に対処しうるよう配慮しつつ、今後、緊急時対策として具体的に活用していくこととしている。
(3) 光化学大気汚染の原因と防止対策の考え方
各種の調査研究結果から、光化学大気汚染の主要な原因物質は窒素酸化物と非メタン炭化水素であり、オゾンがその主要生成物であることが明らかにされている。
しかし、オゾン以外の光化学反応による二次生成物質であるPAN(パーオキシアセチルナイトレート)やアルデヒドについても健康影響の点から重要視されており、オゾンの低減化対策のみでは、光化学大気汚染の防止対策としては十分ではない。また、広域的光化学大気汚染の問題に対処するためには、光化学反応系における原因物質の総量を削減することが緊要である。
このようなことから、大気の移流拡散現象をも考慮して、広域にわたる光化学大気汚染の発生を効果的に防止するためには、窒素酸化物及び非メタン炭化水素の双方を低減することが必要である。
(4) 炭化水素類排出抑制対策
ア 固定発生源からの炭化水素類排出抑制対策
炭化水素類とは、炭素原子と水素原子あるいはこれらと他の原子から成り立っている化合物の総称であり、光化学オキシダントの原因物質として200種を超える物質が確認されている。その排出抑制の必要性が従来から強調されてきた。
中央公害対策審議会は、51年8月13日に、光化学オキシダントの濃度が環境基準に適合するためには、午前6時から9時までの3時間平均値のメタンを除いた炭化水素(非メタン炭化水素)濃度が0.20〜0.31ppmC以下が適当である旨の指針値を示すとともに、光化学オキシダントの原因物質である炭化水素の排出低減が急務であることにかんがみ、炭化水素類の排出抑制のための有効な方策を実施する必要がある旨の答申を行った。
このため環境庁では、51年度、52年度の2か年にわたり固定発生源からの炭化水素類の排出を抑制するため専門家の指導の下に排出抑制技術の検討を行った。
更に、53年度から55年度にかけては、次のような調査検討を行った。
() 発生源別、地域別の炭化水素類排出量の動向及び業界の排出抑制対策の実情を把握するため53年ベースでの排出量の見直しを行った。
なお、主要な固定発生源からの炭化水素類排出量は、第2-3-16表のとおりである。
() 炭化水素類は、通常、複雑な混合物となって排出されており、トータルな非メタン炭化水素として一度に濃度を測定できるよう、サンプリング法、分析法等について専門家の指導の下に検討を行った。
() 多種多様な用途に用いられている炭化水素類の取扱いの実態を把握するため、炭化水素類の排出量の多い東京湾、伊勢湾、大阪湾、瀬戸内、北九州周辺16都府県の取扱業者に対し、業種別の取扱物質、施設の規模と型式、排出防止対策等のアンケート調査とこれの集計、解析を行った。
() 光化学オキシダントが発生する上空における炭化水素類の組成を把握するため、神奈川県の東京湾岸及び内陸部において大気中の炭化水素類の測定とこれの組成分析を行った。
() 炭化水素類の排出抑制対策について、費用効果面からの解析を行った。
() 低公害塗料の開発状況及び転換に際しての問題等について専門家の指導の下に検討を行った。
() 非メタン炭化水素の環境濃度測定データ、地域別、発生源別排出データ等から排出量と環境濃度との相関について専門家の指導の下に検討を行った。
() 炭化水素類発生施設に対する排出防止技術の適用状況及び今後の開発可能性等について専門家の指導の下に検討を行った。
56年度には、これら各種多方面にわたる調査検討結果をとりまとめ、全体的な結論を得るための検討を行った。
今後は、この検討結果を踏まえて、効果的かつ合理的な排出抑制対策を樹立し、推進する必要がある。
イ 自動車からの炭化水素排出防止対策
自動車から排出される炭化水素に対しては、ガソリン又はLPGを燃料とする自動車について、45年にブローバイガス(ピストンとシリンダーのすきまから吹きぬける未然の混合気をいい、炭化水素が主成分)の規制、47年に燃料蒸発ガスの規制が行われ、更に、48年度規制及び50年度規制により排気管から排出される炭化水素の規制が実施された。また、ディーゼル車についても、49年度規制により排気管から排出される炭化水素の規制が行われている。
これらの規制の効果を乗用車1台当たりから排出される炭化水素の量で見ると、第2-3-17図のとおり未規制時に比べて92%の削減となっており、排気管から排出される炭化水素については、48年度規制に比べて93%の削減となっている。
また、軽量・中量ガソリン車、軽貨物車、重量ガソリン車、ディーゼル車について、自動車1台当たりから排出される炭化水素の量は、未規制時に比べてそれぞれ65%、52%、10%の削減となっている。
(5) 酸性雨対策
48年6月下旬、49年7月初旬及び50年6月下旬から7月上旬にかけて、北関東を中心にいわゆる酸性雨によると考えられる眼の刺激や皮膚の痛みを訴える事例が発生した。
酸性雨に関する現在までの知見では、大気中に排出された二酸化硫黄、窒素酸化物が大気中でそれぞれ硫黄イオン、硝酸イオンに変換され、これが雨水の酸性化に大きく関与していると言われており、これらの物質の生成機構及び雨水中への取込み機構並びに眼に対する刺激物質の究明等に関する調査結果の解析を56年にとりまとめた。
これによると、眼や皮膚の刺激は降水中の酸性物質による作用以外に、共存するホルムアルデヒド(HCHO)、ギ酸(HCOOH)、過酸化水素(H2O2)等の物質の相互作用によると考えられ、酸性雨の発生機構については第2-3-18図のように推定された。
また、酸性雨は最近とみに国際的に解決を迫られている問題でもあり、我が国においては今のところ北欧や北米で発生している酸性雨による生態系の被害は報告されていないが、生態系における被害が明白になった時点では手遅れであるため、今後のエネルギー情勢の推移等にもかんがみ、酸性雨の発生機構の解明等所要の調査研究を行い、その結果を踏まえて必要な対策を検討することとしている。