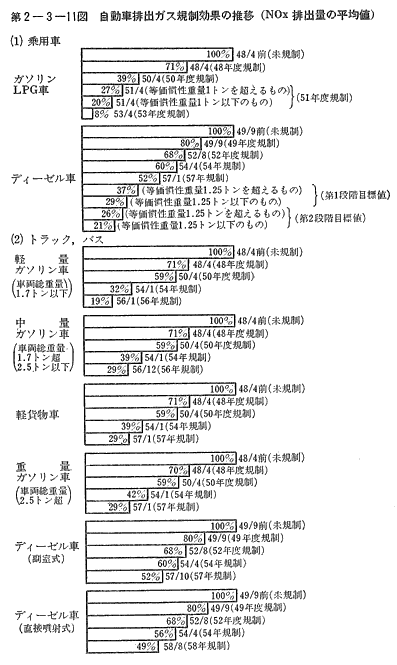
3 ばいじん等対策
大気中の粒子状物質は「降下ばいじん」と「浮遊粉じん」に大別され、更に浮遊粉じんは、環境基準の設定されている粒径10μm以下の浮遊粒子状物質とそれ以外の浮遊粉じんに区別される。これらの粒子状物質の発生源は、工場・事業場等産業活動に係るものだけでなく、自動車の運行に伴い発生するもの、風による土壌粒子の舞い上がりや黄砂等の自然環境も含まれ、多種多様である。これらの各種発生源のうち、工場及び事業場における事業活動に伴って発生するものについては、大気汚染防止法に基づき?燃料その他の物の燃焼又は熱源としての電気の使用に伴い発生する物質を「ばいじん」とし、?物の破砕、選別その他の機械的処理又は堆積に伴い発生し、又は飛散する物質を「粉じん」として規制しており、自動車の運行に伴い発生するものについては、同法等に基づき「粒子状物質(ディーゼル黒煙)」として規制している。
(1) ばいじん対策
ばいじんについては、施設の種類及び規模ごとに排出基準が定められており、更に施設が密集し、汚染の著しい地域においては、新・増設の施設に対し、より厳しい特別排出基準が定められている。
この排出基準は、46年に改定強化されて以来、既に10年余を経過している。
環境庁においては、52年度から3か年にわたり専門家からなる検討会を設置して、集じん技術の現状、ばいじん排出の実態等について検討を行ってきたが、この検討結果等を踏まえ、現在、?石炭利用の拡大等のエネルギー事情の変化、?ばいじん排出防除技術の大幅な進歩、普及、?諸外国の規制水準等を考慮したばいじん排出規制強化のための作業を進めている。
(2) 粉じん対策
粉じんの規制については、46年に堆積場、コンベア等の粉じん発生施設の構造、使用及び管理に関する基準が定められている。
今後、石炭利用拡大等に伴って石炭取扱施設の増加が見込まれるところから、粉じん対策の強化について検討する必要がある。
(3) 浮遊粒子状物質対策
浮遊粒子状物質については、47年1月に環境基準が設定されて以来、その達成率は極めて低い状況にあるため(55年度における長期的評価に基づく環境基準の達成率は全有効測定局の29.2%)、その対策の確立が急務となっており、56年度より4か年の予定で発生源における防除対策、環境への寄与率、対策による環境濃度の改善効果等の検討、調査を実施している。
(4) ディーゼル黒煙対策
自動車から排出されるディーゼル黒煙については、新車に対し47年から、使用過程車に対し50年から、汚染度による規制が実施されている。
また、近年におけるディーゼル車の増加傾向を踏まえ55年度からディーゼル黒煙等のディーゼル排出ガスによる沿道排出実態、生体影響等に関する調査を行っている。