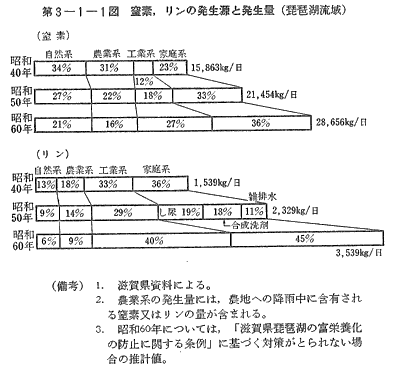
4 閉鎖性水域の汚濁対策
水質汚濁については、環境基準のうち健康項目は全水域の99.95%で達成されており、年々改善が進んでいる。しかし、生活環境項目の達成率は低く、代表的な水質指標であるBOD(又はCOD)についてみると、閉鎖性水域、都市内の中小河川の達成状況が低く、全水域のうち31.3%の水域において環境基準が達成されていない。
特に、湖沼等閉鎖性水域については、水が滞留し、汚濁物質が蓄積しやすいため都市化の進展等によって汚濁が進んでいるところが多く、環境基準(生活環境項目)の達成率が低く、改善がほとんどみられない。
また、生活排水、工業排水等に含まれる大量の窒素、リンなどの栄養塩類の流入により、プランクトンや藻類などの水生生物が増殖繁茂することに伴い、その水質が累進的に悪化するという、いわゆる富栄養化の進行がみられる。このため、湖沼で水道原水の着臭や、透明度の低下などがみられ、また、瀬戸内海、伊勢湾などの内海、内湾で赤潮の発生などによって、漁業被害や海水浴の利用障害、悪臭の発生、海浜の汚染、底層の貧酸素化など広く生活環境への被害が生じている。
このことを琵琶湖について見ると、琵琶湖では、生活排水、工業排水等の要因によって窒素、リンの流入が大幅に増加しており、また、滋賀県の推計によると、有効な対策を講じない場合には今後とも増加するとされている(第3-1-1図)。
このため、同県は「滋賀県琵琶湖の富栄養化の防止に関する条例」を制定し、これに基づき、? 工場・事業場に対する窒素、リンの排出水の濃度規制、? リンを含む家庭用合成洗剤の販売・使用禁止、? 家庭雑排水や農業排水等に対する指導の実施を55年7月から行っている。また、「新琵琶湖環境保全対策(びわ湖ABC作戦)」では、上記対策に加え、下水道の整備とともに窒素、リン除去のための高度処理の実施、土地利用対策等を推進することとしている。茨城県においても霞が浦の富栄養化が進んでいることから条例を制定し、現在施行に向けて準備を進めている。
また、56年7月には、琵琶湖に関係する地方公共団体の長、学識経験者等の参加を得て、琵琶湖環境保全懇談会(琵琶湖サミット)、同年9月には、全国の関係都府県の知事の参加を得て、湖沼環境保全知事懇談会(全国湖沼サミット)が開催され、湖沼の現状が示されるとともに、水質浄化に向けて今後の対策が検討された。
湖沼の水質汚濁が全国的なものとなっている中で、環境庁としては、湖沼環境保全のための各種対策を総合的、計画的に推進することとしている。
更に、環境庁としては富栄養化対策として、水域における窒素、リンの環境基準の設定について、中央公害対策審議会に諮問する方向で準備を進めているところである。