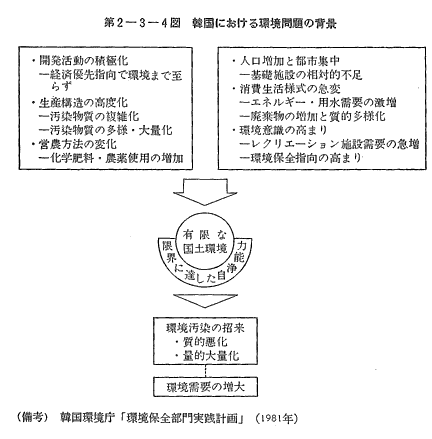
2 広がる環境汚染
(1) 公害の拡大
既にみたように、開発途上国は、1960年代から70年代にかけて高い経済成長を達成した。特に、韓国等の中所得国において経済成長は顕著であり、その過程でこれらの諸国も工業国と同じように公害現象を経験するようになってきている。韓国を例にとり、開発途上国における公害の拡大をみてみよう。
韓国の1970年代の経済成長率は約10%とみられている。しかし、このような経済成長と歩調を合わせて、環境汚染が問題化してきた。韓国の第5次経済社会発展5か年計画の一環として1981年末に策定された環境保全部門実践計画は、環境問題の顕在化の背景を第2-3-4図のように説明している。有限な国土の中で経済活動が高まり、汚染物質の排出が増加し、その量、質が環境の自浄能力を超えた結果、環境汚染が発生したことを示しているが、これは多くの工業国が経験したものと同様である。
第2-3-5図及び第2-3-6図はそれぞれ主要都市における大気汚染(二酸化硫黄(いおう))と水質汚濁(COD)の推移と汚染防止目標をみたものである。二酸化硫黄(いおう)については、年々、汚染濃度が高まっており、0.05ppmという環境基準を超えている都市もある。水質汚濁(COD)も急速に進行しており、3ppmという環境基準を超えている水域もみられる。そのほかにも、廃棄物の急増等が懸念されている。そのため、同計画では持続的成長基盤の形成とともに、経済社会の均衡ある発展を行うことにより環境保全を図ることが、その基本目標とされている。
このような環境汚染の進行は韓国に限らずフィリピン、タイなど経済成長が高く都市化の進展が著しい中所得国に共通しており、今後中所得国においても工業国と同じように、公害が社会問題化することも考えられる。
(2) 地球的規模の環境問題
開発途上国を中心に増大する世界的な人口圧力の下で、食糧、エネルギーなどの資源不足が今まで以上に大きな問題となるであろう。それと同時にこうした問題の解決とからみ合いながら環境問題が拡大することが予想される。すなわち、森林の減少、砂漠の拡大、土壌の流失、動植物の種の絶滅などの生態系の変化、海洋・内陸水の汚濁や化学物質による汚染など種々の問題の進行が懸念される。このような広範囲にわたる環境問題は人間生活のいろいろな側面に重要な影響を及ぼし、全体として人間の環境の質を低下させるだけでなく、ある限度を超えると、人類の生存の基盤が危うくなる可能性もあるともいわれている。
そのため、1972年の国連人間環境会議の決議に基づき国連機関として設置されたUNEP(国連環境計画)を中心に、その実態の把握、情報の交換等の国際協力が進められているが、ここではUNEPアジア・太平洋地域事務所(バンコック)が発表した1980年報告書等により、アジア・太平洋地域の環境問題をみてみよう。
ア 土地・土壌
土壌流失は森林の伐採や過度の放牧などにより、地表を覆っていた植物層が失われ、地表が露出した場合に、雨や風の影響を受けて発生する。このことは浸食作用を受けやすい山地において著しく、保水力の低下や下流域での洪水の要因になるとともに、世界の5分の1から3分の1に及ぶ地域での農地の生産性低下の原因になっているとみられている。
ネパールでは、毎年2億4,000万立方メートルの土壌がインド、バングラデシュに流出していると推計されており、ネパールの農業生産性の低下とともに、インド、バングラデシュの洪水などの原因となっている。この土壌流失は、森林伐採、特に燃料用の木材伐採によるものであり、国土の3分の2を占めていた森林は、この30年間に3分の1に縮小している。
土地・土壌に関連する問題としては、このほかにも土壌中の塩分の増加、重金属の蓄積などとともに地盤沈下があげられる。前述したように、開発途上国における絶対的貧困人口は膨大な数にのぼっているが、その大半は農村人口であり、土地のない貧しい農民は雇用機会を求めて都市に移動する。このため、開発途上国の都市人口の増加は著しいが、一方、都市の水供給は社会資本の未整備や水質汚濁等により容易ではないため、地下水の揚水に依存している都市も多い。しかし、過度の揚水が地盤沈下を引起こしている例もみられる。タイのバンコック圏では1日に約1,000万立方メートルの揚水が行われているため、年平均5センチから10センチの地盤沈下が広範な地域において進行している。
イ 森林
森林伐採は焼畑農業によることが多く、しかも人口増加の圧力の下で休閑期間が短くなり、森林の破壊がもたらされるとされている。
アジアでは、毎年約500万ヘクタールの森林が減少している。これは、およそ我が国の中国地方と四国地方を合わせた面積あるいは我が国の総森林面積の5分の1に匹敵する。更に現在、約100万ヘクタールが不適切な使用により荒廃しつつあるといわれている。
森林の減少をフィリピンについてみてみる。フィリピン政府による第1回環境白書(1977年)によると、丸太を含む林産品はフィリピンの主要輸出品の一つであることに加え、食糧増産の必要性もあって平地ばかりでなく、河川上流地域の傾斜地まで山林伐採が行われている。山林伐採は年に8万4,000ヘクタールにのぼっているが、植林は5万ヘクタールにとどまっており、年々約3万4,000ヘクタールの森林面積が減少していることになる。また、森林が伐採され裸地の状態にある面積は500万ヘクタールにのぼり、そのうち390万ヘクタールは山地であると推計されている。更に水質の悪化により、取水が困難になる等の影響も出ている。
土壌流失についてみれば、その危険のある地域は890万ヘクタールにのぼっているが、これは国土面積の約30%に当たる。土砂の流出が原因となって、河川では土砂の沈泥が進み、河床が上昇する。第2-3-7表は、土砂の沈泥率を国際比較したものであるが、沈泥率の高いのは、フィリピンの2河川であり、これはフィリピンの山地での森林伐採が急峻な地形とあいまって、土壌流失の大きな要因となっていることを示している。
森林の減少の影響としては、そのほかにも野生動物の減少あるいは種の絶滅をあげることができる。森林の伐採により、いわゆる生態系の均衡が崩れ、野生動物の餌や生息地が減少するため、その数は減少し、更には絶滅の危機にひんしている種もみられる。このような例としてはサルクイワシやコノハズクなどがあげられている。
フィリピンは、このような森林の減少とそれに伴う土砂流失等に対し、伐採量の削減とともに、森林生態系経営計画という造林計画を実施している。同計画は、林産資源の再生産とともに、水資源の確保、自然環境の保全を目的としており、これに対し我が国も技術協力を行っている。
ウ 広域汚染
我が国においては、現在数万点に及び化学物質が生産や生活のために広く使用されている。同時に化学物質の中には毒性を有するものもあり、このため、生産、流通の場での危険防止等の措置がとられてきている。
しかし、化学物質は、その生産、使用、廃棄の過程を通じて環境中に広く拡散することは避けられない。このため我が国では、環境汚染の未然防止という観点から、化学物質について事前に安全審査を行い、それをもとに生産、使用、輸入等について厳しい措置を講じている。例えばPCB、DDT等は、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」に基づき原則として生産、使用、輸入等が禁止されている。また、DDTなどは、農薬としても販売禁止などの規制が行われている。また、日本以外の工業国においても、ほぼ同様の規制が進み、その結果、これら諸国からの環境中へのPCB、DDTの拡散は減少しているが、それ以前に環境中に拡散した化学物質の回収はほとんど不可能となっている。
一方、世界的にはDDTの使用が続いており、また、UNEPアジア・太平洋地域事務所の報告書が示すように、当該地域におけるDDT等の殺虫剤の使用が高い率で増加しているため、環境中に残留しているものと合わせると、これらによる広域的な大気や海水中の汚染の拡大が懸念される。
第2-3-8図及び第2-3-9図は、日本から南極にかけての海域におけるDDT、PCBの濃度を示したものである。いずれも、日本から南極にかけて一様に検出されているが、特に赤道の近辺で濃度が高くなっている。DDTについてみれば、かつて工業国から拡散され、海洋中に残留しているものに加え、近年開発途上国において、農業やマラリア撲滅のため、高い伸び率でDDTが使用されており、それらが合わさって第2-3-8図に示されるような状況になっているといえよう。
同時に、既に世界的に禁止又は生産が縮小しているPCBが南極においても中、低緯度地方とあまり濃度に差がなく検出されているが、このことはDDTの例とともに、化学物質が拡散を通じ、地球的規模での汚染の原因となっていることを示している。