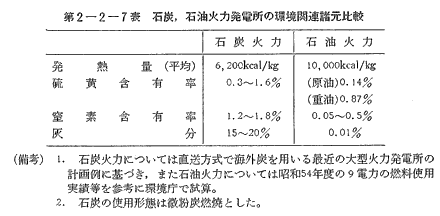
2 石油代替エネルギーの開発・導入
石油については価格が2度にわたり大幅に引上げられたことに加え、中長期的にみて、石油の供給が不安定であることから、石油消費国である主要先進国は省石油とともに、石油に代替するエネルギーの開発・導入に大きな努力を払っている。我が国でも「石油代替エネルギーの開発及び導入に関する法律」等に基づきさまざまな施策が進められている。
中でも石炭については、?石油に比較して世界の各地に広く埋蔵されていること、?また、全体の確認可採埋蔵量が250年程度と格段に大きく、比較的安定した供給が可能であること、?相次ぐ石油の大幅値上げで燃焼後の灰捨て等の費用を含めても価格が石油価格に比べて有利になったことにより、その利用が急速に拡大してきている。
しかし、石炭等の石油代替エネルギーの導入に当たって、適切な環境保全対策を講じない場合には、環境への負荷の増大をもたらすことも考えられる。石炭については燃焼に伴う、窒素酸化物、硫黄(いおう)酸化物、ばいじん等の発生量は一般的に石油に比較して相当量多いこと、石炭の輸送・貯蔵に伴い粉じん飛散が生じやすいこと、石炭利用の結果発生する灰が石油に比べ格段に多いこと等から、今後の開発・導入に当たって環境保全に十分な配慮が必要である。
窒素酸化物についてみると、石炭の窒素含有量は石油に比しおおむね高い。また、石炭は灰分を多く含むため、燃焼安定性が劣り、このため燃焼に伴う窒素酸化物の発生、すなわち燃焼性窒素酸化物の発生量が多くなる。両者を合わせ発熱量当たりに換算して、窒素酸化物の発生量を比較すると石炭は石油の3倍程度になると考えられる。
第2-2-7表及び第2-2-8表は火力発電所について対策前後の排出ガス量等を試算し比較したものであり、石炭燃焼に伴う窒素酸化物の発生量が大きいことが示されている。
なお、窒素酸化物及びばいじんに関する排出基準については石炭を利用する施設は石油を利用する施設に比べ緩くなっている(窒素酸化物は約3倍、ばいじんは4〜8倍)。
ばいじんは、石炭燃焼に伴いかなり高濃度で発生し、現在用いられている集じん装置によっては、石油燃焼施設程度にまでは減らすことができない場合がある。また、湿式脱硫装置からの排水は酸性であり、浮遊物質量、フッ素等の濃度が高く、また、同規模同種類の石油施設に比して排水量も多い。このため湿式脱硫装置の設置に当たっては、汚濁防止のためには、中和、凝集沈澱装置等の機能を備えた排水処理装置が必要であり、石炭火力発電所をはじめとして用いられている。
燃焼の際に発生する灰の処分も重要な課題である。産炭地によって若干の差異はあるが、石炭中には平均して2割程度の灰分が含まれており、これが燃焼後も石炭灰として残る。多くの施設で灰の処分場を手当しているが、今後とも石炭灰の有効利用を更に促進するとともに、大規模な埋立てを行うことに対しては、環境保全に十分配慮していく必要がある。
現在、石炭灰の埋立て処分量の削減にも役立つ石炭灰の有効利用の技術開発の努力が進められている。セメント混和剤等のほか、コンクリート骨材、肥料(珪(けい)酸カリ肥料)、路盤材等への有効利用が技術的には可能となっている。
石炭中には重金属等が含有されているが、大気中に排出される量はわずかであると考えられ現在の知見の範囲では、直ちに健康影響が生じるとは考えにくい。しかし今後はこれらの物質の環境中への排出量及びその影響について、環境中での挙動を含めた総合的な調査検討が必要であろう。