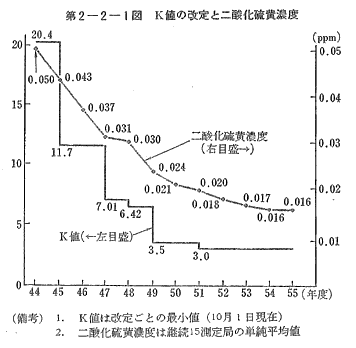
1 公害防止対策の進展と産業構造の変化
(1) 公害防止対策の進展
公害を防止するため、人の健康を保護し、生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準として環境基準が定められているほか、大気の汚染、水質の汚濁の原因となる物質等の排出を規制し、土地利用を規制するとともに下水道等の社会資本の整備等を進めている。排出規制については個別施設の規制だけではなく、一定地域内の汚染物質の排出総量に着目し工場等ごとに排出量の許容限度を設けて規制するという総量規制も導入されてきている。
例えば硫黄(いおう)酸化物についてはこの10年間に排出量は東京、大阪などの地域では7分の1程度に規制されている(第2-2-1図)。
社会資本の整備も積極的に進められた。例えば、55年度までの10年間に政府固定資本形成に占める下水道投資の割合は約2.5倍に増加しており、下水道普及率も16%から30%へと上昇してきた。
公害は地域性の強い問題であることから国の施策とともに地方公共団体の果たす役割が大きい。環境基準に係る水域及び地域の指定が原則として都道府県知事に委任されているほか、すべての都道府県においていわゆる公害防止条例が制定され、地域の特性に応じ国の基準より厳しい排出基準(いわゆる上乗せ基準)等が設定されている。また、法律に基づき勧告、命令の権限が都道府県知事に与えられており、加えて各種規制措置に関する企業の遵守状況をみるための監視測定等も行われている。
更にこれら公害防止施策を補充強化し、未然防止の観点をも含む地方公共団体等と企業との間の公害防止協定の役割が40年代前半に注目され、それ以来協定は急速に増加している。45年度には496事業所であったのが56年度には19,670事業所に達している。
国、地方公共団体の施策の進展に対応して事業者は燃料転換、公害防止装置の設置等、公害防止対策を進めた。これを大企業における公害防止投資についてみると、45年度には2,800億円(50年価格)であったが、その後の規制の基準の設定強化、規制対象の拡大に対処するため急速に増加し、50年度には9,600億円に達した。51年度以降既設生産設備に対する公害防止施設の設置がほぼ一巡したとみられることなどにより減少したが、最近では再び増加に転じている(第2-2-2図)。
中小企業における公害防止投資の動向についても大企業と同様の傾向にあり、48年度をピークに減少したものの、54年以降緩やかに増加している(第2-2-3図)。
(2) 産業構造の変化と環境への影響
48年及び54年の石油価格の大幅な引上げは、全エネルギーの4分の3を輸入石油に依存していた我が国に大きな影響をもたらした。特に原材料・エネルギーコスト比率の高い基礎資材型産業では、コストの大幅な上昇、内需の伸び悩み、国際競争力の低下などにより、生産、出荷の伸びが鈍化した反面、電子製品、精密機械に代表されるような加工組立型産業は、技術革新の進展等に加え輸出の大幅な伸長もあって生産、出荷を着実に拡大し、製造業におけるシェアを高めている(第2-2-4図)。
第2-2-5図及び第2-2-6図は製造業について50年を基準に55年における硫黄(いおう)酸化物及びCODの発生量について試算し、要因の分析を行ったものである。硫黄(いおう)酸化物、CODのいずれについても製造業のシェアの変化でみた産業構造の変化は減少要因になっている。これは、基礎資材型産業の伸びが低い一方、加工組立型産業の伸びが高かったことによるものと考えられる。すなわち、一般に基礎資材型産業は、エネルギー、製品処理用水等の単位使用量が多く、環境への負荷が相対的に大きいのに対し、加工組立型産業は、環境への負荷が相対的に小さいとされている。このことから、生産の伸びのうち、加工組立型産業の寄与が大きかったことは、全体として負荷量の増加を抑える効果をもたらしたといえよう。
(3) 省資源・省エネルギーの進展
近年、省資源・省エネルギーが進められており、環境負荷の減少に大きく寄与している。第2-2-5図及び第2-2-6図にみられるように硫黄(いおう)酸化物についても、CODについても減少要因となっている。このように資源・エネルギーの節約が進んだのは資源・エネルギー価格の高騰に対し、政府・民間一体となって省資源・省エネルギーに取組んだことによる。特に企業がより一層経費節減を進める手段の一つとして多くの工程にわたって省資源・省エネルギーのための合理化努力をしたことがあげられる。
このうちエネルギー、原材料等の使用量の大きい基礎資材型産業については、企業経営上その効果が大きいことから、大規模に省資源・省エネルギーが進められている。石油化学については廃熱回収などによりエチレンプラントで48年から55年の間に19%、鉄鋼については連続鋳造等の工程の連続化、炉頂圧発電等の排エネルギー回収などにより同12%、セメントについてはNSPキルンの採用等によって同21%、非鉄金属のうちアルミニウムについては、電解原単位の向上等で同10%程度の省エネルギーが実現している。また自動車の燃費についても50年度に対し、53年度は2割程度の改善を示している。
一方、省資源の観点から、廃棄物の有効利用を図る努力もされている。特に産業廃棄物については、同質のものが多量に排出されるため再資源化が採算のとれることが多く、最終処分場の確保が困難なこと等もあってかなり進展している。通商産業省の調査によると、54年度に鉱工業から排出された2億695万トンのうち、54.6%が再資源化されたと推計されている。そのうち金属くずについては98.7%とほぼすべてが再資源化されたほか、鉱さい81.4%、ダスト類75.1%と廃棄物の種類によっては、かなりの部分が有効利用されている。一般廃棄物については、焼却処理施設における余熱利用により省エネルギーが図られている。また、種々雑多なものが含まれていること等により、一般廃棄物の再資源化率は低いものの資源化のための分別収集の導入及び分別、再資源化技術の開発等が推進されている。
また、水についてみると、生活用水の使用量は、人口の増加や都市化の進展に伴い増加しているものの、工業用水量の補給水量は工業用水の使用量が増加を続けているにもかかわらず、ほぼ横ばいとなっている。これは工業用水の再生利用や循環利用が進められてきたことによるもので、回収率は、45年の51.7%から、50年67.0%、55年73.6%と着実に上昇している。
以上みてきたように企業の公害対策は環境政策の整備とともに急速に進み、また石油価格の上昇への対応がその効果を大きくした。
すなわち前述のような産業構造の変化、省資源・省エネルギーの進展は、結果的に汚染物質の排出を減らす効果があり、環境負荷は単位生産量当たりでは、低下してきているといえよう。しかし、経済活動の拡大は一般的には環境負荷の増加要因として働くため、以下にみるような新たな環境問題への対応を含め今後とも引続き環境保全対策の充実が必要である。