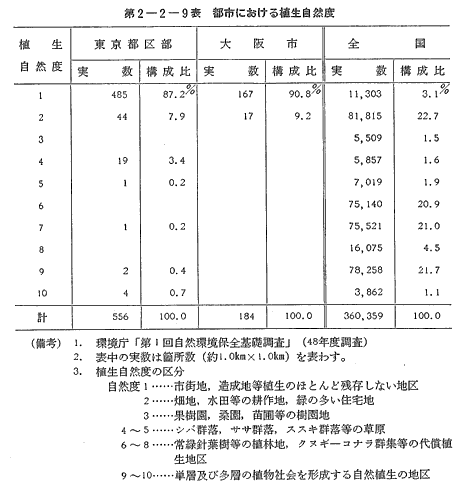
3 都市化の進展と消費の拡大
(1) 都市化の進展
高度経済成長は工業化を軸に地域的には三大都市圏を中心に進展した。このため就職、就学等の機会を求めて大都市へ人口が集中した。昭和40年代後半になると、地方における雇用機会の増加、大都市における社会的条件の悪化に伴う地方志向の強まりなどにより、地方圏における都市化が進展することとなった。一方、大都市圏への人口集中は鈍化し、50年代前半に入ると東京、大阪、名古屋の三大都市圏における社会増のテンポは急速に弱まってきた。東京都区部、大阪市などでは人口が1平方キロメートル当たり1万人を超すなど依然として非常に高い人口密度となっているが、その中で都心から周辺部へ人口が移動している。
我が国の都市においては産業の立地、人口の集中により、土地利用が非常に高密度化しており、樹林地、農地が次々と市街地に組込まれる過程で減少を続けた。第2-2-9表は植生自然度をみたものであるが、東京都区部、大阪市の植生は全国に比べ極端に貧困であり、大阪では早くから市街地化が進んだこともあって、9割が植生のほとんど残存しない地区となっている。また、残りの1割についても畑地、水田、住宅地内の緑であり、果樹園等の樹園地さえ皆無に等しくなっている。
居住環境について総理府の住宅統計調査によってみると、木造共同住宅数の住宅総数に対する比率は、東京都区部で35.2%、川崎38.7%、札幌34.0%、大阪23.1%と大都市では全国の11.6%に比べ高くなっている。また、一戸建、長屋建住宅について、建ぺい率をみると、80%以上とする住宅の数が全国の9.1%に対し大阪42.6%、神戸24.2%、京都20.2%と関西の大都市が特に高くなっており、北九州16.1%、東京都区部15.5%となっている。また、一戸当たりの住宅面積も、東京都区部、大阪などでは全国平均を3割ほど下回っている。このように都市においては緑地空間が乏しい上、木造共同住宅が普及しているが、それらのなかには必ずしもしゃ音性が十分でないものも多いと考えられる。また、一戸建、長屋建住宅についても高密度になっていると考えられる。
(2) 消費の拡大
次に消費についてみよう。戦後の高度経済成長は所得の増大と消費の豊かさをもたらした。特に耐久消費財については、家事の省力化、生活の快適性などのニーズに応えた家庭電化製品の普及に著しいものがあるほか、移動の自由度を飛躍的に高める乗用車保有の増加も著しい(第2-2-10表)。また、流通の効率化や大量化を可能にしたプラスチック、びん、カンなどが広く利用されるようになった。カン入り飲料についてみると、54年には約92億カンと10年前と比べ10倍を超す増加を示している。
以上のような都市の高密度化、消費の拡大がもたらす問題の一例をみてみよう。廃棄物の量的増加、質的変化は処理の困難化、都市域における埋立て処分場用地の不足等種々の問題を生じている。また近年、不用になった空きカンが観光地、道路周辺に投捨てられ散乱していることから大きな問題になっている。環境庁の調査によると、ボランティアの人達が拾い集めた空きカンの数だけでも55年1年間で約4億4,000万個にのぼっている。
都市化の進展に伴う問題の一つとして近隣騒音があげられよう。近年、生活の中で発生する物音や話し声などの騒音が生活環境を悪化させている。特に緑地空間が少なく住宅が密集していることに加え、テレビ、ステレオなどが普及していることなどを背景に都市を中心に問題となってきている。
環境庁が55年秋に東京都で行った調査によると回答者のうち6割が近隣で発生する物音、話し声などを騒音として感じている。内訳についてみると第2-2-11図に示されるように「チリ紙交換などのスピーカー」、「自動車の空吹かし、ドアの開閉」に次いで、「風呂などの給排水」、「室内・階段の足音」、「隣人の話し声」など日常生活に伴うものが多くなっている。その原因(複数回答)については、「心がけが欠けているから」65%、「住宅事情が悪いから」49%などとなっており、都市生活におけるモラルの欠如とともに、前述したような都市化の進展のなかで、しゃ音性が十分でないと考えられる住宅が多いことや住宅が比較的高密度になっていることがその要因となっていることを示している。
(3) 交通公害
我が国の都市化の進展に寄与したものの1つとしては交通手段の発達があげられる。中でも、乗用車は国民の所得向上と強いニーズに支えられ、高い機動性をもつ貨物車は、経済発展に伴い急速に利用が拡大した(第2-2-12図、第2-2-13図)。このような自動車の急速な普及と都市間及び都市内を中心とする道路の整備に伴い自動車輸送が大幅にのびることとなった。しかし、都市内においては既に道路沿いに住宅を含む高密度な土地利用が行われている上、交通量、通行車種、走行条件、道路構造等の各種の要因が複雑にからみあって、自動車交通に起因する騒音、振動等の公害が生じている。このうち騒音については都市における幹線道路周辺の住居地域では、夜間においても、2車線を起える道路に面する住居地域の環境基準である50ホンを超えることが多く、場所によって70ホンを超えるなど環境基準の達成率が低い。
このほか鉄道、航空機の運行に伴う騒音等についても引続き対策が求められている。
(4) 水質の汚濁
大都市においては、人口の社会増の頭打ちと同時に、人口の増加の中心が周辺部へと移動し、都市域を拡大する一方、都心では人口が減少するといういわゆるドーナツ化現象が進行している(第2-2-14図)。
他方、一般に都市部から離れるほど地域の下水道普及率は低くなっている。例えば東京都の場合都心部の下水道普及率が96%であるのに対し、40〜50キロメートル圏については24%とかなり低くなっている(第2-2-15表)。また、宅地開発に当たって区画整理等により計画的な市街地の整備が進められた地区においては、下水道等の整備が進んでいる反面、下水道等が整備されないままスプロール的に宅地開発された地域も多い。このような地域においては、人口増加に伴い、大量の雑排水などの汚水がほとんど処理されないまま河川等に流込み、水質汚濁の大きな要因となっている。
大都市周辺にある水域のうち、流域の都市化が進み、大量の汚水が流入する河川では汚濁がかなり進んでいる。更に、このような汚濁が進んだ河川の水が流込む湖沼や内湾などの閉鎖性水域については、水が滞留しやすいこともあって深刻な状態になっている。
大都市周辺の水域で、都市化の進展により汚濁の進んだ例として千葉県手賀沼をみてみる。手賀沼は東京の北東にあり、都心から約30キロメートルに位置し、東京の通勤圏内にあることから、周辺の宅地化が進んでいる。これを人口でみると、40年から55年までの間に柏市、沼南町で約2倍、我孫子市、鎌が谷市で約3倍と急速に増加している。しかし、流域の公共下水道の普及率は56年3月現在、柏市17%、我孫子市21%と低く、公共下水道が設置されていない市町もある。現在、手賀沼流域下水道の整備が進められているが、一部が供用を開始しているにすぎず、依然として大量の汚水が河川に流込んでいる。工場排水に加え、家庭からの排水が大量に流込む大津川、大堀川では、55年度のBODがそれぞれ16ppm、17ppmと環境基準を大きく上回っており、悪臭の発生限界といわれる10ppmをも超えている。
このように大津川、大堀川等汚濁の進んだ河川の水が流入することに加え、栄養塩類の流入による沼の富栄養化の進行により、手賀沼ではCOD(年平均値)が55年度において23ppmと非常に高い水準となっているほか、アオコの発生、悪臭などが問題となっている。