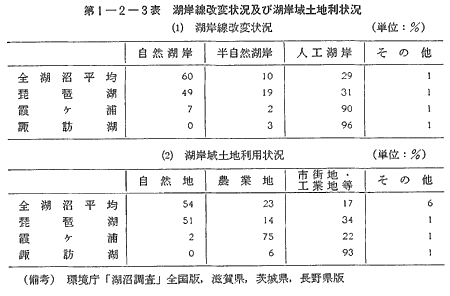
3 水辺環境の状況
我が国は四面を海で囲まれているほか、地形が複雑で、かつ、年間降水量が多いこともあり、湖沼、河川、海岸など水辺環境に恵まれている。しかし、それらの水辺環境も次第に改変されてきている。湖沼、河川、海岸に関する調査結果により水辺環境の現状をみることとする。
(1) 湖沼
面積1ヘクタール以上の天然湖沼(全国で487)を対象に実施した湖沼調査によると、その面積及び湖岸線延長の合計はそれぞれ約2,400平方キロメートル及び約3000キロメートルである。湖岸線の総延長は、北海道の海岸線延長とほぼ等しく、湖沼は内陸部の水辺環境として重要な役割を果たしているものといえよう。
我が国の湖沼については、近年富栄養化等による水質の悪化、天然湖沼の自然性の消失等が問題とされているが、湖沼の自然性の消失の一例として湖岸の改変状況をみてみよう。水際線及び水際線に接する陸域の状況により、湖岸を自然・半自然・人工に区分してみた場合、水際線がコンクリート護岸等の人工構築物でできている人工湖岸の比率は湖沼全体で29%、水際線は自然状態であるが、水際線より20メートル以内の区域に人工構築物が存在する湖岸である半自然湖岸は10%であり、自然湖岸は60%である。
次に、湖岸域(水際線より陸側100メートル以内の区域)の土地利用状況を「自然地」、「農業地」、「市街地・工業地等」に区分してみると、湖沼全体では23%が農業地、17%が市街地・工業地等として利用されている。
これらの湖沼のうち最近水質汚濁が大きな問題となっている琵琶湖、霞ヶ浦、諏訪湖について、湖岸域の改変状況や土地利用状況をみると、まず、湖岸の改変状況については、琵琶湖では、人工湖岸が31%、半自然湖岸が19%となっており、霞ヶ浦、諏訪湖では、人工湖岸率は、それぞれ90%、96%となっている。また土地利用状況についてみると琵琶湖岸域は農業地としての利用は14%と低いが、市街地・工業地等としての利用は34%と、湖沼全体の平均に比べ高くなっている。霞ヶ浦では、農業地としての利用が75%と極めて高いほか、市街地・工業地等としても22%が利用されている。諏訪湖岸域では市街地・工業地等は93%、農業地は6%となっており、極めて高度に利用されている(第1-2-3表)。
(2) 河川
我が国の河川は、融雪や梅雨期、台風期の豪雨により、たびたび氾濫(はんらん)し、流域の住民等に対して多大な被害を引起こしてきた。明治中期以降これに対してとられてきた治水策は、遊水池、ダムによる洪水調節と河道改修を組み合わせて洪水処理を行うものであり、その一環として大規模な河川改修が各地で行われてきた。
この結果、河川環境は変貌(ぼう)し、周辺の風致景観や河川の生物相に大きな影響を与えてきた。
今回の河川調査では、112の一級河川及び沖縄県の浦内川を対象に、魚類等の生息場所としての機能に重点を置き、河川の改変状況を調査している。
まず、河川の水際線が護岸等によって人工化されている割合をみると、調査河川区間の総延長11,414キロメートルのうち19%(2,166キロメートル)となっている。一般に北海道の河川の人工化の程度は低く、瀬戸内海や九州西岸の内湾に注ぐ河川の人工化の程度は高い(第1-2-4表)。
河川に生息する魚類のうちには、サケのように海水と淡水の双方を規則的に利用するものがあり、それらにとって移動を妨げる河川横断工作物(橋は除く)の存在は、重要な影響を及ぼす。河川における工作物の設置状況により魚類の遡(そ)上の可能性をみるため、北日本においては主としてサケ、サクラマスについて、南日本においては主としてアユについて、調査を行った。それによると、113の調査対象河川において魚の遡(そ)上に影響を及ぼす河川工作物は全部で1,371あり、魚道が設けられていないこと等により、魚の遡(そ)上が阻害されている河川は、133河川のうち103河川となっている。
これを地域別にみると北海道では河川工作物が少なく、魚の遡(そ)上に支障がないと思われる河川が13河川のうち5河川であるが、本州の日本海側では全流路にわたって遡(そ)上可能な河川は存在しない。本州の太平洋側に注ぐ河川のうち、6河川は遡(そ)上が不可能であるが、3河川には遡(そ)上を不可能するような河川工作物は全く存在しない。
また、瀬戸内海に注ぐ河川は魚の遡(そ)上に関しては条件が悪く、18河川のうち全流路にわたって遡(そ)上可能であるものはわずか1河川であり、遡(そ)上不可能な工作物が多数あるものは6河川となっている。
(3) 海岸
我が国は、四面を海に囲まれた島国であるとともに海岸地形も複雑であり、国土面積に比べ海岸総延長距離は、非常に大きい。一方、我が国は山がちであるため、各種産業等の活動は海岸及びその周辺に集中する傾向にある。したがって、海岸環境の現状及びその推移について把握し、適切な保全対策を検討していくことが今後の環境政策の展開において非常に重要である。
53年度、54年度にわたって実施された海岸調査によると、北海道、本州、四国及び九州については、人工海岸は海岸総延長の34%、半自然海岸は16%、自然海岸は49%等となっている。海岸の人工化は、人口、産業の集中した大都市圏を後背地に持つ海岸で著しい。例えば、東京湾では三浦半島の剣崎から房総半島の州崎に至る海岸のうち86%が人工海岸であり、自然海岸は、わずか11%にすぎない。東京湾や瀬戸内海など海岸の人工化が著しい海域について、現在人工海岸である場所が明治・大正時代どのような状況であったかをみると、当時海であったところが59%と圧倒的に多い。すなわち約6割が海の埋立てで、人工海岸になったことになる(第1-2-5図)。特に東京湾、伊勢湾、響灘など、大都市を背後にもつ海域ではその比率は、高くなっており7割を超える。
更に、当時、海であったところについてその海に隣接している海岸の状態をみると、54%が自然海岸、37%が半自然海岸、人工海岸が9%であった。自然海岸から人工海岸へ改変されたもの48%のうち、埋立てによるものが32%で、自然海岸をそのまま人工海岸化したもの16%の2倍になっており、全体に占める比率もほぼ3分の1と大きい。一方、明治・大正時代から人工海岸であったところは、平均では13%となっているが、東京湾では22%、三河湾では27%と大きい。
次にこれらの海岸の陸域、すなわち海岸陸域(通常大波の限界線より陸側100メートルの区域と定義)をみると、これらの海岸陸域の中で自然地の占める割合は明治・大正当時でも39%であり、現在の瀬戸内海区全体の平均である41%を下回っている。このことは、この陸域が早くから人間活動によって利用されていたことを示すものである。現在これらの海岸陸域の自然地は10%にすぎず、農業地が16%、市街地・工業地等が74%を占めるに至っている。明治・大正当時に比べ自然地は、およそ4分の1に、農業地は2分の1以下に減少し、一方、市街地・工業地等は3.4倍に拡大している。
特に、東京湾、伊勢湾、響灘では、現在の人工海岸のうち陸域が市街地・工業地等となっているところが、80%以上を占めており、その地域はこれら海域全体における市街地・工業地等の合計の90%以上を占めている。すなわち、現在人工海岸となっているところを中心に、海岸陸域の開発が進められてきたことが明らかである。