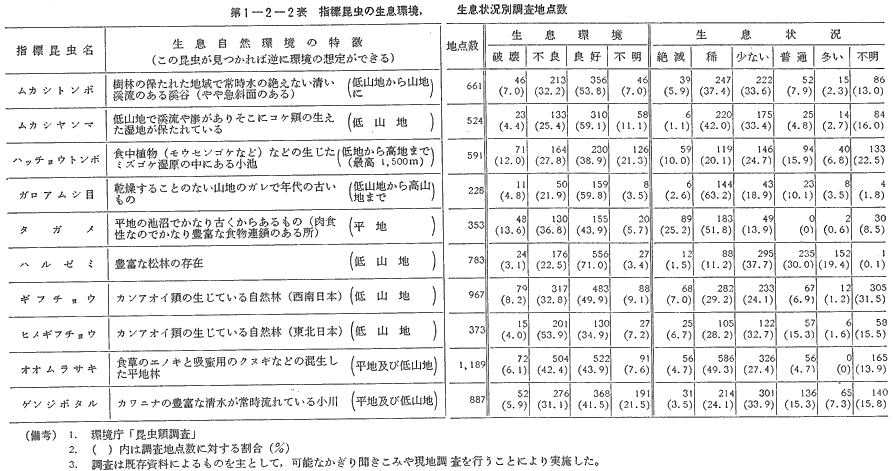
2 野生動物の状況
野生動物の生息は、人間の生活と深い関係を有するものであり、野生動物はその生息条件が備わった環境の指標としてとらえることができる。ここでは哺乳類分布調査等により、我が国の野生動物の現状をみることとする。
(1) 哺(ほ)乳動物
今回の哺(ほ)乳類分布調査により、我が国に生息する大・中型哺(ほ)乳類8種(ニホンザル、シカ、ツキノワグマ、ヒグマ、イノシシ、キツネ、タヌキ、アナグマ)の全国的な分布状況が初めて明らかとなった。
これら8種の分布と人間の活動域との関係をみると、
? キツネ、タヌキ、アナグマは人里近くまで広く分布し、人間との共存も可能と思われる。
? ニホンザル、シカ、ツキノワグマ、ヒグマは森林に依存し山地に分布している。
? イノシシは、分布の中心は山地の森林であるものの、水田や畑を含む低地まで広く分布しており、前記両者の中間的存在と考えられる。
その中でニホンザル、シカ、ツキノワグマの3種については、他の種に比べ分布域が狭く、縮小しつつある。またこれら3種が重複して生息する分布域は一層限られている。すなわち、重複して生息する分布域の区画数は、全体で238でこれは本来ニホンザルが生息しない北海道を除く区画数12,367のわずか1.9%にすぎない。地理的には関東、中部、近畿にかたよっており、具体的には秩父山地、赤石山脈、飛騨山脈、紀伊山地などの山岳地帯で2〜4都府県の境界付近にある、人が接近しにくい自然性の高い地域である(参考資料5)。
なお、この重複分布域は、ほぼイノシシ、タヌキ、キツネ。アナグマも生息することが可能な地域であり、また、カモシカ分布調査によると重複分布域のほとんど全域にカモシカが分布している。
したがって、前記重複分布域は我が国の大・中型哺乳類にとって人間活動の影響をあまり受けることなく、生息を維持していける地域として特に貴重な地域であり、その保全を図っていくことが重要である。
(2) 昆虫類
我が国に生息する昆虫類は、約10万種にのぼるものと考えられている。昆虫類調査は、一定の条件を備えた自然環境にすむムカシトンボ、ゲンジボタル等10種の昆虫類を指標昆虫類として選定し、その分布状況等を調査した。これらの昆虫類が分布している地点には一定の条件を備えた自然環境が残されていると推定することができる。
調査結果によると、既に絶滅している地点及び生息環境が破壊されている地点の割合が高い昆虫は、大型のタガメと湿原の代表種であるハッチョウトンボである。一方、ムカシヤンマやガロアムシ目は比較的生息地域が残っている(第1-2-2表)。
また、昆虫の絶滅もしくは減少した原因についてみると、タガメについては薬物散布が、ハッチョウトンボについては宅地造成や観光開発が多くあげられている。一方、ギフチョウ、ヒメギフチョウ、オオムラサキについては乱獲のほか、森林の改変が主な原因としてあげられている。全般的にみても乱獲のほか、薬剤散布、森林伐採、宅地造成などにより昆虫の生息できる環境が狭まってきている。
特に、東京都においてはタガメとハッチョウトンボが姿を消し、また、大阪府でも指標昆虫が全般的に大幅に減少しているなど大都市においてこれらの昆虫が生息できる自然環境が失われてきているといえよう。