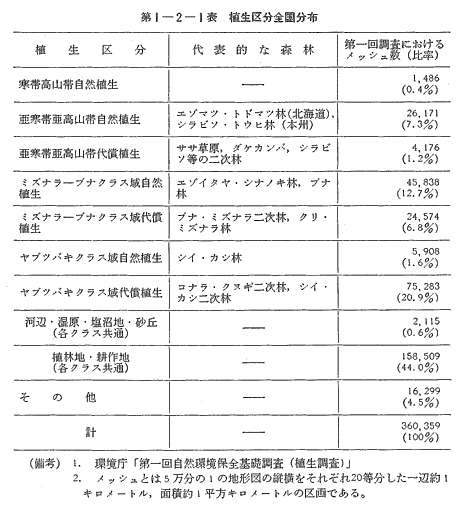
1 植生の状況
世界全体の森林面積が、全陸地面積の約3割であるのに比べ、我が国は国土の3分の2以上が森林でおおわれており、世界でも有数の森林の豊かな国となっている。
森林の成立と種類を決定する要因は、主として気温と降水量であり、亜寒帯から亜熱帯にまたがり、高標高の山岳地も各所にみられる我が国では、多様な森林のタイプがみられる。
第一回調査では、森林の成立と種類を規定する要因として、緯度や標高のほか、人間活動による影響もある程度考慮することにより、植生の区分を行った。その結果によれば、第1-2-1表にみるように植生区分は面積の多い順に植林地・耕作地、ヤブツバキクラス域代償植生等となっている。
また、植林を除き我が国の代表的な森林についてみると、面積の大きい順にコナラ・クヌギの二次林、エゾイタヤ・シナノキ林、ブナ林等となっている。
これらの植生区分について自然性の度合をみると、最も自然性の高いのは亜寒帯・亜高山帯で、次いでミズナラ・ブナクラス域(冷温帯・低山帯)であり、最も改変を受けているのはヤブツバキクラス域(暖温帯・亜熱帯)であった。
一般に、我が国の植生自然度は、北日本ほど高く、南日本は極めて低い。
北日本における自然性の高さは、北海道に広大な面積で残されているエゾイタヤ・シナノキ、ミズナラなどの広葉樹やエゾマツ、トドマツの針葉樹の自然林、東北地方のブナ林などの存在に負っている。
このように広大な自然林は、ヒグマやツキノワグマ等の大型哺(ほ)乳類の安定した生息環境となっている。
第二回調査では、植物群落のうち開発などによって急激に減少しつつあるものなどを「特定植物群落」とし、その分布状況等を調べている。このうち減少の著しい照葉樹林と破壊されやすい湿原についてその状況をみていくこととする。
(1) 照葉樹林
照葉樹林は、本来、我が国の暖温帯の低山地の極相林に普通みられるものであるが、世界的には気候的な要因から分布が極めて限られており、朝鮮半島南西部、中国の華中の揚子江以南、南西部の低地及び日本の南西部に分布しているにすぎない。
我が国における照葉樹林地域は、古来日本人の主たる生活圏域であったため、人間活動による改変が進んだところである。調査の対象としたまとまりのある照葉樹林(903カ所)の総面積の43%は大分、宮崎、鹿児島の3県で占められ、これらの地域では、比較的規模も大きいが、全般的には、10ヘクタール未満のものが全体の8割以上を占めるなど、小規模な群落が散在しているにすぎない状態となっている(参考資料3)。
なお、調査対象照葉樹林のうち半分近くを占める428か所が、付近の人々から鎮守の森などと呼びならわされ、親しまれてきた社寺林等であり、近年の身近な自然の保護や歴史的雰囲気のある快適環境に対するニーズの高まりの中で、その保存は重要である。
(2) 湿原
日本の湿原には、サロベツ原野のツルコケモモ、ミズゴケ群落から、沖縄県西表(いりおもて)島の浦内川河口のマングローブ林周辺のミミモチシダ群落まで多様な植生群落が存在している。湿原は、植物の宝庫であると同時に人間活動の影響を最も受けやすい自然といわれており、山間部の高層湿原の多くが、国立、国定公園内の核心的部分として厳正に保護されているのに対し、低地部の湿原は開発の対象ともなりやすく、人間の生活圏に近いところでは姿を消したものは少なくない。現在残されている湿原のうち大規模なものは長野県以北に偏在し、面積でみると9割以上となっている。特に、北海道には数千から1万ヘクタールを超える大規模な湿原が分布している(参考資料4)。