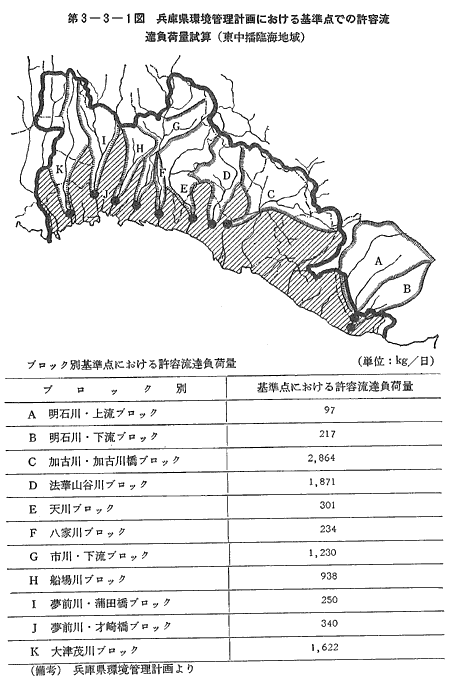
2 環境利用制御の新たな展開
我々は環境を様々な形で利用し、そこから測り知れない恩恵を受けている。この環境は、広くは「宇宙船地球号」のレベルから、狭くは居住空間を一歩出た路地や庭先のレベルまで、多くの主体が共有し、共同で利用し相互に影響を及ぼし合う限られた空間である。我々は、都市化と産業化を通じてこの有限な環境資源をより多く多様な形で2次的環境利用に供してきている。これに伴い環境を共有し利用しあっている様々な主体間で利害対立が生じ、公害問題が社会問題となった。
公害問題はかなり大規模な二次的環境利用を行っている主体である産業活動と地域住民の間に加害者と被害者という不幸な関係を生み出したといえる。
このような環境利用の混乱を事前に回避する努力を払わなければ環境問題を加害者と被害者という一元論で割り切り、共有の財産である環境を多様に利用しなければならないという最も基本的な視点が失われることになろう。産業化と都市化が進展していく中で、個々の環境利用の主体に対してその環境利用の正確な影響を事前には握できるようにすることによって環境利用の主体を郊外や自然破壊の加害者の立場に陥いることのないようにしようというのが環境利用制御の基本的なねらいの一つである。
人間活動と環境との幅広い結びつきを調整して行くためには、環境資源の状況、特性の把握、環境利用のニ―ズの集約、環境利用が環境資源に与える影響の事前評価、そして環境利用の調整のためのシステムとル―ルの確立など多くの面での施策の多面的な前進が必要であろう。それらの全体像については、なお、今後の検討に待つべき部分が多いが、今日各地で環境問題の広がりと、これまでの公害防止対策の成果及び地域住民の環境への多様なニ―ズの高まりを受け、環境利用制御の新展開の手がかりとなる動きが起こっている。
この節では、環境問題の多様化の中で、地方環境行政がより総合的、計画的な環境利用の制御を目指して検討を進めている地域環境管理計画などの新しい環境政策への展開へのいくつかの試みを見ることとしたい。
(1) 環境資源の現状の把握
これまでの事後的な公害防止政策体系における環境の状況は握の中核は、大気中や水中における環境基準の設定された特定の物質の濃度の測定であり、この環境情報としての重要性はいうまでもない、しかしながら、事後的、対症療法的な公害防止から進み、より総合的、予見的な視野から環境利用の制御を進めて行くとき、その基礎にはより多角的な環境資源の状況の把握が求められる。例えば水質汚濁を考えれば、同一量の汚濁負荷が水域に流入しても汚濁物質を受け入れる水域における希釈、沈着、生物による浄化等の浄化作用の大きさにより、汚濁の範囲、程度が大きく異ってくる。このような自然の浄化力をは握することは予見的、計画的な汚染防止を図る上で極めて重要である。また流入する汚濁負荷についてもこれを予測あるいは制御するためには、流域の自然条件、経済社会的条件についての広範な情報が必要となる。
このような発想のもとに、従来の環境情報の粋にとどまらず、環境資源の状況をより広範なデ―タ―で表現し、総合的な環境管理の基礎的な資料として整備して行こうとする試みが石川県や宮城県などで進められている。
石川県においては、昭和52年〜53年に「環境基本情報モデル作成調査」を行い、良好な地域環境の達成維持を目的として地域環境管理計画を推進していくときに必要となる地域環境の現況等に関するデ―タ―を収集・整理し、これを「環境基本情報書」としてまとめている。この「環境基本情報書」の中では、収集・整理すべき環境資源に関する情報が環境資源目録としてリスト・アップされているが、その項目は広く地質、土壌、地形、水文、植生、動物、気象、土地利用にわたり、環境資源の状態を多角的にとらえる中で、適切な開発行為の規制、誘導を考えて行こうとしている。
(2) 環境利用の制約条件の把握
環境資源の有限性は既に公害の歴史のなかで明らかになってきている。適切な公的管理がなされない場合には、産業化、都市化の進行の中で二次的環境利用は無制限に拡大し、ついには一次的環境利用と三次的環境利用を脅かす。このような二次的環境利用を予め適切に制御して行くためには環境資源の状態を中心として、環境利用が環境資源の状態をどのように変え、またそれが他種の環境利用にどう影響するかをは握して行くことが必要である。その一つの考え方は、環境影響評価に見られるように、ある一定の二次的環境利用について、それが環境資源の状態をどう変え、他の環境利用にいかなる影響を与えるかを事前に予測評価するというものである。他方、ある特定の二次的環境利用を与件とするのではなく、環境利用を選択的な土地利用を通じて誘導していく方向がある。予め三つの環境利用の持つそれぞれの価値と相互の影響を勘案してバランスのとれた三つの環境利用を想定した上で、地域的な環境資源の状態と環境利用の現状に則して環境利用の制約条件を見つけ出し、個々の環境利用を誘導していけるようにすることが、より計画的な環境利用調整の立場から要請されている。
これまでの公害対策の経験から、大気、水の汚染物質の規制において一部汚染因子についての総量規制の導入、公害防止計画の策定と実施などを通じて地域における環境利用の制約条件について検討が進みつつある。
第3-3-1図は、兵庫県環境管理計画において示されている各河川の基準点におけるBODについての環境基準を達成する上で許容し得る流達負荷量を示してものである。この特定地点における許容流達負荷量をの考え方をさらに発展させ、一地点における流達負荷から地域で発生する負荷の量とパタ―ンの限界を明らかにして行くこと、すなわち環境資源の制約から人間活動を規制誘導する際の基本的情報としての環境容量を設定して行く方向が望まれている。このためには、地域の自然浄化力や汚染物質の発生メカニズムに関するより深い知識が必要となろう。
また、宮城県では、「宮城県環境管理計画」の中でこれまで都市化、産業化の進展する中で、失われて行った身の回りの自然を保全するとともに、特に自然の保護が必要な地域を明らかにすることなども目的として、地域の植生、動物、景観を総合して自然環境の質を表現する「自然環境質指標」の開発が行われ、この指標と住民の緑に対する満足感のアンケ―ト調査を組み合わせることにより人々の6割が満足することができる望ましい身の回りの自然環境の保全水準を前記「自然環境質指標」で表わした「グリ―ン・ミニマム」を導き出している。
この「グリ―ン・ミニマム」は、新たに農地、山林、原野を宅地、工業用地として開発する際に、その地域において保全すべき自然環境の水準を明らかにしようとする試みであり、新たな環境利用に伴う自然改変の制約条件を示し、開発行為を制御していこうとするものである。
環境利用の制約条件といっても、生命、健康にかかわる保全水準から導き出される限界は正に絶対的な許容限度であるが、一方生活環境の質の向上に着目した環境保全水準は広い選択可能性を持っていることに留意する必要がある。望ましい環境の水準は、様々な環境利用が社会にもたらす効用を総合的に見て決定されるものであり、地域の自然、社会の諸条件によって変わり得るものである。様々な環境利用と環境資源の状態の適切な組み合わせを選択するためには、個々の環境利用それぞれが持つ価値とそれが他の環境利用に与える影響を環境資源の制約条件の中で総合的に勘案し、そのなかで三つの環境利用の適切なバランスを確保していくための環境保全水準を見つけ出して行くことが必要となろう。
(3) 土地利用からの環境利用制御
環境利用の制御の中で、最も基本的なものとして土地利用の調整があげられる。土地は生産・生活の基盤を形成し、その利用のされ方はその地域での環境利用を基本的に規定する。さらに、我が国では土地は環境資源の中でもその量的制約が強く、その利用権の自由な行使によって環境利用の混乱を大きくしてきたことは否定できない。したがって、環境の適切な利用を進めるために土地利用の調整の必要性が極めて高いといえる。
公害防止の施策体系においても個別排出源の規制では対応が困難な課題等について土地利用規制が行われ、また、自然環境保全対策においては、土地利用規制がその中心的施策であったことは既に本章第1節で見たところであるが、今後の環境利用制御にあっては、環境の適切な利用を計画的に実現していくという観点から、土地利用の誘導、規制手法を充実していくことが有効な対応として求められている。
今日、多くの都道府県で進められている地域環境管理計画の検討の中で極めて重視されているのが、土地利用の誘導を計画的に行っていくための情報としての土地の利用適性の把握である。
一定の広がりを持つ地域の中で、様々な環境利用の要請が混在するとき、どの土地をどの用途に利用すべきかということを総合的に判断することは極めて重要である。その判断が適切になされない場合には、ある土地でしか満たすことのできない環境利用、例えば、かけがえのない優れた自然の利用などが、一切行うことが出来なくなったり、既に環境への負荷が集中し、環境が劣化している地域で、人口、産業の集中に伴う環境負荷の増大をもたらすような土地利用転換が行われ、環境の劣化がさらに進行したりする。
既に各種個別法に基づき行われている土地利用規制、例えば自然公園法に基づく自然公園での開発規制などもある特定の環境利用と、そのために適した環境資源を確保するために行われているものである。しかしながら限られた土地を様々な環境利用のなかのどの利用に供するかを判断するためには、広い地域のなかで個々の土地の持つ条件、適性を明らかにし、広域的、総合的な視点から当該土地のいくつかの利用可能性を比較検討して行かなければならない。このような土地の利用適性があらかじめ把握され、様々な環境資源の利用主体、例えば開発行為の計画主体と地域住民及び環境保全の責任を有する主体に予め明らかにされることは、より望ましい環境資源の利用が選択されて行くための重要な基礎となるものと考えられる。