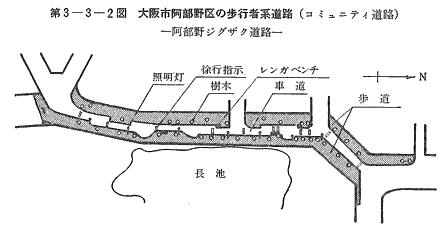
3 快適環境の創造の可能性
環境資源の利用が混乱し、様々な環境問題が起こる中で、人々は今までの物的豊かさの追求に終始した環境資源の利用を反省し、真に望ましい環境とは何かを考え、その姿を求め、つくり上げはじめている。高度成長期に市場のメカニズムによる調整に偏って進められた環境の改変に対して生命、健康を防衛することからはじまった環境保全は、今日、積極的に今まで蓄積された富と技術と文化のうえにどのような望ましい環境をつくり出していくかというところに進もうとしている。
30年代から40年代にかけて、主として工場排水の排出に伴い、我が国の都市内の河川が極めて深刻な水質汚濁の状況を示し、いくつもの河川が悪臭を発し、魚が死に絶えたことはよく知られている。また一方で、高密度化した都市構造の中での洪水予防のための河川改修は、いきおい人工的、直線的な河川をつくり上げることとなり、この双方があいまって、都市の中小河川の多くが人の生活のつながりを失った単なる放水路、下水路と化していった。
東京の下町、江戸川区を流れる古川もそういった都市河川の一つであった。この古川を再び人々が水と親しめる空間として再生させようという試みが始まったのは40年代も後半に入り、自然が失われつくされ、人々がかつての水辺にあった安らぎと潤いの価値にようやく気がついてからであった。
古川の再生は、まず川底にたまったヘドロのしゅんせつに始まり、次いで良質の土を客土し、さらに玉石を敷きつめ、あるいは樹木の植栽を行い、江戸川から水を浄化ののちに引き込み、全長1.2kmにわたる人が水と触れ合い、親しめる空間がつくり出された。古川は、古川親水公園と名付けられ、高密度化し、自然との触れ合いのなくなった都会における数少ない人々の豊かな潤いのある空間として機能し、子供たちが魚をとらえ、あるいは水泳をし、川辺では多くの人が散策を楽しみ、祭りも行われている。(写真1)
同じく水辺環境の再生の例として福岡県柳川市でのクリ―ク(用水路)の浄化事業があげられよう。柳川は筑後川が有明海に注ぐ河口部に位置し、市内には水利と土地かさ上げのために掘られたクリ―クが縦横に走り、かつては舟運、飲料水の供給をはじめとして柳川での生産・生活の両面にわたってその中心的役割を果たしてきていた。この柳川のクリ―クを自動車交通の発達に伴う舟運の衰退、上水道の整備による水供給機能の喪失などから次第にその維持管理がなおざりにされ、40年代には雑排水の流入により水質汚濁が進むとともに、水辺は荒廃して行った。このため、52年になって、ついに市街地の荒廃したクリ―クを埋立て、下水溝にとりかえてしまうことが計画されたが、一方で市の行政内部に柳川の象徴でもあり、かつては市民が生活のよりどころとして大切にしてきたクリ―クを埋立てによって永久に放棄してしまうことへの反省が生まれ、ついに埋立て計画が破棄され、52年12月には新たにクリ―ク及びその周辺を浄化し、整備し、再びかつての清流を取り戻すため、河川浄化計画が策定された。
その後、市当局と市民が一体となってクリ―クのしゅんせつ、流水の確保、水質汚濁の防止、水路の維持管理の徹底が進められ、さらに河川、水路の周辺に遊歩道、緑地等も整備されていった。今日柳川ではクリ―クの荒廃が回復され、一時は失われていた市民のクリ―クとのつながりが蘇えり、個性のある水辺環境が形成されている。(写真2)
水辺環境の問題以上に今日都市環境のなかで問題となっているのは、自動車利用の増大に伴う交通公害やのびのびと歩ける空間の喪失の問題である。都市の中の生活道路は過密化した今日の都市においては、住民の様々な要請を受けている。すなわち、地域の人々はそこで会話、散策、遊びと楽しみ、また、何よりも安全な歩行が出来ることを望んでいる。このような人々の要請を限られた空間で実現する新しい試みを大阪市の阿倍野区での試験的な生活道路づくりに見ることができる。
大阪・阿倍野でつくられたモデル的な生活道路(歩行者系道路―コミュニティ道路―)は、通称、「阿倍野ジグザグ道路」と呼ばれている。これは、この道路が通過自動車交通を減少させるとともに、自動車の走行速度を低下させるため、従来の道路づくりの発想を転換し、あえて自動車の走行に不適なように、ジグザグ状に設計されていることから来ている(第3-3-2図)。
この道では、広々として歩道にベンチが置かれ、樹木が豊富に植栽されており、従来自動車の走行利用という単一の目的に特化して整備されて来た道路空間が、自動車の走行を一定の範囲で許容しつつ、歩行、休息、会話、遊びなどの地域の人々の多様な要請を満たす豊かな生活空間となっている。(写真3)
このように、歩行というヒュ―マンなスケ―ルを生活空間に蘇生させることによって快適環境を創造していこうとする大阪・阿倍野の事例が自動車という同時代のものと新しい空間の調整を目指したものであるとすれば、東北の田園都市、岩手県遠野市の事例は、柳田民俗学の集めた「遠野物語」において、土地と歴史の結びつきを蘇生させることにおいて時間的連続性の中に快適環境を創造していこうとするものである。このような歴史の継承は、街並み保存を始めとする多くの町づくりの事例に共通して見られる一つの重要な要素である。歴史を継承し時間を共有してきたという地域の共同の意識と個性を環境の快適性の核に育てていこうとするものである。(写真4)
以上見てきたように、今地域では環境の望ましいあり方を見直し、つくり上げようとする動きがはじまっている。古川は、行きつくところまで劣化してしまった都市環境を再びまったく新しい人と水との触れ合いという価値に着目する視点からつくり変えてしまった好例であり、柳川は、荒廃しつつも残っていた環境資源を再生し、かつて人々の生活の中まで息づいていたその利用を蘇生させている。また、阿倍野の例は、今までの産業化、都市化のなかで半ば固定化していた道路空間のあるべき姿に対し人々の望む空間を追及していく中で大きな転換をせまっている。さらに遠野市の例は、市民の活動の盛り上りの中で、歴史や民俗を風土を踏まえながら継承していこうとするものである。そこに環境の快適性と文化の接点が見い出せるはずである。
このような地域の自主的な快適な環境づくりの活動とその成果に特徴的であることは、地域の人々の旺盛な環境改善への工夫と参加意識に支えられ、同時に活動の過程と成果がさらに人々の環境改善への関心と意欲を増大させていることである。江戸川区では、現在、区民の益々高まる水辺へのニ―ズを受け、さらに大規模な親水公園計画に着目している。また、柳川のクリ―クの再生は、当初の一部の行政当局者の努力から大きな環境改善へと発展してきている。
このような身近かな環境を行政、住民、企業等様々な主体が一体となって快適なものにしていくことは、同時に快適な環境づくりに留まらず、総ての人が係わり合っていく環境というものの管理全般についてそれぞれの主体が自らの問題として環境を考え、主体的に環境管理に参加して行く一つの契機とも考えられる。より広い保全の目標と施策の体系を持つ環境管理は、その目標の決定についても、施策の遂行においても地域の住民の環境改善への積極的な意思の表明と理解・協力が必要不可欠であり、今日ようやく高まりつつある人々の環境改善への参加意欲を活かす環境管理のシステムが望まれる。
人間活動は常に環境とのかかわりを持って行われ、環境との間で相互に影響し合って営まれている。これまで人間による環境改変は、主として環境中の物質・エネルギ―循環を人間の人工的な循環に出来るだけ取り込み、環境からの自律性を高めながら大量生産、大量廃棄のパタ―ンを拡大していった。この過程での環境管理は物的豊かさの追求の中で生ずる環境の劣化を生命、健康の維持という限界的レベルで押しとどめることに留まっていたといえよう。しかし、今日我々は積極的に環境資源の持つ多様な価値の中から美しさや安らぎ、潤いといった価値に着目し、その価値を高める方向で環境に手を加え、あるいは環境利用を調整することが可能であることを知るに至っている。
地球的規模の環境から身の回りの生活空間の設計に至るまで、自然の多様な活力を積極的に活用しながら我々の環境利用を自ら制御し、快適性の追及を通じて、誰もが共有できる身近かな価値を環境につくり出していくことによって、高密度な様々な環境利用の共存を可能にしていくような環境経営を考えるべき時期に来ているといえよう。