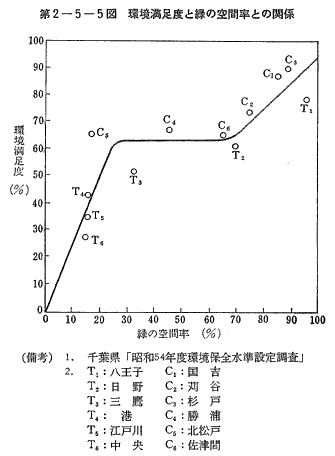
2 自然へのニ―ズ
都市域の拡大に伴って、都市を囲む自然のヒンタ―ランドが縮小するとともに都市内の自然は貧弱なものとなっている。このような都市化の進展するなかで人々の自然に対するニ―ズがどのように現われているかを見ていこう。
千葉県で行った「環境保全水準設定調査」によって日常生活空間における緑の空間の比率と人々の環境満足度の関係を見ることができる(第2-5-5図)。山林・原野、水田・畑地、河川・湖沼岸、公園等いわゆるオ―プンスペ―スを緑の空間とし、市町村別にこの緑の空間の全面積に占める割合とそこに住む人々の環境満足度の関係を見ると、緑の空間率が70%以上の地域と30%以下の地域で緑の空間率の増大が環境満足度の上昇と強い相関を示し、緑の空間率が30%から70%までの間の地域においては、緑の空間率の変化はほとんど環境満足度に影響を与えず、60%以上の人が環境に満足している。
この千葉県の調査は、都市周辺と都市内の山林・原野、水田・畑地、河川・湖沼岸、公園等の緑のオ―プンスペ―スが、全域面積の70%を越える地域と30%以下の地域の両端で、そこに住む人々の環境全体の満足度に対して比例的な効果を持っていることを示している。
次に、内閣総理大臣官房広報室の「居住地の魅力とまちづくりに関する世論調査」(54年調査)によって、人々が住んでみたいと思っているまちのイメ―ジと現実の居住地としての都市の選択との間のギャップから人々の自然のニ―ズを見ることができる。
第2-5-6表は、「住んでみたいまち」のイメ―ジを1つ選んでもらったものであるが、57%の人が「水やみどりが美しいなど自然の多いまち」を、20%の人が「古都や城下町といわれるような落着いたまち」を、17%の人が「雑然としていても生活する上で便利なまち」を「住んでみたいまち」のイメ―ジとしてあげており、現在住んでいる都市の規模による差がほとんどないことが注目される。このことは現在の居住地の規模に関係なく半分以上の人が住みたいまちとして自然との強い結びつきをイメ―ジし、5分の1前後の人が落着いたまちと便利なまちをそれぞれイメ―ジしていることを示している。ところが同じ調査によって「仮にあなたが居住地を選ぶとしたらどの地域に住みたいか」という現実の都市の選択を求めると、第2-5-7表に見られるように、大都市居住者は同じ大都市を、地方主要都市居住者は同じ地方主要都市を選択するという水平移動した居住地選択を行う人が多く、しかもその理由を、複数回答で質問した第2-5-8図に見られるように都市選択の理由として「交通機関の便利さ」と「日常生活の便利さ」をあげる者が「自然環境」を上回っている。
このイメ―ジの都市選好と現実の都市選択における自然指向のギャップが、現実の都市における満たされない自然指向を暗示しているといえるであろう。
このような現実の都市における満たされない自然指向が、自然への接触を求めるレクリエ―ション活動になって現れている。前述した内閣総理大臣官房広報室の行った「森林・林業に関する世論調査」によって、このレクリエ―ション活動の実態を見ることが出来る。
この1年間に山や森、渓谷など仕事を離れて行ったこのがある人は54%、内人は46%で5年前の前回調査とほとんど変化がない。行ったことのある人に、その目的を複数回答方式で質問したところでは「すぐれた景観や風景を楽しむため」が35%と最も多いが前回より4ポイント低下し、「何となく自然の中でのんびりしいたいため」が32%で2ポイント低下しているが、「キャンプやピクニックなど野外生活を楽しむため」が25%、「ドライブを楽しむため」25%、「釣りや狩り、山菜つみなど野外生活を楽しむため」24%でそれぞれ前回調査より3、8、2ポイント上昇しており、人々の自然指向が活動的かつ多彩なものとなっていることを示している。
都市化の進展に伴う人々の自然指向の高まりの中で自然のヒンタ―ランドの価値はきわめて高いものとなっている。
しかし、反面、このような自然指向もこれを受けいれる体制が準備されていないときは、一部の自然公園、観光地等への利用者の集中を招き、これらの地域の自然環境に好ましくない影響を与えるおそれがあることにも注意を向けるべきである。
国立、国定公園の利用者は、35年に年間延べ9、016万人であったが40年には2億9、953万人、45年には5億218万人と急増し、48年以降は6億人前後で推移している。
このような利用者数の増大はこの間に、国立、国定公園の新規指定が行われたことも一因ではあるが、都市住民の自然ニ―ズへの高まりを反映して旧来の主要な公園においても顕著な増加がみられている。
個別の国立公園について見ると、その公園の知名度や都市との距離などの地理条件、輸送手段の整備の状況等によって利用者数には大きな差があるが、例えば、首都圏の周辺に位置し、古くから観光地として知られた富士箱根伊豆国立公園の年間延べ利用者数は54年には8、000万人余を数え、同年の全国立公園の利用者数の約4分の1を占めるなど、一部の公園あるいはそのうちの特定の地区における利用者の集中傾向がみられる。
このような地域においては、利用者の増加に合わせて、各種レクリエ―ション施設の整備が進められてきているが、周辺の自然環境との調和という観点から見ると、開発がすでに許容限度に達していると見られるところも認められている。
こうした傾向は、景観保護の観点から規制の及ばない一般の観光地では一層顕著であり、高層ホテル等が林立し、その結果、もはや都市住民の自然ニ―ズには十分に応えられない観光都市に変貌してきたところも少なくない。
また、高山性の植生、景観等を特徴とする地域では、その自然の生態系の脆弱さ等その収容力の低さに対し過剰利用が行われることより自然環境への悪影響が生じやすい。
以上のように人々の多様な自然指向に対応した自然の受け入れ体制の可能性を考えた場合、都市周辺の人々が手軽に近づける人為自然環境のもつ親しみやすく多様な自然の豊かさが極めて大きな意味を持っている。
このように都市周辺の人為自然環境こそ、第1章第2節でも触れたように、人々が自然の豊かさと潤いを肌で感じ親しみのある自然の律動の中で都市生活が強いる緊張を解き、神経の失調を治ゆすることのできる貴重な空間である。都市化が進展して行く中で、極めて広い公共空間を形成している河川、湖沼、海浜などの自然は人為自然環境の中でも戦略的重要性を持っている。
滋賀県が55年4月に出した琵琶湖ABC作戦では、この我が国最大の湖の自然の保全の重要性を次のような言葉で表わしている。
琵琶湖の周辺は開発の進行に伴い、自然のままの湖辺が徐々に少なくなってきています。昭和30年に約420ヘクタ―ルあったヨシ自生地が、現在では半減するなど、ヨシ自生地の松林が少なくなり、貴重な水辺空間としての価値や風景としての価値が損なわれつつあります。
また、戦中・戦後にかけて、食糧の確保の面から、琵琶湖や内湖の干拓・埋立が盛んに行われましたが、昭和20年以降干拓された面積は約2,480ヘクタ―ル、埋立された面積は約431ヘクタ―ルとなっており、合わせて約2,911ヘクタ―ルの水面面積が減少しています。
近年、湖周辺の開発が進んだことによって、ヨシ、マコモ等水生植物の自生地が減少し、このことが魚介類、水生昆虫や水鳥の繁殖および生息に大きな影響を与える一方、従来、内湖や沼地を経由して流入していた汚濁水は直接琵琶湖に流入し、その水質に悪影響を与えています。
自然的湖辺の美しい景観は、人と湖のかかわりを深める場としての高い文化的価値を有し、かつ水質浄化の機能をもっている。従って湖岸堤、港湾、漁港など湖辺に必要な施設とくに大規模な構造物の設置に当たっては関係法令等の適正な運用により、環境の保全につとめる。
この琵琶湖に関する記述は、水という巨大な自然の生態系を内包した典型的な人為自然環境が持っている自然の価値の見直しを求めているといえる。その基本には、湖沼とその周辺が市街地化、埋立、干拓など都市域の拡大と生産の安定と拡大を求める各種の開発行為により、豊かで多様な自然を備えた自然的環境が急速に失われつつあるという認識がある。それと同時に、湖際のヨシ、マコモなどの水生植物が湖の生態系の重要な要素として湖に流入する河川などからの汚濁の浄化機能を持つとともに、湖際の内湖・湿地などが遊水機能を持ち、全体としてこの自然が織りなす自然の景観が高い文化的価値を有していることを明らかにしている。