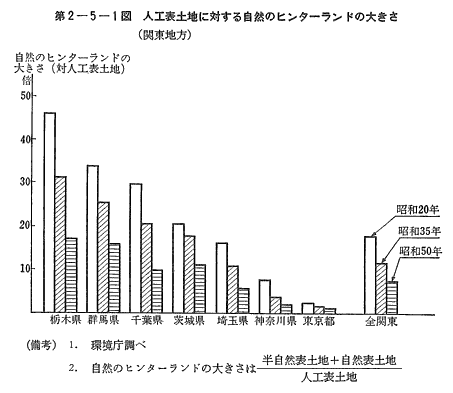
1 都市域の拡大と自然改変
第1章第2節では、関東地方における表土改変状況調査によって我が国の戦後の自然改変の典型を見た。戦後30年間、生産、流通、消費を通じる経済的な効率主義とこれに対応した都市の機能主義に主導されて国土利用が進められていた結果、市街地と工業用地が周辺の人為自然環境を無秩序に侵蝕し、安全性と利便さを求めて全国的な自然改変が進んできた。このため動植物相は、甚大な影響を受けるとともに、人工の極相である都市域では自然が極めて貧弱なものとなっているばかりでなく、都市を囲む自然のヒンタ―ランドも相対的に縮小してきている。
第2-5-1図は、都市と都市を囲む自然のヒンタ―ランドの大きさの変化を見るため、表土改変状況調査から、都市を中心とする人工表土地の大きさを1として、半自然表土地と自然表土地を加えた都市を囲む自然のヒンタ―ランドの大きさの変化を関東1都6県について見たものである。人工表土地と都市を囲む自然のヒンタ―ランドの大きさの比は、関東では昭和20年の1:17.7から50年には1:7.2と都市に対する自然の縮小は顕著である。
このような現象は大都市圏域に限らず、全国的な都市化の進展に伴い各地で生じている。例えば、第2-5-2図は、金沢市を中心とした面積約140k?について、37年と52年の土地利用の変化を見たものであるが、人工の構造物によって覆われ、人工化された土地の割合は15年間で14.6%から33.4%へと拡大し、この地域内での人工化された土地と緑被地の大きさの比は1:5.5から1:1.7へと大きく変化している。
都市化の進展に伴って、都市を囲む自然のヒンタ―ランドは縮小を続けているが、都市内部の自然も貧弱なものとなってきている。都市の自然の現状を都市内の緑地とそこに生息する鳥類によって見てみよう。
我が国の都市は、主要先進国の都市と比べ著しく自然的な緑地が小さい。主要先進国では、例えばパリのブロ―ニュの森(860ヘクタ―ル)、ウィ―ンのウィ―ンの森(7、457ヘクタ―ル)、フランクフルトのフランクフルトの森(4、200ヘクタ―ル)等の自然に近い樹林地がある。東京では明治神宮(89ヘクタ―ル)、自然教育園(20ヘクタ―ル)などが一般的に開放された自然に近い森であるが、上記諸都市の樹林地と比べて大きさのちがいは明白である。都市内の緑地が都市の物質・エネルギ―の循環のなかで生物種の保存、環境の浄化等の自然のもつ機能を果たすとともに、都市住民の自然への渇望をある程度満足させるためには、緑地が大規模であるか否かは極めて重要な意味を持っている。このことからすれば、明治神宮や自然教育園などの存在の重要性が理解されるとともに、その規模の主要先進国の都市樹林地との比較から、我が国都市における自然の貧弱さが浮かび上がってくる。
第2-5-3図は明治神宮、自然教育園に生息する鳥類の種類の変化を見たものである。明治神宮及び自然教育園は、自然性の高い樹林が形成されており、特に自然教育園については東京の自然植生が残されているが、その周辺部で緑地が減少を続けるなどして人為が高密度化を続けたため、わずかに残された緑地であるこれら2つの林地を取り巻く周囲の自然環境は急速に劣化してきた。
このような周辺地域の人工化の進行に伴い鳥類の種類が急激に減少し、周辺地域の人工化がほぼ完全に進んだ近年、その減少傾向が鈍化していることは、生息域内そのものの改変が小さい場合でも、周辺地域の自然改変がその生息に間接的な影響を与えたものと考えられる。
人々の居住地の周辺から、自然が失われていったことを人々の意識から見てみよう。
内閣総理大臣官房広報室の行った「森林・林業に関する世論調査」(昭和55年調査)によると居住地周辺(住居から歩いて20〜30分の範囲)の森とか林に対する充足感については恵まれていると考えている人が57%、恵まれていないと考える人は41%となっている。これを前回の調査(51年)と比べると恵まれているは、前回の63%より6ポイント低下しており、恵まれていないは35%から6ポイント上昇している。地域別に見ると東京都区部において充足感が低く(16%、前回は37%)、都市規模が小さくなるほど充足感が高い。身近かな森や林がどのように変化したかを質問した結果が第2-5-4表である。森や林の増減については5年前と比べて「減っている」が41%で、「増えている」の5%を大幅に上回っている。
東京都区部を除くと「増えている」はいずれも5%前後で低く、「減っている」は40%前後でほとんど差がない。東京都区部は「以前から森や林が近くになかった」(41%)ため「増えている」0パ―セント、「減っている」17%となっているがそれ以外の地域では都市の規模を問わず、森や林の減少が進んでいると人々が認識していることを示している。