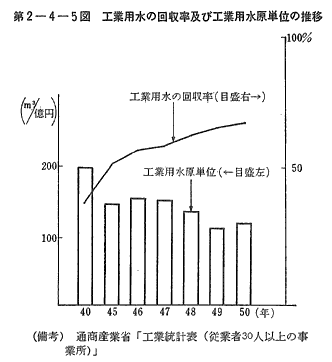
2 水利用の変化
我が国の人口1人当たりの降水量は世界平均の約6分の1程度であり、しかも降雨期が季節的に偏っていることや地形が急峻で河川の流路が短かいこと等から、水資源の利用という面から不利な状況にある。他方、水需要は既に見たように都市化や産業化の進展に伴って、都市用水を中心に急増しており、今後とも水需要のひっ迫が予想されている。また、このような水利用の増大は、汚濁物質を含む排水の増大を伴う一方、自然水の減少等による自然の浄化作用の低下等を通じて水質汚濁の要因となる。さらに、地下水の過剰採取による地盤沈下等の問題を生じている地域もあり、環境保全の面からも水利用の節約と水利用の合理化を含む適切な水資源の使用を推進することが必要になっている。
長期水需要計画によれば50年の水利用は全国的には農業用水が65%と最も多く、次いで工業用水の21%、生活用水の14%の順となっていが、関東臨海では生活用水が41%、農業用水31%、工業用水28%と生活用水が最も多く、都市域では生活用水、工業用水の比重が高くなっている。また、水需要の推移を見ると、40年から50年にかけて生活用水が2.1倍と最も高い伸び率を示しており、工業用水が1.3倍(40〜53年では1.2倍)、農業用水が1.1倍となっている。
このような中で、水の再利用が比較的進んでいるのは工業用水である。第2-4-5図は工業用水の回収率(従業員30人以上の事業所)の推移を見たものであるが、40年には全業種平均で36.3%であったが、その後地盤沈下地域における地下水採取規制等への対応や回収率向上のための施策、原水単価の上昇や上下水道料金の負担に対応するための補給水使用量の節減あるいは水質汚濁防止対策の強化により回収水の利用や循環利用が進み、50年には67.0%に高まっている。特に、鉄鋼、化学、石油等冷却用水の使用の多い業種では75〜85%と高くなっている。こうした工業用水の回収率の向上等により、工業用水の原単位(単位生産額当たりの工業用水需要)も低下しており、52年には40年当時の約6割になっている。このように回収水の利用を進めることにより工業用水の有効利用は進展しているが、これまでは冷却用水が中心であり、今後は冷却用水に加え、工程水についてもその回収をより一層進める必要がある。
一方、都市用水のうち約40%を占める生活用水については、排水の再利用を進めるところまでは、ほとんど進んでいないが、業務ビル等で排水を処理した上で水洗便所用水等の雑用水として循環利用する例が増えているほか、下水道においては下水処理水の再利用が進められている。例えば福岡市では、下水処理水を業務用水として循環利用しており、新宿副都心においても超高層ビルの中で下水処理水を水洗便所用水として再利用が計画されている。東京都の「マイタウン構想」に見られるように、歴史的な遺産である野火止用水に多摩川上流処理場から処理水を送水するなど、河川、水道、下水道を一体とした大きな循環系の中で水資源問題を考えるという発想も生まれつつある。また、内閣総理大臣官房広報室では国民の節水意識について調査を行っているが、「ふだん水を心掛けている」が51年調査の59%から54年には66%へと高まっており、節水の理由も「水は限られた資源で大切にしなければならないから」が67%から76%へと増えており、節水に対する意識がしだいに浸透していることを示している。