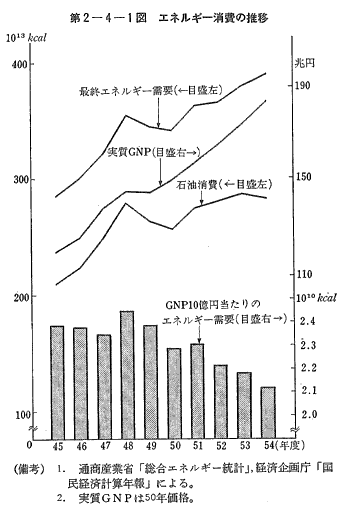
1 エネルギ―と鉱物資源消費の変化
エネルギ―は生産、流通、消費のあらゆる過程で利用され、我々の生活にとって欠くことのできないものであるが、その膨大な消費量が大気汚染などの環境汚染の大きな要因となっている。また、現在のところ我が国は石油中心(全エネルギ―消費の71%)のエネルギ―供給構造になっているが、今後、石炭や地熱等石油代替エネルギ―の利用増大が、十分な環境保全対策が講じられることなく進むとすれば大気汚染の悪化だけでなく、水質汚濁、自然破壊等新たな環境問題を生じるおそれもある。
第2-4-1図は、我が国の最終エネルギ―需要並びに石油消費の最近10年間における推移を見たものであるが、いずれも48年度を屈折点として大きく変化しており、年平均伸び率で見て45〜48年度は、最終エネルギ―需要7.6%、石油消費10.0%であるのに対し、48〜54年度はそれぞれ1.6%及び0.3%に低下している。これを、GNPとの比較でみても、GNP単位当たりの最終エネルギ―消費は48年度以降着実に低下を続けており、経済構造全体の省エネルギ―化が進展していることを示している。
このようなエネルギ―の有効利用による節約を促したのは、48年末に始まるOPECによる原油価格の大幅引上げが大きな要因であると考えられるが、特に産業部門におけるエネルギ―消費に大きな影響を与えている。我が国のエネルギ―消費を部門別にみると産業部門が59%、運輸部門15%、民生部門26%と諸外国と比べエネルギ―消費に占める産業部門の比重が大きく、産業部門におけるエネルギ―消費の節減が全体のエネルギ―消費に対して大きな影響を持っているといえる。
48年度以降我が国の原油輸入価格は、48年の約5,200円/klから55年8月には48,000円/klと約9倍になっているが、このような価格の上昇により産業部門のエネルギ―消費の伸びは大きく鈍化している。第2-4-2図からも分るように、製造業におけるエネルギ―消費は、48年度まで10%を大きく超える伸びを示したあと、生産活動の停滞、省エネルギ―政策の進展もあって49年度、50年度とエネルギ―消費は減少し、その後生産は拡大しているにもかかわらずほぼ横ばい状況で推移している。ことに、エネルギ―多消費型の産業といわれている鉄鋼、化学、窯業・土石、紙パルプ、非鉄等の業種においては、廃熱の回収、設備の連続化、生産工程の改善などによってエネルギ―原単位を低下させており、これらエネルギ―多消費型産業の製造業全体に占めるエネルギ―消費の割合は48年度の74%から53年度には70%へと下がっている。
他方、運輸部門、民生部門においても燃料価格の上昇や省エネルギ―政策の推進によって、エネルギ―消費の伸びは鈍化してきている。しかしながら、民生部門や輸送部門においては1人当たりのエネルギ―消費が先進諸国と比較して少ないこともあって、エネルギ―消費の節減の効果はそれほど大きいとは言えない。
次に、このようなエネルギ―の有効利用が環境保全にどの程度の効果をもったかをみてみよう。
第2-4-3図は、石油消費の節減が大気汚染の改善にもたらした効果を見るため、現実の石油消費と第1次石油危機が起こった48年度以降もそれ以前の石油消費構造を維持した場合の石油消費から54年度における石油節減量を求め、さらに公害対策の効果を見ることにより、代表的な大気汚染物質の一つである硫黄酸化物の排出量を試算したものである。
硫黄酸化物の排出量は、48年度までは主として燃料の低硫黄化による公害対策の進展によって減少したが、48年度以降はこれに省エネルギ―の効果と排煙脱硫装置普及の効果が加わってさらに減少を続けている。仮に48年度以降もエネルギ―消費の節減が進まなかったとすれば、硫黄酸化物の排出量はより大きなものとなっていたものと考えられる。
エネルギ―の節約とともに鉱物資源の有効利用も進みつつある。48年度と比べた各種鉱物資源の消費量は、鉄鉱石11%減、ボ―キサイト8%減となっている。このうち鉄鉱石についてやや詳しく見たのが第2-4-4図である。鉄鋼生産は48年度まで急激な拡大を示したあと、49、50年度と減少し、54年度には再び48年度のピ―クを超えている。一方、鉄鋼生産の主原料である鉄鉱石の消費は、49年度までは生産の拡大に伴って増加しているが、その伸びは鉄鋼生産の伸びに比べ緩やかであり、49年度以降は一貫して減少しているが、この結果54年度における銑鉄1トンを生産するために必要な鉄鉱石の量は45年度に比べ半減しており、鉱物資源の有効利用の進展を物語っているといえる。
以上のように産業部門を中心にエネルギ―及び鉱物資源の有効利用は進展しつつあるが、一方において石油需給の逼迫に伴う世界的なエネルギ―制約のなかで石炭等へのエネルギ―転換が図られており、環境汚染の防止を図るためには、今後はなお一層のエネルギ―、鉱物資源の有効利用の促進を行うとともに今後の石炭等の石油代替エネルギ―の開発利用にあたっては環境保全に十分に留意しつつこれを進めることが重要である。
高度経済成長に伴って30年代以降我が国のエネルギ―消費は石油中心に急速に増大してきたが、公害規制の強化によって公害防止技術の開発が進むと同時に、低硫黄燃料の確保の努力が続けられ、その結果大量の石油燃焼に伴う硫黄酸化物やばいじんによる大気汚染は改善してきたが、しかし、2次にわたる石油危機はエネルギ―需給を一転させ、その結果、石炭等へのエネルギ―転換を進めることが必要となっている。
石炭の開発利用の増大にともなって、開発段階での採掘に伴う水質汚濁、流通段階での輸送及び貯蔵に伴う粉じんの飛散、燃焼後の石炭灰の処理が新たな環境問題として加わるほか、燃料や原料としての利用の段階での燃焼に伴う硫黄酸化物、窒素酸化物、ばいじん等についても石炭の特性により石油に比べ発生量が増大する可能性がある。
我が国では今後の石炭利用の増大は、主として輸入炭に依存する割合が大きいと考えられることから、開発段階での採掘に伴う水質汚濁は大きな問題とはならないであろうが、利用段階での大気汚染、石炭灰の問題を石炭火力発電を例にとってみてみよう。
石炭は石油に比べ単位重量当たりの発熱量が小さいため、同じ発熱量を得るためには、燃焼させる石炭の重量は大きくなること、及びその燃焼特性からより多くの燃焼用空気が必要であることから、同一出力の発電所で比較した場合、排ガス量は2割程度多くなる。
また、単位発熱量当たりの硫黄分、窒素分については石炭の方が石油に比較して一般的に多いため、燃焼に伴う硫黄酸化物、窒素酸化物及びばいじんの発生量は石炭火力の方が多くなる。
現在、これらの大気汚染物質に対する環境保全対策として、硫黄酸化物対策としては、排煙脱硫技術が、窒素酸化物対策としては、ボイラ―での二段燃焼、低Noxバ―ナ―等の窒素酸化物抑制のための燃焼技術が確立しており、窒素酸化物対策としての排煙脱硝技術についても実用化の段階に至っている。さらに、ばいじん対策としても高性能の電気集じん器が広く採用されており、これらの大気汚染物質の排出量を低く押さえるための技術が進んできている。
したがって、今後ともこれらの対策を適切に組み合わせるとともに、所要の対策を推進することにより、環境基準の維持・達成に支障を及ぼさないよう措置する必要がある。
石炭灰についてみると、石炭は、産地により若干の差異があるが、平均して1〜2割程度の灰分が含まれており、これが燃焼後も石炭灰して残るため、その処分が問題となる。
我が国では石炭火力からの石炭灰は約30%がセメントの原材料等として有効利用されているほかは埋立処分されているが、今後の石炭火力の拡大に伴い、石炭灰の発生量が増大するため有効利用の一層の推進を図るとともに、石炭灰埋立処分地の確保を図る必要があるが、この場合において、石炭灰による水質汚濁等の影響、処分地設置による環境への影響等を十分に考慮して環境保全対策を適切に講じなければならない。
以上のように石油需要のひっ迫化は省エネルギ―推進の原動力となり、その結果として環境負荷を軽減させる一方で、石炭等の石油代替エネルギ―の開発利用を推進する必要性を生じさせているが、このため、省エネルギ―の一層の推進を図るとともに、石炭の導入促進に当たっては環境負荷の増大要因とならないよう適切な環境保全対策を講ずるなど環境保全への慎重な配慮が必要であることを示している。
第2-4-3図 硫黄酸化物(SO2