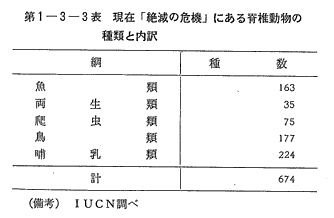
2 野生生物の種の減少
地球上に最初の生命体が出現したのは、おおよそ30億年程前のことだと言われている。この生命の出現以来現在に至るまで生物は様々な種に進化し、出現と絶滅をくり返しながら生物界を形成してきた。いうまでもなく現在でも生物の進化と絶滅の歴史は進行しており、今の生物界の姿が永久不変のものであると考えることはできない。しかしながら、近代に入り人間の自然に及ぼす影響が加速度的に大きくなるに従って、絶滅し、あるいは絶滅の危機に頻している野生生物の出現頻度が高くなっていることが観察されている。
野生生物の個々の種の絶滅についての正確な記録は、おおむね1600年以降に限られており、それ以降現在までに絶滅した鳥類、哺乳類は130種ほどである。この絶滅の頻度は、人類の影響がない場合の自然の絶滅頻度に較べ5〜50倍にあたると推定している例があるが、いずれにせよ近代に入ってから人間活動に起因した生物の種の絶滅が多くなっていることは間違いがないと思われる。
現在、「絶滅の危機」にある生物種は多く、我が国においては、トキ、ニホンカワウソ、イリオモテヤマネコなどが種としての存続があやぶまれ、タンチョウ、イヌワシ、アホウドリなども「絶滅の可能性」があるとされている。地球上で「絶滅の危機」にある野生生物は、IUCN(国際自然保護連合)によってリスト・アップされ公表されているが、これによれば魚類、両生類、爬虫類、鳥類、哺乳類からなる脊椎動物で「絶滅の危機」にあると判断される種の数は674種にのぼっている(第1-3-3表)。
ちなみに、これらの絶滅のおそれのある種の数を現存する種の全体数に対する割合を見ると、哺乳類で約6%弱、鳥類で約2%となっている。
かつて、人間生活による野生動物の絶滅の主要な原因は狩猟行為にあった。例えば、19世紀の初め北米大陸に50億羽生息していたと推定されるリョコウバトは1914年に絶滅したが、この原因は主として農作物への被害防止と食用のための乱獲であったと考えられており、また、我が国の鳥島におけるアホウドリの減少も羽毛の獲得を目的とした乱獲によるものと考えられている。
近年狩猟については一定の制限が課されるようになりその影響は小さくなっているが、一方で大規模な自然改変の進行に伴って野生生物の生存を脅かす主因は生息環境そのものの破壊に変わってきた。
前述のIUCNによって「絶滅の危機」にあるとリストアップされた種の存続を脅かしている要因を見ると、「絶滅の危機」にある種、全674種のうち67%に当たる449種は生息環境の破壊・悪化によるもので、乱獲、侵入種の影響などがこれに続いている(第1-3-4表)。今後とも人間の活動の拡大に伴い生息環境の破壊は、ますます拡大することが予想され、またその回復も極めて困難と考えられる。
野生生物の種の保存の必要性については、国連人間環境会議等の場をはじめ国際的に共通の理解が生まれており、国際協力の体制づくりが進む中で各国の対応も展開してきている。国際協力体制としては、既に述べたようにワシントン条約、ラムサ―ル条約などの多国間条約が発効しているほか、日米渡り鳥等保護条約のような二国間条約によっても野生生物の国際的な保護が進められてきている。我が国における最近の例としては、日中間で日中渡り鳥等保護協定が56年3月に署名されていることは記憶に新しい。
このような国際的協力体制づくりを進めるための国際機関としては、UNEP(国連環境計画)、UNESCO(国連教育科学文化機関)、IUCN(国際自然保護連合)、IWRB(国際水調査局)、WWF(世界野生生物基金)、ICBP(国際鳥類保護会議)などがあり、様々の活動を行っている。これらの国際機関の活動を支援しつつ国際的な野生生物の保護に関する協力は、今後、人口の増大と世界的な経済発展に伴い地球的規模で野生生物の生息環境の変化が進むなかで、更に強力に推進されて行く必要があろう。