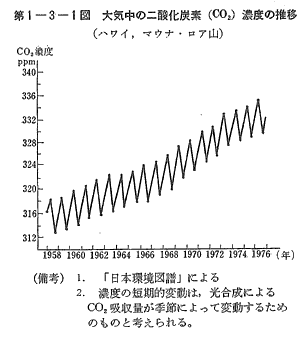
1 地球的規模での環境汚染
(1) 大気の組成変化
地球上の生命をはじめ、気象、気候、海流などの自然の生態系の営みを支えている物質・エネルギ―循環の源泉の大宗は太陽からのエネルギ―である。生命を支えているエネルギ―の大宗は植物の光合成によって吸収される太陽光から供給されるものであり、大気や水の循環も太陽光のエネルギーによって支えられている。人間を含め多くの生物は太陽光と密接に結びついた生理を持っており、常に太陽光の影響を受けている。
このように重要な意味を持つ太陽光は、地球の大気の層を透過する際に大気の組成等により様々な影響を受け、質的量的に変化した後に地表に到達している。また、地表に到達した太陽エネルギ―は最終的には再び大気層を経て地球から放出されている。大気はこの太陽光の地表への入射と地表からの放射に対してフィルタ―に似た役割を持っており、この組成変化は大気と地球上の生物との基本的な結びつきに攪乱的影響を及ぼすことになる。
人間活動が大気の組成を攪乱し、これが地球上の生態系に大きな影響を与える危険性が近年懸念されている。なかでも注目されているものは、大気中の二酸化炭素(CO2)の濃度上昇に伴う地球の熱収支バランスの変化と、環境中に排出されるフロンガスによるオゾン層の破壊の可能性である。
(二酸化炭素の上昇)
大気中の二酸化炭素の濃度は、植物、海洋、土壌を通ずる地球的規模での二酸化炭素の放出、吸収等の収支バランスによって、かなり長期にわたって安定していたと考えられる。ところが、近年、大気中の二酸化炭素の濃度が着実に上昇していることが観察されている。
第1-3-1図は、ハワイのマウナ・ロア山において観察された二酸化炭素の大気中濃度の推移を示したものであるが、季節による規則的な変動を繰り返しながら、年々、1ppm強の濃度上昇が継続しており、同様な状況は南極など世界各地の測定によっても観察されている。
太陽から地表に入射してくる太陽光線は大気中の二酸化炭素を透過するが、一方暖まった地表から放出される波長の長い赤外線は大気中の二酸化炭素によって反射されること(この二酸化炭素の働きは温室におけるガラスの働きと同様であるため、二酸化炭素の温室効果と呼ばれている)が知られている。このため、二酸化炭素の濃度が上昇すると地表からの熱放射が妨げられ、気温の上昇を招き、気候変動や極地の氷の融解による海面上昇を引き起こすと考えられている。
研究段階では比較的早くから、このような自然の変動が起これば農業をはじめとする生産活動はもちろん人間の生活に大きな影響が出るという危険が確認されていた。最近では、多くの国際機関や政府によって現実の問題としてそのおそれが公的に表明されるようになってきている。このような二酸化炭素の問題について警告を行っている公的機関としては、世界気象機関(WMO)、国連環境計画(UNEP)、国連食糧農業機関(FAO)などがあげられる。
二酸化炭素の濃度の上昇については、定量的なメカニズムの解明は未だ十分に進んでいないが、熱帯地方での大規模な森林伐採のよる植物の二酸化炭素吸収の低下と、石油、石炭等の化石燃料の大量燃焼による二酸化炭素の発生量の増大などに起因するとみられている。また、二酸化炭素濃度の上昇と気候に影響を及ぼす多くの要因との間に如何なる相殺あるいは相乗効果があり、あるいはそれによって地球全体の大気循環がどのように変化するかといった問題について、極めて限られた科学的知識しか得られていないのが現状である。また将来予測についても二酸化炭素濃度がどの程度の気候変動とそれに伴う人間活動への影響が生ずるか不明の点が多い。
米国政府は、1980年に発表した「西暦2000年の地球」報告において、西暦2050年には二酸化炭素濃度は現在の2倍となり、平均気温の上昇は中緯度地帯で摂氏2〜3度、極地帯での気温上昇は、その3〜4倍にのぼる可能性があるとしている。なお、これらの数値は、いくつかの仮説に基づいて算出されたものであることに注意しなければならない。
しかしながら、大気中の二酸化炭素濃度の増大とそれに伴う地球的規模の物質・エネルギ―循環の攪乱は、影響が顕在化してからでは不可逆的な環境変化となり、対策の取り得る余地が極めて少なく、取り返しのつかない被害を人間活動に与えるおそれがあることに留意しなければならない。仮に地球の平均気温が一度上がったとすれば、過去1000年間で最大規模の地球の温度変化のスケ―ルを超え、単に温暖化するという現象にとどまらず水循環、大気循環に測り知れないインパクトをもたらすことになると予測されている。
(フロンガス問題)
成層圏オゾン層は、皮膚がんの誘発など人間の健康に有害な紫外線を吸収する働きを持っているが、既に1970年頃から、超音速旅客機の飛行や火山の噴火等によるこのオゾン層の破壊の問題が、地球的規模の環境問題の一つとして注目されるようになっていた。このような背景のもとに、このオゾン層に対するフロン11、12を中心としたフロンガスの影響が近年注目されるようになった。
フロンガスはエアゾ―ル製品の噴射剤や冷蔵庫等の冷媒等に可燃性がないこともあって広く使用されている。フロンガスは化学的に安定であるため環境中に放出されると対流圏では分解せず高く成層圏へ拡散して、そこで光化学反応によって分解し、この分解過程で生ずる塩素がオゾンと反応することにより、オゾン層の破壊が生ずるおそれがあると指摘されている。しかし、この問題は実際の成層圏オゾンの減少を実証することが、現段階では困難であるなど、未だ科学的な解明が十分には行われていない部分がある。
フロンガスによるオゾン層の破壊は、紫外線に対して皮膚が特に敏感な欧米人の間で大きな議論を呼び、科学的に不確定な部分を残しつつも既に米国等においてはエアゾ―ル製品用のフロンガスの生産が禁止され、ECでは1980年の理事会においてフロン11とフロン12の生産能力を現在以上に増大させないことと決定されるに至っている。
(2) 海洋汚染問題
地球全体の物質・エネルギ―循環のなかで海洋の占める役割は極めて大きく、また、水産業、海運、海洋レクリエ―ション等を通じて生活と深く結びついている。このような海洋の環境が汚染された場合には、その影響は極めて広くかつ重大なものになることは容易に想像できるところである。
既に、大気、河川、湖沼あるいは内海、内湾における汚染の進行は、環境の容量、浄化に限界があることを示している。海洋は地球上の総ての陸上の水の合計(氷雪を除く)の実に7、000倍の水を保有し、陸水域や内海、内湾に比較して極めて大きな浄化力をもってはいるが、その浄化力に過大な期待を持つことは出来ない。
第1-3-2図に示すように、既に、海洋においても高い頻度で油濁が発見されている海域が存在しており、またPCB、DDTなどの難分解性化学物質、有害重金属等が海洋中にも微量濃度ながら検出されている。いうまでもなくこれら物質の濃度は通常陸水域や港湾などでのそれに比べはるかに低濃度であり、例えば、1ppb(10億分の1、ppmの更に1000分の1の単位)以下という通常の検査方法では検出できない程の低いレベルであるが、これら難分解性化学物質のうち生物濃縮性を持つ化学物質は低濃度であっても食物連鎖を通じ生体内に濃縮される傾向があることなどから、海洋中の動植物も含めグロ―バルな監視が必要であるといえよう。
第1-3-1図 大気中の二酸化炭素(CO2