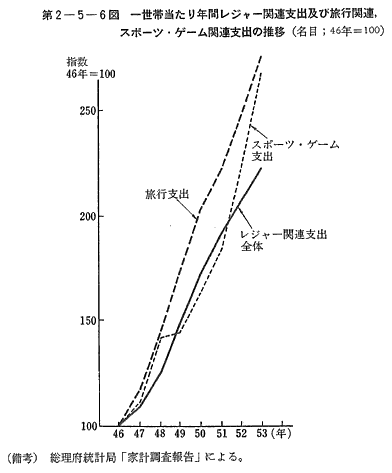
3 優れた自然への欲求の強まり
日常の居住環境に対する快適さへのニーズを高めてきている大きな要因である自然やオープン・スペースに対する欲求は、居住環境を超えて、国立公園をはじめとする優れた自然への欲求の増大につながっている。
第2-4-6図は、レジャー関連支出全体の伸びとそのなかでの旅行及びスポーツ・ゲーム関連の支出の伸びを比較したものであるが、レジャー関連支出のなかでの積極的余暇活動の比重の高まりを示している。
また、内閣総理大臣官房審議会が行った全国旅行動態調査によると、国民一人当たりの旅行回数は、42年が0.55回であったのに対し、47年が0.75回、51年が0.96回と直接的な伸びを示しており、国民の余暇活動の活発化の一端をうかがわせるものとなっている。
52年に策定された第三次全国総合開発計画においては、今後とも国民の余暇時間は増大すると予測されているとともに、余暇時間の増加割合を上回るレクリエーション活動、特にスポーツ型レクリエーション活動の増大が予測されている(第2-5-7表)。
このような観光レクリエーション活動の拡大に加え、その活動の内容においても自然志向が強まっている。国立公園の利用者数は、昭和40年代に2倍以上になっており、かつ国立公園のなかでも従来の利用の中心であった伝統的温泉地の占めるウェイトが低下し、より自然に恵まれた地域の利用が増加する傾向にある。
物的豊かさの増大と都市化の進展の中で人々がより自然志向を強めている理由は主に次のようなものであろう。
第1は、日常生活空間での自然との分断である。既に述べたように、大都市中心部をはじめとして、都市において広範に起こっている自然と人間との分断は、必然的に人々に日常生活で果せない自然との接触を観光レクリエーションのなかに求めさせるようになったと思われる。
第2は、自然への認識の深まりである。高度経済成長期における公害の発生と自然改変の増大は、その反動として広範な環境保全の世論を呼び起こし、それによって人々は、自然の価値をより深く認識するとともに自然に対する様々な関心を強めている。
第3は、優れた自然への到着が容易になったことである。交通手段の発達、特に山岳観光道路に代表される自動車交通の山岳地での拡大は、従来潜在的なものであった奥地山岳地帯等の大自然への欲求を顕在化させたものと考えられる。
第4は、大型化、多様化したレクリエーション需要に対する自然公園等自然に恵まれた地域の優位性の発現である。交通機関の発達や所得水準の向上により大型化し、かつ国民の意識の変化により多様化した近年のレクリエーション需要に対応して、観光地には大きなスケールと多様な観光素材が要求されている。自然環境の保全されている地域は、このような要求に対応できる雄大かつ変化に富んだ景観や自然現象、様々なレクリエーション活動の対応する多様性を備えており、自然に恵まれた地域の観光地としての優位性は増大していると考えられる。
自然志向の増大は、また、同時により原生の状態に近い自然や自然とのより深い接触を求める傾向の強まりをもたらしている。1970年代には、「秘境ブーム」、「離島ブーム」などと称される手つかずの自然への一般大衆の接近意欲が顕在化したし、一方で単なる自然鑑賞から野鳥観察、キャンピング、オリエンテーリングなど更に深く、活動的に自然と接触しようとする活動の増大がみられた。
以上みてきたような国民の野外レクリエーション活動の動向は、今後とも国立公園などの優れた自然への国民のニーズが強まることを示しているが、このことは、同時に良質な自然環境の喪失につながる危険をはらんでいる。
観光レクリエーションとしての自然の利用に伴つて生ずる自然環境への影響は、利用のための施設の建設によるものと利用者によって直接もたらされるものの2つに分けられる。
自然公園などにおける観光レクリエーション施設の建設は、程度の差こそあれ自然環境、自然景観に影響を与えるものであるが、なかでも観光道路のような長大な工作物やスキー場、ゴルフ場のような広大な面積を必要とする施設の建設は、広範囲の森林伐採や地形の改変を伴い、その影響は大きいものがある。特に高地山岳地帯などの自然条件の厳しい地域では自然の復元力が弱くかつ、生態系が微妙なバランスの上に成り立っており、わずかの環境負荷でも大きな自然破壊が引き起こされる。このような地域では、直接的影響が大きくなるとともに、日照、水収支、通風などの環境条件の変化によって生態系が受ける二次的影響も大きい。
例えば、我が国における代表的な山岳観光道路の一つである富士スバルラインでは、道路建設によって生じた道路周辺の日照、通風、水収支などの二次的な環境変化により1万7,500本の樹木が枯損したとの報告がある。
利用者によってもたらされる自然への影響も、利用者の増大に伴い国立公園などの主要利用地域の多くで様々な問題を引き起こしている。その代表的なものが利用者によって廃棄される大量のごみ問題である。例えば毎年300万人にのぼる登山者が訪れる富士山では、登山者が捨てた空缶、空ビンが山腹一帯に大量に散乱し大きな問題となっている。そのため、54年度に環境庁及び山梨、静岡両県が中心となり、(財)クリーン・ジャパンセンターなどの協力も得て2万4,000人のボランティアを動員する大がかりな清掃活動(富士クリーン作戦)が行われたが、この時収集された空缶、空ビンは合計176万個にのぼった。このごみの問題のほか過剰な利用に伴う問題には、利用者の湿原、高山植物帯などへの踏み込みによる植生の破壊、大量のし尿や雑排水によっておこる水質汚濁、あるいは様々な発生源からの騒音などの問題があるが、いずれも利用者が自然に期待する美しさ、静けさを大きく損なうものであると言える。
これらの問題に対応するため、自然公園の様々な規制の強化や、利用者の集中する地区での清掃活動等への国庫補助制度の創設などの対策が講じられ、自動車道など大規模工作物による自然破壊は減少し、ごみ問題も改善の兆しがみられるが、今後とも自然環境と人間の接触に伴う自然への負荷、あるいは快適な利用の確保の問題は、自然への人々のニーズの強まりのなかで大きな問題となっていくものだろう。