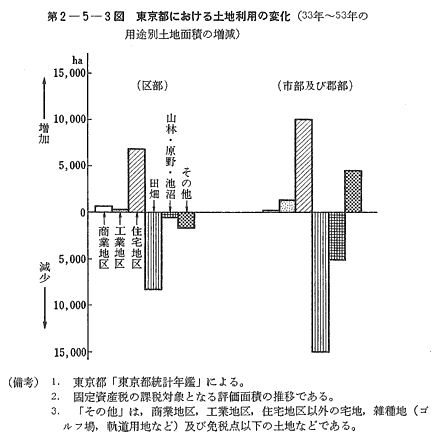
2 快適さへの欲求の強まり
第4節でみたように、我が国における都市化は急速に進み、過密化した都市構造の中で都市・生活型公害をもたらすと同時に、都市及び都市近郊において緑地や良好な水辺環境の喪失を引き起こしている。特に大都市圏域においては、大都市中心部のみならず、かつて都市の環境を支え、市民に豊かなレクリエーション空間を提供していた周辺農林水産業地域においても広範囲な市街化が進行し、都市住民が手軽に良好な自然の中で開放感にひたり、自然の潤いを求めることのできる空間が失われてきている(第2-5-3図)。
大都市圏域における都市化、工業化による水辺環境の変容は著しいものがある。環境庁が48年に行った「第1回自然環境保全基礎調査」の結果によれば、自然のままの海岸が残されている比率は、東京湾で9.9%、伊勢湾で12.1%大阪湾で11.5%となっている。53年に行われた「第2回自然環境保全基礎調査」における干潟の消滅状況の調査結果をみても、20年から53年までの間に東京湾、伊勢湾、大阪湾では、20年当時存在していた干潟のそれぞれ85.5%、60.8%、98.8%が埋立などにより消滅している。
このように海水浴、潮干狩などのレクリエーションや散策などの場となる海浜は大都市圏域で大幅に少くなって来ているのである。
かつて、経済の中心が農林水産業であり、自然が生活の中に溶け込んでいた時代には自然や歴史的環境が身近に豊富に存在していた。そのような状況の中で産業化が進展するに伴い人々は物的消費や利便の向上を求めて工業化、都市化を進めて来た。しかしこのような経済効率や利便を求める意識も、物的生活水準の上昇、自由時間の増大を背景として大きく変ってきている。公害の発生に触発され、人々の環境に対する意識は高まり、より良い環境の質を求めるようになってきている。
自然環境や歴史的環境が失われていく中で都市が肥大化してきたため、人々は環境の質として、澄んだ空気、静けさ、潤いのある水辺や緑、歴史的環境、落ち着いた街のたたずまいなどの快適な環境を求めている。
人々が居住している環境に何を求めているかをみるため、望ましい環境の構成要素を安全、衛生といった基礎的なものから利便、快適さとより選択的なものまで大きく四つに分けて、それぞれに対する満足度を意識調査(環境庁「望ましい環境に関する意識調査」)を行って調べた結果が第2-5-4図である。
調査を行なった8つの地域を大都市中心部、大都市近郊部、地方都市の3つの地域類型に分けてみると、利便が3類型のいずれでも満足度が最も高くなっており、大都市中心部で他の2つの地区にくらべて衛生の満足がより高く、快適さの満足はより低くなっているのが特徴的である。大都市中心部では、他の地域に比べ快適さについて満足とする回答の割合が2分の1以下、逆に不満とする回答の割合が3倍近くになっている。
4つの要素をあわせた居住環境の総合満足度は、大都市中心部で最も低くなっている。この総合満足度が人々の意識の中で4つの要素のうちどの要素に最も左右されるかを数量化分析で調べた結果によると、快適さに対する満足度が全体の総合満足度を左右する度合が一番高くなっている。
更に、この調査では、環境の快適さの構成要素を「空気のさわやか」、「静けさ」、「緑との触れ合い」、「水辺との触れ合い」、「町並みの美観」、「歴史的ふんい気」、「のびのび歩ける空間」、「レクリエーション施設」の8つに分けて、これらの快適さの日常生活空間における各構成要素ごとの満足度をみている。それによると、「水辺との触れあい」、「のびのび歩ける空間」、「レクリエーション施設」の不満が高くなってきている(第2-5-5図)。
また、「緑との触れ合い」については全体としては不満の割合は多くないものの、8要素のうちで最も地域による差が大きく、大都市中心部においては、台東区で59.6%、旭区で43.5%と極めて高い不満が示されている。