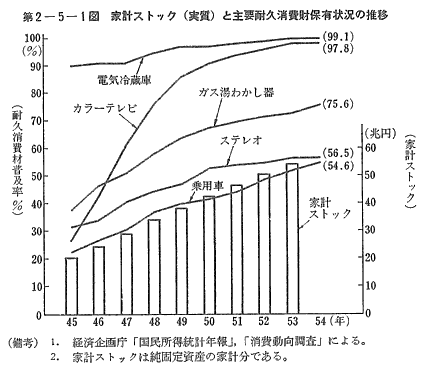
1 生活水準の向上
人々の生活水準の向上を民間最終消費支出の推移(実質)でみると、40年から53年にかけて、年平均7%を超える率で上昇し、53年には40年と比べて2.5倍の拡大を示している。
このような消費の伸びに支えられて、物的消費の豊かさは相当程度の水準に達した。家計の物的資材(家計ストック)の蓄積も、着実に進んできており、主要な耐久消費財の保有状況をみると電気冷蔵庫やカラーテレビなどの普及率は既に95%以上の水準であり、その他の耐久消費財の普及率も大幅に向上している(第2-5-1図)。
このような物的消費の向上を反映して、物の豊かさから質の豊かさへと国民の意識も変ってきている。45年に内閣総理大臣官房広報室が行った「国民生活に関する世論調査」の結果によれば、今後の生活の仕方についての問いに対して、「物質的にある程度豊かになったので、これからは心の豊かさやゆとりのある生活をすることに重きをおきたい」とする回答の割合(41%)が、「まだまだ物質的な面で生活を豊かにすることに重きをおきたい」とする回答の割合(40%)を上回る結果となっている。
また、生活の利便は、様々なサービス機能の拡大等により特に都市部において向上した。環境庁が54年に大都市圏及び地方圏の都市地域8地域(岩手県一関市、東京都台東区、東京都調布市、福井県武生市、静岡県掛川市、大阪市旭区、奈良県橿原市、岡山県津山市)で行った「望ましい環境に関する意識調査」によれば、「生活の便利さ」について満足とする回答が全体の68.9%を占めており、都市部において、生活の利便の満足度が相当程度高いことを示している。
国民の生活時間をみても、自由時間が大きく増大している。民間企業の週休二日制適用労働者数の割合をみると、何らかの形で週休二日制の適用を受ける労働者数の割合は、45年の17.9%から50年には69.9%へと大きく伸び、53年には72.2%の水準へと達している(第2-5-2図)。また勤労者の総実労働時間をみても45年から53年にかけて、1人1か月当たりの実労働時間は187.7時間から176.1時間へと11.6時間減少し、これに伴い勤労者の自由時間は増加してきている。