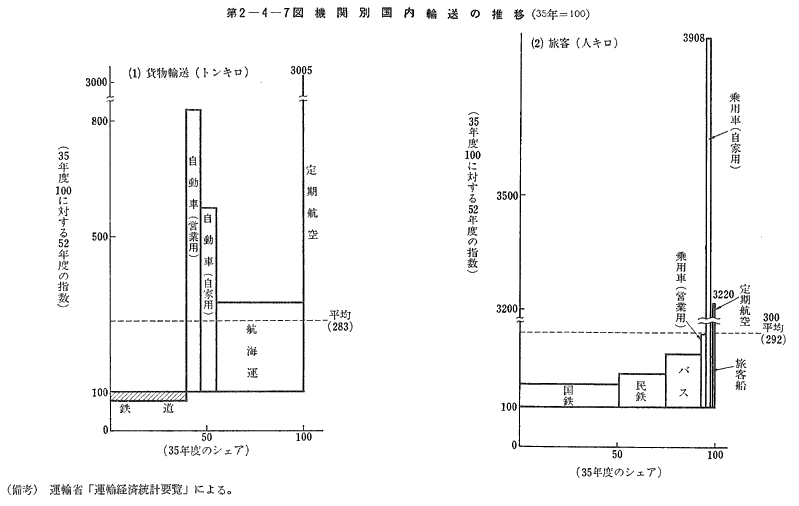
3 交通量の増大と都市の高密度化
(1) 交通量の増大
我が国では、都市における生活と事業活動により交通量は飛躍的に拡大してきた。またその中で輸送手段の構成も著しく変化し、貨物輸送においても旅客輸送においても自動車の比重が増大してきている(第2-4-7図)。
すなわち35年度と52年度の輸送分担率の推移をみると、貨物では鉄道が39.8%から10.7%とそのシェアを下げているのに対し、自動車は15.2%から37.0%と急速にそのシェアを高めており、旅客においても鉄道は75.8%から43.9%へ減少し、自動車は22.8%から51.9%へと増加している。
自動車輸送はシェア上昇とともに貨物車の大型化が進んでいる。これは後に述べるように自動車交通公害の要因となるものである。貨物自動車の輸送量を小型車と普通車に分けてみると40年度ではそれぞれ39.8%、60.2%であったが、52年度になると、21.0%、79.0%と小型車はその比率をほぼ1/2に下げており、普通車が輸送量の増加分のほとんどをひき受けそのシェアを高めてきている。
更に、自動車貨物発着状況を東京、神奈川、千葉の3都県についてみると、発数で全国の14.2%を占め、また、発数のうち同地域内へ着くもの、すなわち地域内貨物自動車交通は実に84.6%にのぼっている(52年度)。このことは全国的な交通網の発達によって、全国的な経済活動拠点であるこの地域に交通輸送の拠点が形成されてきているだけでなく、大都市圏内で発生する交通・輸送需要の増大に伴う負荷も極めて大きいことを示している。
新幹線鉄道による輸送量も急速に拡大してきた。40年度の1日平均輸送人員は8.5万人であったが52年度には34.7万人で4.1倍に増加しており、走行距離(車輌キロ)は1億8,029万kmから9億4,434万kmへと5.2倍になっている。また、航空機輸送の同期間の国内旅客数は、515万人から3,289万人へ6.4倍になっており、運行キロ数は2.7倍になっている。
(2) 都市の高密度化
我が国の人口は1平方キロメートル当たり約300人で世界で最も人口密度の高い国の一つに数えられているが、わずか2.2%の人口集中地区に全人口の57.0%(50年)が居住しており、この人口集中地区の人口密度は実に7,712人にのぼっている。
第2-4-8表は人口密度、公園面積について国際比較したものである。人口密度は1ha当たりで東京都区部が144.1人、大阪市が132.4人に対し、ロンドンは46.4人で約1/3である。一方1人当たり公園面積をみると、比較的広い名古屋の3.7?に対しフランクフルトでも3.5倍の13.1?の公園が設置されており、ストックホルムでは80.3?で21倍以上になっており、我が国の都市公園の貧困さを示している。
我が国の都市では、このような居住空間の高密度、貧困さの中でサービス経済を中心にした過密な社会経済活動が行われている。第2-4-9図は、都市における生活や経済活動の密度をみるために、個人消費、自動車登録台数、卸売販売額と小売販売額の4つの指標について、可住地面積当たりの密度をとって、東京都、愛知県、大阪府の地域密度指数(全国平均=1)を算出したものである。いずれの都府県とも全国平均を大幅に上回っており、特に東京都、大阪府の卸売販売額はそれぞれ32.2、17.8とその地域の人口シェアを上回った購買力を吸収しており、都市の商業活動に伴う負荷はその都市人口の集中の度合をはるかに上回る大きさになっていることを示している。
このような都市の高密度の商業活動は、更に大きな輸送需要を誘発し、人人の移動の増大が生み出す交通量の増大と重なって、交通・輸送による大きな負荷が発生することになる。
また、我が国の都市は、社会資本の整備や土地利用規制が急速な市街化に十分対応しきれなかったため市街地周辺農地の宅地化が進むとともに、工業や商業あるいは交通のための空間が細分化された宅地と混在し、一部土地利用が不適切なまま都市が肥大化したことが高密度な都市に発生する公害をより深刻なものとしている。