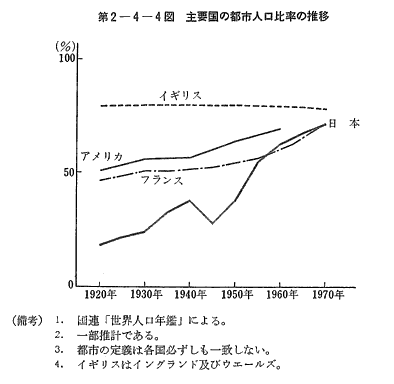
2 人口の都市集中と都市的生活様式の定着
(1) 都市への人口集中
1960年代の我が国の経済成長は欧米諸国の約2倍の速さであったが、人口の都市集中も主要国をはるかに上回る速度で進んできた(第2-4-4図)。この人口の都市集中は首都圏、近畿圏及び中部圏の3大都市圏で顕著で(第2-4-5表)、1960年代の全国の人口増加は、1,037万人であるが、その間の3大都市圏の人口増加は実に1,153万人にのぼり、全国の人口増加を上回っている。
しかし、1970年代に入ると3大都市圏への人口集中は依然進んでいるものの、その伸びは鈍化してきた。同じ3大都市圏でみても既成市街地及び近郊整備地帯の人口増加の伸び率はやや低下し、その周辺の都市開発区域での伸び率が高まってきている。
また、人口移動を都道府県別にみても、人口減少県の数は、35〜40年の25県から40〜45年では20県に減少し、さらに、45〜50年では5県となっている。このような動きを反映して地方圏の人口は35〜40年、40〜45年の間に減少を示しているが、45〜50年には増加に転じている。
このように、3大都市圏への人口集中が鈍化するとともに、地方における人口増加の傾向があらわれており、県庁所在市を含めた地方中核都市、中都市への人口集中が強まるなど、地方においても人口の都市集中が進んできている。
全国的な人口の都市集中は、今後とも進んでいくものと考えられる。「第三次全国総合開発計画」では40年48.1%、50年57.0%と上昇してきた全国の人口集中地区の人口の比率は、60年には64.6%、65年には67.3%に達するものと推計している。
(2) 都市的生活様式の定着
高度経済成長により国民所得は急速に増大し、またそれは所得の平準化を伴いながら国民の消費水準を拡大させた。
農家と都市家庭の間の所得格差も農家の農外所得の伸びを背景に解消し、消費水準も勤労者世帯(人口5万人以上都市)1人当たり消費支出を100とした場合、農家世帯の1人当たり消費水準は35年度49.9と市場への依存の低いものであったが、40年度63.8、45年度77.1、50年度94.9、53年度98.4と格差は縮小の一途をたどり、農家においても市場に依存した都市的消費が急速に浸透してきている。
このような中で教育水準の上昇、マスコミの発達などが進行したこともあり、生活意識の均一化したいわゆる中流階級が増加し、市場の豊かな供給に依存しながら物的豊さを追求するいわゆる都市的生活様式が全国的に定着してきた。すなわち均一化した中流階級においては、デモンストレーション効果が大きく、生活を豊かにし、家事の省力化を求める消費者の指向に応える、テレビ、冷蔵庫、クーラーなどの家庭電化製品や合成洗剤などの普及はめざましく、また大量流通の効率性がプラスチック、びん、かんなども大量に日常生活に送りこんできている。更に都市内、都市間の移動を容易にする自動車の普及もめざましいものがある。これらの商品は消費者のし好に合わせて市場が提供するものであるが、大量生産、大量消費のもとでは商品自体の陳腐化がはやいこともあって廃棄物の増加要因となっている。これらの廃棄物は自助努力により個々の家庭等で処理するのではなく公共サービスとして一括処理されることになっている。公共サービスとして行われている廃棄物処理事業においては、技術革新によって高度複雑化した商品は廃棄物になった時点で、高カロリー又は不燃のごみ、有害物質を出すごみとなり、処理したごみをどう処分するかという問題と並んでごみ処理の一つの大きな問題となってきた。
都市的生活様式の定着は、サービス経済の都市集中、都市人口の増加などとともに都市における水需要の大きな要因となっている。第2-4-6図は東京都区部における水道水使用量の推移であり、家庭用水が顕著な増加を示しているが、このような家庭用水需要の増大は、生活を豊かにした反面、同時に生活雑排水の増大につながっている。また、洗濯機の普及に結びついた合成洗剤の使用量の増大などがおこる一方、下水道等の整備がいまだ十分でないため生活雑排水が未処理のまま都市内中小河川に排出され、水質汚濁が助長されている。このようにして生活雑排水等の処理が十分でないため都市内中小河川が汚濁し、しかもそれが滞留する閉鎖性水域を中心とした湖沼、海域の有機汚濁、あるいは富栄養化の大きな要因となっている。更にし尿については、かつては農村還元されていたが、し尿に対する需要が激減したことと衛生面からの要請により水洗化が進められてきているが、水洗化は、都市的生活様式の定着とも一致している。下水道が未整備な地域においてはし尿浄化槽が設置されているが、その設置や維持管理が十分でない例もみられる。