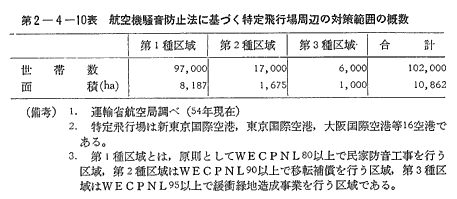
4 都市・生活型公害の増大
高密度な都市活動が生み出す環境負荷がどのようにして都市・生活型公害となって現れてきているかみていこう。今までみてきたように、都市化は、?都市への人口の集中と居住の過密化、?大量消費、都市内と都市間の自由な移動、交通機関の自由な選択、廃棄物や排水などの生活排出物の増大とそれを処理するための公共サービスへの依存などの都市的生活様式の定着、?物流、商業、都市内と都市間の交通網あるいは生活排出物の処理を行う公共サービスなど都市的生活様式を支える都市的サービス機能の拡大及び?事業活動を支える物流、中枢管理機能などのサービス経済の都市集中、といった特徴を持っている。このように経済と生活の両面において都市的諸機能の集積のメリットを最大に活かしながら都市化は進んできており、都市域における産業の活動も加わって、都市化は都市環境への過剰な負荷を生み都市・生活型公害をもたらしている。確かに、産業公害に対しては発生源対策を中心とする政策的対応手段が整備されてきたが、多数の汚染源が混乱した都市構造の中で複雑に組み合わされた都市・生活型公害については必ずしも十分対応が行われているとはいえない。
都市・生活型公害は発生源は個々には小さく、移動したり、広く分散したりしていて、発生源対策のみでは十分に対応しきれない場合が多く、都市的機能の利用を制限する必要がある場合がある。他方、汚染の発生者とその被害を受ける者がともに同じ都市的機能の利便を享受している場合が多く、都市的機能の公益性を損なわないようその利用に伴う環境負荷の増大を防止しなければならないという困難な対応が必要である。
(1) 交通公害
交通機関のもたらす大気汚染、騒音及び振動などの交通公害は都市・生活型公害の代表的な事例である。高度経済成長とともに交通量は急速に増加し、また、36年国内航空路線にジェット機就航、39年新幹線東京・大阪間開通、そして44年には東京・西宮間に高速道路開通など、交通手段も質的に大きく変化した。それにともなって交通公害は質的に変化してきている。
交通は建設資材、生活物質、廃棄物などの輸送や、通勤・通学、レジャー活動など人々の移動に広く貢献しており、都市的生活様式が求める大量の物流や利便、快適性を満たす上で不可欠なものとなっている。しかしそれが同時に、人々の日常の生活環境に大きな負荷を生んでおり、都市域、あるいは都市間での広範な交通公害を発生しており、今や社会問題の一つとなっている。
? 自動車交通公害
交通公害のうち、もっとも広範に発生しているものは自動車交通公害である。
自動車交通量の増加は種々の問題を発生させるが、特に、騒音・振動と排出ガスによる大気汚染が道路周辺においては深刻な問題となっている。
自動車騒音については「公害対策基本法」に基づき「騒音に係る環境基準」が設けられるとともに「騒音規制法」により個々の自動車に対し、騒音の大きさに係る許容限度が排気騒音、加速走行騒音、定常走行騒音についてそれぞれ設定され、また影響の大きい大型車などの加速騒音に対しては規制の強化が図られてきた。
しかし、環境庁が行っている沿道における自動車騒音実態調査(53年、全国3,315測定点)によると、環境基準を満足する地点は朝方35.5%、昼間30.7%、夕方29.3%、夜間46.6%であり、すべての時間帯で環境基準を満たす地点はわずか17.0%にすぎない。また、要請限度(騒音規制法第17条)を超えている地点は22.5%にのぼっている。
自動車の排出ガスについても、一酸化炭素、炭化水素、窒素酸化物及び粒子状物質について規制が行われている。41年から、一酸化炭素濃度規制が行政指導により行われたが、その後規制の強化、範囲の拡大が図られてきた。その結果を一酸化炭素濃度についてみると、44年をピークに改善にむかっている。東京都内3ヵ所の国設自動車排出ガス測定所では35年の4.1ppm(3か所平均)が、44年に6.4ppmまで増加したが、その後減少に転じ、50年には2.9ppm、53年には2.3ppmと最高時の半分以下に低下している。
一方、窒素酸化物は、全国的には、固定発生源である産業による排出の比率が大きいが、サービス機能の集中が進んでいる都市部では、自動車交通により排出されるものの比率が高まっている。自動車交通量の増加とともに沿道における二酸化窒素濃度は年々高まっており、自動車排出ガスを継続して測定している東京都内10局の測定結果をみても、46年度の0.026ppm(全国の継続26測定局の平均は0.032ppm)がその後すう勢的に悪化し、53年度では、0.044ppm(同0.042ppm)に達している。
? 新幹線鉄道騒音・振動
長距離都市間移動における高速性、快適性、経済性を飛躍的に高めたのが新幹線の開通であった。しかし、新幹線鉄道の列車の走行に伴い発生する騒音・振動は著しく、沿線の一部の地区においては、環境保全上深刻な問題となった。これに対処するため、50年に「新幹線鉄道騒音に係る環境基準」が告示され、51年に「新幹線鉄道対策要網」が閣議了解され、更に「環境保全上緊急を要する新幹線鉄道振動対策」について勧告が行われたが、それを受けて同年国鉄は、「新幹線鉄道騒音・振動対策処理要網」を策定した。
これらの施策に基づき騒音対策のための技術の開発に努めるとともに国鉄は53年度末までに防音壁設置494km(上り、下りの合計)、防音工事実施1万1,464戸、移転426戸などの対策をとってきた。騒音とともに新幹線の振動の一部の沿線の地区で大きな被害を生じている状況から、51年、環境庁長官は運輸大臣に振動レベルが70dBを超える地域については、緊急に振動源及び障害防止対策等を講ずることを内容とする勧告を行った。国鉄においては、防振技術の開発に努めるとともにレールの重量化、バラストマット敷設等の対策を行っている。
? 航空機騒音
経済活動の高度化、所得の上昇、国際交流の活性化は航空輸送に対する需要を高め、航空輸送の飛躍的増大をもたらした。人キロでみると航空の伸び率は極めて高く、45年度を100とした場合53年度では289と自動車輸送の伸び率の142、そのうちの伸びの高い乗用車の163もはるかに上回っている。このような航空輸送需要の増大に伴い航空機のジェット化、大型化が進展する一方、空港周辺地域においては次第に都市化が進んできた結果、周辺における航空機騒音問題が急速に拡大してきた。そのため、「公害対策基本法」の制定(42年)に先だって41年には「防衛施設周辺の整備等に関する法律」が、翌42年には「公共飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律」(航空機騒音防止法)が制定された。その後49年には騒音対策の拡大を図るためこれらの法律の改正を行い、また53年には騒音による障害の防止を図るとともに合理的土地利用を図ることを目的として「特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法」が制定されるなど騒音対策は充実されてきている。
第2-4-10表は、「航空機騒音防止法」に基づく対策の実施される16の特定飛行場周辺の区域指定及びその区域内の世帯数であり、全国で世帯数にして約10万世帯、面積1万862ha、となっている。特に、大阪国際空港をみると、第1から第3種合計で5万9,000世帯2,225haとなっており、世帯数では、全空港約10万世帯の過半数を占めている。
(2) 近隣騒音
公害等調整委員会の調べによると53年度の公害苦情6万9,730件のうち、騒音に関するものは、2万9,305件で30.6%を占めている。騒音苦情件数のうち、製造事業所を発生源とするものが37.3%を占めており、商店、飲食店、家庭生活、娯楽・遊興・スポーツ施設を発生源とする近隣騒音は、合計で23.4%となっている。これら近隣騒音は、身体、財産に直接被害を与えることがほとんどないこと及び隣近所への気兼ねから苦情が潜在化している事例も少なくないものと推定される。
環境庁は、全国の環境モニターを対象に近隣騒音に関する調査を行ったが、ここ1年程の間に近隣騒音により迷惑を受けたことがある人は56.0%にのぼっている。人口規模別にみると人口の多い市、区に住んでいる人に訴えが多く、また地域別にみると、商業地域、住居・商業混合地域での比率が高くなっている。種類別にみると、?近所の自動車の空吹かし音など、?チリ紙交換等のスピーカー音、?ペットの鳴き声、?テレビ、ステレオの音、?隣人の声、?クーラーの音など多種多様な近隣騒音があげられており、発生源は多様である。また騒音を受けている人々の居住地域の状態も千差万別である。過密な都市の居住構造に加え、住宅の材質、構造、利用している機器の特性やその利用の仕方、騒音を生んでいるサービス活動のあり方など、多様な要因が高密度な騒音空間を生み出していると考えられる。
より良い環境を求める意識がさらに強まれば、近隣騒音をめぐるトラブルは今後さらに増大するものと推測される。しかし、近隣騒音問題が顕在化してきている背景には都市における対話やコミュニティ意識の欠如による面が大きいと思われ、都市生活におけるルールづくりが必要になってきている。
(3) 水質汚濁
1970年代を通じ、水銀などの人の健康に係る有害な物質による水質汚濁の状況は著しく改善した。しかし、有機物など生活環境に係る項目についてはその改善が必ずしも十分とはいえない状況にある。これは、事業場などからの排水については、「水質汚濁防止法」などに基づく濃度規制により徐々に改善してきたが、家庭からの生活排水については、人口の急速な都市集中が進み、都市的生活様式が定着するとともに水質に対する負荷が増大してきており、このような急速な都市化による生活排水の量の増大及び下水道などの整備が十分でないこともあって、全体の水質汚濁負荷量に占める割合が大きくなってきている。
瀬戸内海におけるCOD汚濁負荷の総量とその発生源別ウェイトを推計したところ、51年度で総量は1,360トン/日にのぼり、そのうち生活排水によるものが43%を占めている(産業排水49%)。瀬戸内海と同様に総量規制が導入される伊勢湾、東京湾についても生活排水の負荷量総量に対する比率を推計すると、伊勢湾では450トン中43%(産業排水は47%)と同様に高い比率を示しており、東京湾では700トン中62%(産業排水は26%)と生活排水が産業排水を大幅に上回っている。
また、窒素、リンなどの栄養塩類による富栄養化については、生活、産業などの排水から多量の窒素、リンなどの栄養塩類が水系を通して湖沼、内湾などに流入し、そこで植物プランクトンなどの藻類が繁殖し、水質を悪化させている状況が近年多くみられる。
富栄養化の原因となる栄養塩類については瀬戸内海において「瀬戸内海環境保全特別措置法」に基づくリン削減対策が実施されることになっている。リンの発生源を琵琶湖についてみれば、家庭からのものが48.0%(工場からのものは29.3%)また、瀬戸内海についてみれば、生活系が41.9%(産業系は40.6%)と推定されるように、産業排水による負荷と並んで生活排水による負荷が大きな比重を占めている。また閉鎖性水域を中心に赤潮が発生している。赤潮については、定性的には日照、降雨に関係し、窒素、リン、微量物質などにより発生するとされているが、その発生機構について解明が十分でなく、現在、その解明に全力をあげているところである。
このような閉鎖性水域を中心とした水質汚濁は、近年各種の被害を引き起こしている。自然環境の観点から水が着色して外観を損ね、レクリエーション、観光的価値を損ねたりしている水域も多い。また、上水道用水として利用する場合には、水質の悪化により、浄水場のろ過障害、飲料水の異臭味等の障害がみられる。最も被害金額の大きい被害は、漁業被害であり、52年度では総額で78億円の被害が出ているが、そのうちの約70%は赤潮による被害となっている。
(4) 一般廃棄物
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」では、廃棄物を「ごみ、粗大ゴミ、燃えがら、汚でい、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固型状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染されたものを除く。)」と定義している。廃棄物をその発生源で大きく分類すると事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃えがら、汚でい、廃油、廃液等「産業廃棄物」とそれ以外の「一般廃棄物」とに分類される。
一般廃棄物のうちごみは、所得の増加、都市的生活様式の定着に伴い年々増加してきている。また、し尿についても、都市での人口増加によりその量は増加してきている。
一般廃棄物の処理については市町村が、処理計画を策定し、それに従った処理を行っているが、これについては処理困難なものが増加しており、量の問題とともに質的な面での処理の困難さが加わっている。
? ごみ
所得が上昇する中で、大量消費が一般化し、それに伴ってごみも増加してきている。
第2-4-11図のように東京都区部のごみ収集量の合計は高度経済成長期の45年度から48年度のかけては年平均9.5%で増加したが、第1次石油危機後の低成長下の48年度から53年度にかけてはその伸び率が1.8%に低下している。しかし、安定成長下においても今後とも一定の増加がみこまれる。
東京都区部における常住人口は44年の8,888千人から漸減傾向にあるが、第3次産業や中枢管理業務などサービス機能が集中を高めているため非居住昼間人口は増加しており、その中で量的な増大とともに紙類、プラスチックなど高カロリーの廃棄物、金属、ガラスなどの不燃物が増加していることがあげられる。
更に東京都区部においては、全国の0.2%という狭い地域にその15.6%(52年度)という多量のごみが排出されることがごみ問題を深刻化させているが、これは東京都区部のみの問題ではなく、人口の集中している都市の共通の問題でもある。しかも大量のごみを過密な都市で収集し、焼却、埋立を行わなければならないため、これらの収集、焼却、埋立などが適切な組み合わせと配置でなされない場合、取り残し、不法投棄、悪臭、大気汚染など、ごみの収集と処理自体が生活環境の悪化、公害現象をまねくことになる。
また、ごみ処理のためのコストは年々高くなってきており、東京都区部におけるごみ処理の原価は、42年度のトン当たり5,208円から51年度には1万9,095円と3.7倍になっている。
? し尿
公衆衛生面からも、環境保全面からも都市におけるし尿処理は地方公共団体にとって重要な問題となっている。
し尿処理の方法としては、?水洗便所から公共下水道への排出、?し尿浄化槽による生物化学的処理、?くみ取り後下水道投入やし尿処理施設での処理、?農村還元や?海洋投入などがある。このうち?についてはし尿が肥料として使われなくなり、?については海洋汚濁防止などの理由により次第に困難になってきている。現在公共下水道を中心に整備が図られているが、第2-4-12図は東京都における下水道への汚水排出量をみたものである。し尿のみでなく、家庭排水等も含まれているが、その量は年々増加しており、区部では年率4.9%、47年度より使用開始された武蔵野市などを対象とした野川処理区では毎年30%近い伸びを示している。しかし、全体としてみると、日本下水道の普及率はいまだ低く、イギリスの94%、西ドイツ79%、アメリカの71%など(いずれも1975年)に対して27%(1978年)にとどまっている。また必要性の高い都市部においても東京都区部68%、名古屋市73%、大阪市96%(いずれも52年度末人口比)を除きその普及率は高いとはいえない。