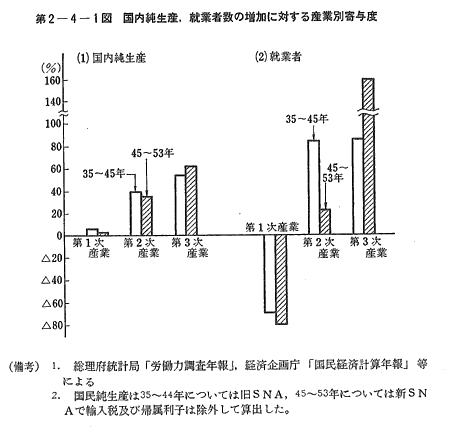
1 都市のサービス経済化
1960年代の高度経済成長期には、第3次産業と並んで重化学工業化を伴った製造業の拡大が大きな雇用吸収力を発揮した。1970年代には、安定成長への移行期に入り、製造業の雇用吸収力は低下したが、第3次産業の雇用は著しい伸びを示している。
第2-4-1図は国内純生産の増加における産業別寄与度と就業者の増加に占める産業別寄与度の変化を1960年代と1970年代(1970〜1978年)についてみたものであるが、1970年代に入ると生産、雇用の両面にわたり、第2次産業の寄与度が低下しているのに対し、第3次産業の寄与度は上昇しており、特に第2次産業と第3次産業の雇用面での寄与度の変化の差は極めて大きくなっている。
このような第3次産業の拡大は都市において顕著である。第2-4-2図は東京都区部における35年から50年までの就業構造の推移と、50年における県庁所在市と政令指定都市の就業構造を全国と比較したものである。東京都区部の第3次産業就業者のウェイトは35年以降一貫して上昇してきており、50年では、全国平均の51.6%に対し、65.0%と高く、また同様の傾向は県庁所在市、政令指定都市でも顕著である。
更に、都市における経済活動の拡大の特徴をみるため、東京都における35年度から51年度までの業種別の純生産の伸びをみたのが第2-4-3図である。35年度に対する51年度の都内純生産は約11倍になっているが、農林水産業、鉱業、製造業はそれぞれ3.8倍、3.8倍、7.2倍と平均を下回っている。一方、卸・小売業、サービス業など、第3次産業を構成する業種は、いずれも平均を上回る伸びを示しており、純生産の面からみても都市において第3次産業の構成が高まっていることがわかる。
第3次産業の都市集中と並んで、中枢管理機能の都市集中も極めて高くなっている。3大都市圏における中枢管理機能の集中の実態を本社、本店の立地状況(52年現在)でみると、3大都市圏には全国の72.2%(首都圏41.9%、近畿圏17.5%、中部圏15.0%、福井、滋賀、三重の3県は近畿圏、中部圏において重複している。)が集中し、更に資本金50億円以上の大企業についてみると、首都圏63.1%、近畿圏21.8%、中部圏6.9%、3大都市圏合計では、91.3%と極めて高い集中を示している。
また、学術・研究の中心である大学の大都市への集中も著しく、53年5月現在の調べでは全国の大学・短大の952校のうち3大都市圏では628校、66.0%となっている。金融、保険、証券、卸・小売業、出版、マスコミ、サービス業などの第3次産業とともに中枢管理機能、学術・研究などのサービス機能の都市への集中度は極めて高く、都市のサービス経済化は顕著な傾向となっている。