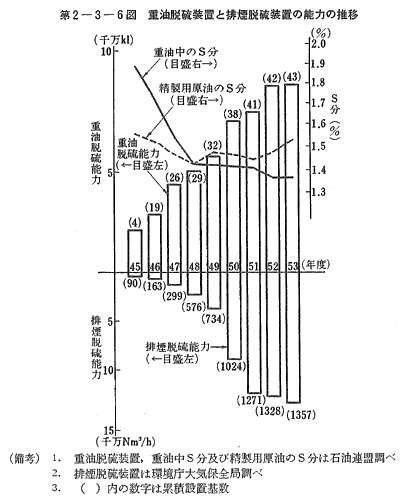
2 公害防止の進展と安定成長への移行
(1) 産業公害防止施策
高度経済成長の過程で生じた産業公害の進行を背景として、我が国の環境行政は、このような事態に対処すべく、42年には「公害対策基本法」が制定され、同法を軸として我が国の環境政策は急速に進展することとなった。
「公害対策基本法」は、公害の防止に対する事業者、国、地方公共団体の責務を明らかにした上で、大気の汚染、水質の汚濁及び騒音について環境基準を設定するとともに、公害の著しい地域または著しくなるおそれのある地域について公害防止計画を定め、環境行政を総合的、計画的に進めることとした。
更に同法を受けて43年には「大気汚染防止法」、45年には「水質汚濁防止法」等の制定が行われ、産業公害防止のための体制が確立されていった。このような各種法体系の整備に伴い、個別排出規制の強化・拡充が実施されることとなった。すなわち、硫黄酸化物については「大気汚染防止法」に基づき、ばい煙発生施設ごとのK値規制が導入され、43年12月の第1次規制以来51年9月の第8次規制まで段階的に改定強化が行われた。また、窒素酸化物についても48年8月に排出基準が設定されて以来、54年8月の第4次規制に至るまで強化・拡充が行われている。また公共用水域の水質保全のため、「水質汚濁防止法」に基づき規制業種の拡大が行われるとともに、都道府県による上乗せ排水基準の設定も行われている。
更に硫黄酸化物について、ばい煙発生施設ごとの排出基準のみによっては環境基準を確保することが困難である地域に対し、総量規制が導入されるとともに、水質汚濁の著しい広域的な閉鎖性水域について総量規制が導入された。
(2) 事業者による公害防止措置
? 公害防止技術
環境基準の設定、排出規制の強化・拡充など公害防止施策が整備されてしたことに対応して、事業者においても公害防止技術の開発・導入、公害防止施設の設置など積極的な対応が進められることとなった。
硫黄酸化物による大気汚染防止のために、燃料である輸入原油に含まれる硫黄分を除去する重油脱硫技術と燃焼後の排ガスの中から硫黄酸化物を除去する排煙脱硫技術の開発を中心として公害防止技術の開発、向上が進められた。重油脱硫装置については42年に設置が開始され、53年には内需用重油の68%に当る8,129万klの重油の脱硫処理が行われることとなっている。このような重油脱硫装置の普及の結果、輸入段階で公害に対する配慮から低硫黄原油の輸入が増大したことも手伝って、重油中に含まれる硫黄分は48年までは大きく低下した。その後、精製用原油の硫黄分が上昇に転じたが、重油脱硫技術によってこれを相殺し、燃料重油中の硫黄分は緩やかに低下している。
また、排煙脱硫装置については、41年から通商産業省による大型工業技術研究開発テーマとして研究開発が進められ、45年には電力会社において実用装置が稼動を始めている。それ以降設置基数及び処理能力とも急速に増大しており、45年度の90基、500万Nm
3
/hから53年度には1,357基1億3,382万Nm
3
/hとなっている。
大気汚染をもたらす窒素酸化物の防止技術としては排煙脱硝技術と低NOx燃焼技術を中心に技術開発が進められている。
排煙脱硝技術の開発状況はLNGなどの燃焼に伴うダストの少ない、いわゆるクリーン排ガスについては、50年時点で実用化が行われるとともに、重油燃焼に伴う排ガス程度のダーティ排ガスについても52年時点で技術開発は実用化の域に達しつつあるとされ、技術の信頼性の向上などが図られている。また、石炭燃焼に伴うようなダーティな排ガスについても実用化が進められるとともに、パイロット・プラントテストの成果が蓄積されてきている。
また、低NOx燃焼技術の開発は、低NOxバーナー、二段燃焼、排ガス再循環など多くの技術開発が進められ、ボイラーをはじめ金属加熱炉、石油加熱炉などに広く実用化されてきている。
次に、水質汚濁防止技術についてみると、COD、BODなどの水質指標改善のため、有機物汚濁防止技術としては活性汚泥法、凝集沈澱法などの利用が早くから進められ、産業排水の高次処理が行われている。しかし水質富栄養化防止のための脱リン、脱窒技術の開発はまだ解決すべき多くの問題が残されている。また、生産工程の変更の一例として、か性ソーダの製法転換があり、従来の水銀法からイオン交換膜法等への製法転換が進められている。
更に現在、生産設備での排熱、排ガス利用、廃棄物の再利用などの省資源・省エネルギー、の技術開発・利用が行われている。これらの企業努力は環境質を改善する効果を持つといえよう。
? 公害防止投資
以上のような公害防止技術の開発実用化に伴い、1970年代前半に公害への企業の対応が急速に進んだことを反映して民間企業における公害防止投資は大幅に増加を続けた。第2-3-8図は通商産業省が調査している資本金1億円以上の民間企業について公害防止投資の推移をみたものであるが、公害防止投資は45年度の1,883億円から50年度にはその約5倍に当たる9,645億円にまで拡大している。また公害防止投資の全設備投資に占める比率(公害防止投資比率)も45年度の5.3%から50年度には17.7%へと急速に上昇している。
その後公害防止投資は減少してきているが、これは既設生産設備に対する公害防止投資がほぼ一巡したとみられること、また、石油危機以降の景気の低滞から設備投資全般が低滞し、それに伴って新規設備投資に対する公害防止投資も減少したことによるものとみられる。今後は設備投資の増加とともに公害防止投資も増加するものとみられる。
また、公害防止投資を業種別にみたのが第2-3-9図である。これは、前記調査が始められた40年度から54年度までの公害防止投資額の累積を示したものであるが、これによると全業種では約5兆3千億円の投資が行われ、業種別には火力発電と鋼鉄で半分を占め、次いで石油、化学(石油化学を除く)の順となっている。
また、公害防止投資の推移を防止施設の種類別にみると、大気汚染防止施設が過半を占め、水質汚濁防止施設が10〜20%台となっている。これは、重油脱硫装置、排煙脱硫装置、排煙脱硝装置などの大気汚染防止技術の向上にともなって火力発電、鉄鋼、石油精製などを中心に積極的に公害防止のための設備投資を行ってきたためとみられる(第2-3-10図)。
(3) 地方分散
これまでみたように、1960年代における高度経済成長の下で我が国において太平洋ベルト地帯を中心に高密度な生産活動が行われ、これらの地域に環境負荷が集中し産業公害が発生したが、1970年代に入り、生産の地方への分散化の傾向が現れている。
第2-3-11図は、45年以降の太平洋ベルト地帯における工業製品出荷額の全国に占めるシェアをみたものもあるが、同地域の出荷額のシェアは緩やかではあるが低下傾向にあり、53年には45年の67.8%から62.8%へと低下している。
また、工業用地面積の推移でみても、45年から51年までの間に、全国で約1万7,000ha増加したが、東京都、神奈川県、愛知県、大阪府、兵庫県では、3万3,554haから3万3,751haへとわずか197haの増加にすぎず、東京都と大阪府のみをとると、1万0,069haから8,939haへと逆に1,130ha減少している。このことは太平洋ベルト地帯の中核となる地域で分散化が強く出ていることを示している。
このような分散化の背景には、工業再配置政策などにより地方における生産基盤の整備が進むとともに、大都市における過密化が激しく、地価の上昇、交通の混雑による輸送コストの増大等過密化による不利益が増大していることと同時に公害苦情件数の増大、公害防止施策の進展による規制の強化により、施設の増設や立地が困難になっていることがあるとみられる。環境庁と中小企業庁が53年度に実施した「中小企業公害防止投資動向調査」によると、公害苦情への対応策として防止施設の設置(71%)、燃料転換(12%)に次いで、工場の移転(9%)を上げている(複数回答)。
工業立地の分散化当たっては地域の環境保全に十分配慮する必要があるが、立地の分散化は環境負荷の地域的な集中に伴う解決の困難さや汚染防止費用の増大を回避することができるという大きなメリットがある。「第三次全国総合開発計画」においても、工業立地の規制、誘導を図るため、東京圏、大阪圏における工業開発を抑制し、北海道、東北、九州などの地域における工業開発を促進することとしている。
(4) 安定成長への移行と省エネルギー
1970年代に入り、経済活動をめぐる情勢は大きく変化することとなった。それは高度経済成長を支えていた石油の価格が48年末の石油危機を契機として大幅な上昇示をしたことである。
この石油価格の高騰を契機として、我が国の経済成長率は急激に鈍化するとともに、鉱工業部門における生産は停滞を続けることとなった。第2-3-12図は48年度以降の国民総生産、鉱工業生産指数及び石油消費の推移を示したものであるが、53年度の実質国民総生産は48年度の水準を約22%上回っているのに対し、鉱工業生産指数は49年度、50年度と大きく落ち込んだあと、53年度になってようやく48年度の水準を約5%上回る程度に回復したに過ぎない。
他方、鉱工業部門における石油需要は、鉱工業生産が53年度には48年度の水準まで回復しているのに対し、53年度においても48年度のピークをなお下回っている。これは、鉱工業部門において石油危機以降石油価格の高騰に伴って省エネルギー努力がかなり進展していることを示している。
このような省エネルギーを通じて、それまで大気、水質などへの環境負荷の増大をもたらしていた産業構造にも変化が現れてきている。
第2-3-13図によって石油危機以降の生産の回復状況を主な業種についてみると、53年度の鉱工業生産指数は48年度の水準を5.6%上回り、わずかではあるが回復を示しているのに対し、鋼鉄は5.9%、窯業・土石は4.0%、石油・石炭製品は2.9%といずれも48年度の水準を下回っており、大気に対する環境負荷を軽減する要因となっている。一方、水質に対する環境負荷は、食料品が48年度に比べ53年度は9.4%増と鉱工業全体の平均をわずかに上回る伸びを示しているが、紙・パルプが0.3%増と48年度とほとんど同水準の生産にとどまっていることから全体としては負荷の増加傾向は鈍化してきている。