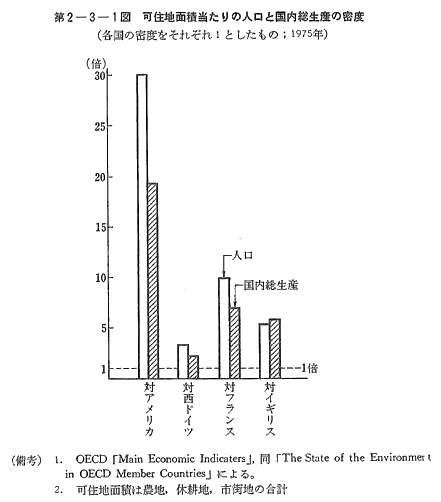
1 高度経済成長と環境負荷
(1) 産業構造の高度化
我が国の鉱工業生産は1960年代の高度経済成長の下で、主要先進国の鉱工業生産を上回る急速な増大を示した。OECD(経済協力開発機構)加盟諸国の1960年から1969年までの鉱工業生産の年平均増加率が6.0%であったのに対し、我が国の同期間における生産の伸びは13.7%と2倍以上の伸びを示している。また、アメリカ、西ドイツと比べても、我が国の生産の伸びはアメリカの約2.6倍、西ドイツの約2.4倍というように他に例を見ない急速なものであった。
一方、我が国は、国土が狭隘で、特に国土面積全体から森林、原野、湖沼を除いた可住地面積は国土全体の約33%にすぎない。そこに人口、産業の著しい集中が行われており、しかも、我が国においてはアメリカに次ぐ自由世界第2位の生産が行われているため、極めて高密度な状態となっている。第2-3-1図は、我が国の人口と経済活動の実質的な密度をみるために可住地面積当たりの人口と国内総生産を主要先進国と比較したものである。可住地面積についてはOECDの資料を用いたが、国により可住地面積の定義が異なるため、正確な比較は困難であるが、我が国の密度の高さは理解できるであろう。これによると1975年における我が国の可住地面積当たりの国内総生産は、アメリカの約19倍、またフランスの約7倍、イギリスの約6倍、そして西ドイツの約2倍の規模となっている。
このような我が国の急速な鉱工業生産の拡大が、環境に対してどのような負荷の増加をもたらしたのか、大気と水質に対する負荷を中心にみてみよう。
1960年代を通じて鉱工業生産の規模は約3.5倍に拡大したが、石油消費量は約5.9倍と、我が国経済の拡大は石油消費の急速な拡大によって支えられてきた。第2-3-2図は一次エネルギー供給量の推移をみたものであるが、エネルギー供給の増大のほとんどが石油の供給によるものであったことを示している。
このような生産の拡大に伴う石油消費量の増加は、公害防止措置が講じられなければその燃焼を通じて大気に対する負荷を増加させる要因の一つになるが、当然のことながら個々の産業により、その大きさは異なっている。1960年代における石油消費量及び生産額単位当たりの石油消費量によって大気への環境負荷の大きさを業種ごとにみると、電力、鉄鋼、石油製品、化学などの業種の値が相対的に大きく、1960年代のおいて、大気に対する負荷を高める要因となったと考えられる。
また、水質の有機汚濁の代表的な指標であるCODの生産額単位当たりの排出量によって水質に対する環境負荷の大きさをみると、紙・パルプ、食料品などの業種の値が相対的に大きく1960年代において水質に対する負荷を高める要因となった考えられる。
1960年代における鉱工業生産増大のいわばリーディング・インダストリーは、鉄鋼、非鉄金属、金属・機械、化学、石油、石炭製品などの重化学工業部門であり、この期間に我が国の産業構造は軽工業から重化学工業へと大きくシフトしている。第2-3-3図は、1960年代における主な産業の生産増加率(年平均)をアメリカ、西ドイツと比較したものであるが、重化学工業部門の生産は、いずれも高い伸びを示したことがわかる。鉄鋼が4倍以上、金属・機械が3倍以上、非鉄金属、化学・石油・石炭製品が約2倍と重化学工業部門ほど総じて高い伸びを示している。このような我が国の産業構造の高度化は、石油消費の増大を通じて大気に対する負荷を増大させる要因となったと考えられる。
一方、紙・パルプ、食料品は、鉱工業生産平均増加率に比べ低い伸びとなっているが、それでもアメリカ、西ドイツの約2倍の伸びを示しており、水質に対する環境負荷が我が国において大きくなった一つの要因といえよう。
(2) 生産活動の高密度化
1960年代における鉱工業生産活動に伴う環境負荷の増加は、工場、人口の集中した地域において環境汚染を引き起こすこととなった。
1960年代の我が国においては、鉱工業生産は主としていわゆる太平洋ベルト地帯で行われていた。同地域の可住地面積は国土全体の可住地面積の約21%に過ぎないが、工業製品の出荷額では、45年において全国の約68%を占めていた。その結果、太平洋ベルト地帯の可住地面積単位当たりの出荷額は、同地域以外の出荷額の約8倍と高密度な生産活動が行われていたことになる。
また、太平洋ベルト地帯における主な産業の全国に占める出荷額のシェアをみても(第2-3-4図)、鉄鋼、石油・石炭製品、化学、火力発電などの産業が特に同地域に集中していたことがわかる。一方、食料品、紙、パルプは、比較的太平洋ベルト地帯への集中の程度は低いが、それでも50%を越える集中を示しており、同地域においては大気、水質など環境への負荷が高くなっていたことを示している。
これまでみてきたような鉱工業生産の拡大、重化学工業を中心とした産業構造、そして生産の地域的な集中などを背景として、1960年代においては公害問題の激化、自然環境の改変が生じることとなった。
まず大気汚染については、二酸化硫黄の濃度(年平均値の15局平均)が42年には0.059ppmにまで上昇するなど硫黄酸化物を主とする大気汚染が激化し、四日市、川崎などの工業地帯を中心に健康被害が発生した。二酸化窒素の濃度も生産や交通量の増大などにより上昇傾向で推移した。また、45年には、窒素酸化物や炭化水素を原因物質とする光化学大気汚染も生じ、それによるとみられる被害が生じることになった。
また、水質汚濁についても、カドミウム、水銀など有害物質による健康被害が発生し大きな社会問題となるとともに、都市河川及び水の交換が限られている閉鎖性水域を中心に有機物、栄養塩類による水質の悪化が進んだ。
更に工場など事業場からの騒音、振動、悪臭に対する苦情件数も大幅に増大し、これらの汚染因子も加わって産業公害は大きな社会問題の一つとなった。
工場などの生産基盤の整備を進める上で、工場用地の確保が不可欠の条件となるが、1960年代においては、多くの干潟が工業用地となって消滅していった。第2-3-5図は、戦後の干潟の消滅の推移と消滅干潟の利用状況を太平洋ベルト地帯の中核である東京湾についてみたものである。昭和20年代においては約9,800haの干潟が存在していたが、35年から45年にかけてその約4割に当たる4,300haが消滅していった。そして、その利用状況をみると工場用地が大部分を占め、次いで市街地が大きな割合を占めており、高度経済成長期において自然の改変が進んだことを示している。