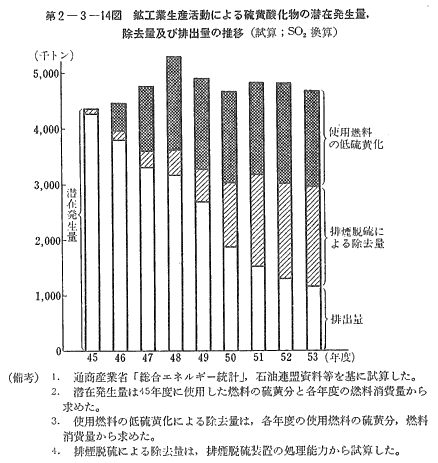
3 環境負荷の変化
(1) 環境負荷の軽減
公害対策の進展による産業公害に対する規制の強化・拡充、それに対応した事業者の公害防止努力と並んで石油危機以降の生産活動とエネルギー消費の停滞は環境に対する負荷にどのような影響を及ぼしたであろうか。代表的な大気汚染因子である硫黄酸化物、窒素酸化物及び代表的な水質汚濁の指標であるCODについて負荷量が1970年代に入り、どのように変化したかをみることにしよう。
? 硫黄酸化物
第2-3-14図は、鉱工業生産活動に伴う硫黄酸化物の潜在発生量、除去量及び排出量を石油、石炭の消費量とそれらに含まれる硫黄分などを基に試算したものである。この試算によると燃焼となる石油などの消費量の増大により潜在発生量は48年度までは増加する傾向にあったが、49年度、50年度と鉱工業生産の停滞などにより石油消費が減少したことから減少し、その後もほぼ横這いで推移しているものとみられる。
一方、除去量は、排出規制の強化・拡充に伴う低硫黄原油輸入の増加による輸入効果と重油脱硫装置の普及による燃焼中硫黄分低下による重油脱硫効果、そして排煙脱硫装置普及による排煙脱硫効果が働いて増加を続けている。
このような潜在発生量の伸びの鈍化と除去量の増加により大気中に排出される硫黄酸化物の排出量は45年度以降着実に減少を続けている。
硫黄酸化物の排出量の推移を業種別にみると、45年度においては電力、化学、鉄鋼などの産業の排出量が多かったが53年度には低硫黄燃料の確保や排煙脱硫装置の設置など公害防止のための努力が進められ、それら産業についても排出量はかなりの低下をみている(第2-3-15図)。
? 窒素酸化物
鉱工業生産に伴う窒素酸化物については、固定発生源によるものと移動発生源によるものがあるが、固定発生源に係る窒素酸化物の潜在発生量、除去量及び排出量の推移を試算すると第2-3-16図のようになる。窒素酸化物の潜在発生量はエネルギー消費の増大に伴い、48年度までは増加を続けたが、49年度以降は生産活動の停滞などによりエネルギー消費の伸びも鈍化したことからほぼ横這いで推移しているものとみられる。
一方、除去量は、48年8月の第1次規制以降排出規制が逐次強化・拡充されたことから、排煙脱硝装置、低NOx燃焼技術の普及が進み徐々に増加しつつある。
鉱工業生産活動による窒素酸化物の排出量は以上のような潜在発生量の伸びの鈍化及び除去量の増加により49年度以降減少に転じている。窒素酸化物は硫黄酸化物とは異なり、規制の歴史が浅いこと、また、燃料の改善による効果も硫黄酸化物ほど大きくないことから、必ずしも満足すべき改善を示していないが、今後は54年8月に実施された第4次規制の効果があらわれるものとみられる。
? COD
有機物による水質汚濁の代表的な指標であるCODについて、その潜在発生量、除去量、並びに排出量の推移を試算したものが第2-3-17図である。
CODの潜在発生量は、鉱工業生産活動の増大から48年度まで増加する傾向にあったが、49年度、50年度と不況による生産の落ち込みから減少することとなった。しかし、その後は、生産の緩やかな回復に伴い潜在発生量は増加を続けているものとみられる。
一方、CODの排出量は、45年度以降着実に減少しており、53年度の排出量は45年度の5割程度に削減されたものとみられるが、この背景には国の排水基準の強化・拡充とともに、都道府県による上乗せ排水基準の設定の効果があらわれているものと考えられる。
第2-3-14図 鉱工業生産活動による硫黄酸化物の潜在発生量、除去量及び排出量の推移(試算;SO2
第2-3-15図 産業別の硫黄酸化物排出量の推移(試算;SO2
(2) 新たな条件変化
1960年代の高度経済成長期は、鉱工業生産活動やエネルギー需要の急激な拡大に伴って鉱工業生産活動による環境負荷が増加し、産業公害の加速度的な進行をみた。しかし、1970年代に入って公害対策が進展し、それに対応した企業の公害防止努力も進み、経済が安定成長へと移行しつつあることもあって産業公害は深刻な状況を脱しかなりの改善をみることになった。80年代を迎え環境負荷をめぐる条件は、鉱工業生産の安定的な拡大の中でエネルギー情勢を中心に新たな条件変化が生じようとしている。
第一は石油情勢の流動化の中で、省エネルギーの推進とともに石炭、地熱など石油代替エネルギーの利用及び開発の促進が求められていることである。
第ニは、これまでの環境負荷の軽減に大きく寄与してきた低硫黄燃料の供給に変化が生じていることである。硫黄酸化物による大気汚染の防止対策の一つとして低硫黄燃料への転換が進められてきたが、今後は輸入原油の重質化が予想されており、重質油分解技術、重油脱硫技術など技術開発面の努力など十分な対応が求められている。