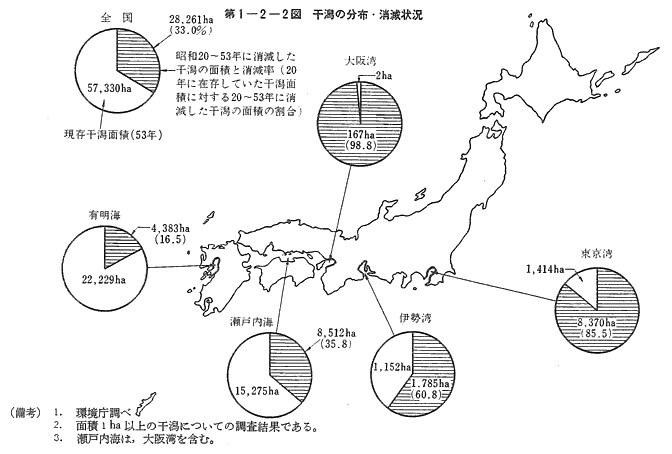
2 干潟
干潟は、潮の干満によって水没と干出をくり返す海と陸との接点に形成されている。そこでは極めて豊かな生命の営みが行われ、生物の種も多く、有機物の生産も大きいので、干潟は、そこに餌を求める渡り鳥の重要な渡来地でもあるなど多くの生物にとってその生活の場であるとともに、豊かな海水の浄化力を持ち、海陸の生態系全体にとって大きな意味を持っている。また、干潟は潮干狩や鳥類の観察など人と海とのふれあいの場としても貴重な自然である。
我が国においては、潮位差の少ない日本海側や北海道ではほとんど干潟は発達していない。全国の面積1ha以上の干潟について行われた「第2回自然環境保全基礎調査」の暫定集計結果によれば、我が国では53年現在5万7,330haの干潟が存在しているが、そのうち90%以上が千葉県以南の本州南岸、四国、九州にあり、かつ、瀬戸内海と九州西岸にその大部分が集中して存在している。瀬戸内海には全国の干潟の27%に当たる1万5,275ha、有明海には39%に当たる2万2,229haの干潟が存在している。
また「第2回自然環境保全基礎調査」では、20年からの埋立、干拓、浚せつなどによる干潟の消滅状況も調査している。これによると20年当時、8万5,591haに干潟が存在していたが、53年までにその33%に当たる2万8,261haが失われている。これを主要海域別にみると、工業用地の造成などのための海面の埋立が急速に進んだ東京湾及び瀬戸内海で、20年から53年の間にそれぞれ8,000haを超える干潟が消滅し、東京湾では20年当時存在していた干潟に対する消滅した干潟の割合が85.5%に上っている。また伊勢湾、大阪湾ではもともと干潟が東京湾ほど発達していなかったため消滅面積は少ないものの消滅率は高く、それぞれ20年当時存在していた干潟の60.8%及び98.8%が消滅してしまっている(第1-2-2図)。