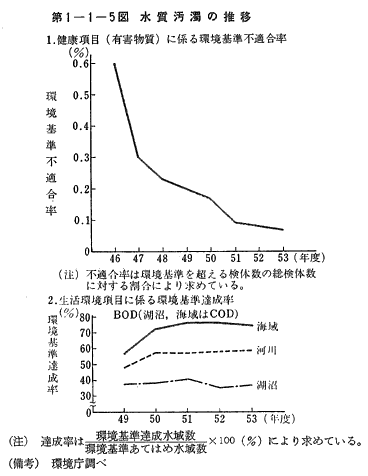
2 水質汚濁
水質汚濁に関する環境基準は、人の健康に有害な9物質(カドミウム、シアン、有機リン、鉛、クロム(6価)、砒素、アルキル水銀、PCB、総水銀)に関する健康項目と、利水上の障害などをもたらす有機物質等(pH、DO、BOD又はCOD、SS、大腸菌数などで測定される)に関する生活環境項目の2つ大別される。
(健康項目)
健康項目について、53年度公共用水域水質測定結果をみると全国5,061地点において測定された総検体数のうち、環境基準に適合していない検体数の割合(不適合率)は0.07%(52年度0.08%)となっており、かなりの改善を示している(第1-1-5図)。
有害物質を種類ごとににみると、アルキル水銀及び有機リンについては、前年度に引き続き全く検出されなかった。また、測定点の濃度の年間平均値で評価している総水銀についても、環境基準値を超えると評価される地点はなかった。その他の有害物質についても総体的に改善されている。
(生活環境項目)
生活環境項目については、53年4月までに環境基準の類型当てはめが行われたのは2,814水域(河川2,199、湖沼93、海域522)であるが、代表的な有機汚濁の水質指標であるBOD(またはCOD)の環境基準を達成している水域は、1,737水域(河川1,309、湖沼35、海域393)と全体の61.7%(前年度61.2%)となっており、最近の動きをみると全体としては横ばいで推移してきている。環境基準の達成率を水域別にみると河川59.5%(同58.5%)、湖沼37.6%(同35.2%)、海域75.3%(同76.9%)と湖沼で低く、海域で高くなっている(第1-1-5図)。
更に、「主要公共用水域の水質汚濁状況調査」をみると、都市内中小河川、都市を貫流する大河川などにおける水質汚濁状況は、かつての深刻な汚濁状況は脱したものの、依然として汚濁の程度が高く、また53年の結果をみると都市内中小河川のように、前年度に比べ汚濁が進行したものもあり、今後とも、改善のための努力が必要とされている(第1-1-6図)。
また、水質総量規制の導入(54年6月から導入)されている東京湾、伊勢湾、瀬戸内海の3閉鎖性水域の53年度の環境基準達成率をみると、東京湾61%(52年度61%)、伊勢湾53%(同47%)、瀬戸内海75%(同73%)と前年度よりもわずかに向上している。しかし、これらの3水域以外の海域では環境基準の達成率が77%と前年度の81%よりも低下している(第1-1-7図)。
また代表的な湖沼について、水質の汚濁状況をみると、霞ヶ浦(茨城)、琵琶湖(滋賀)、宍道湖(島根)などにおいて環境基準が達成されていない。
近年、湖沼や内海などの閉鎖性水域においては、工場排水や生活排水などからの大量の窒素、リンなどの栄養塩類の流入により、いわゆる富栄養化が進行し、このため、プランクトンや藻類などの異常発生がみられる水域もある。この結果、湖沼では、水道原水の着臭などがみられ、また、瀬戸内海、伊勢湾などの内海、内湾では、赤潮により魚介類のへい死などの被害がみられる。瀬戸内海における赤潮発生件数についてみると51年326件(うち被害を伴う件数18件)、52年236件(同27件)53年176件(同19件)、54年193件(同13件)と依然としてかなり多く、特に最近は赤潮の発生により漁業被害が発生している水域もある。
(海洋汚染)
我が国の周辺海域における海洋汚染の発生確認件数は、54年に1,733件と53年に比べ296件の増加となっており、油による海洋汚染が全体の約73%を占めている。
海域別にみると、全体の約59%に当たる1,028件が東京湾、伊勢湾、大阪湾及び瀬戸内海において発生している。また、タンカーから投棄されるバラスト水などの油分に起因すると推定される廃油ボールについては、依然として南西諸島から本州南岸に至る黒潮流域に沿った海域を中心にして、我が国沿岸への漂着は後を立たない現状にあり、加えて日本海などの今まで汚染の少なかった海域においても量的に多くなっているところがあり、今後の推移を見守る必要がある。